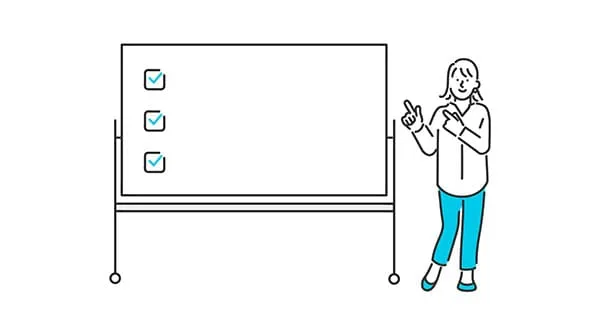適応障害でも続けやすい仕事 長く仕事を続けるためのポイントや症状が進行しやすい人の特徴を解説

仕事や職場の人間関係から生じる強いストレスが原因で心身の調子が崩れる適応障害。
仕事を続けるべきか、休職すべきか、悩む人は多いと言われています。
このコラムでは、適応障害の人が知っておきたい仕事を続けるコツや休職中の過ごし方、復職支援などをまとめて解説します。
適応障害と仕事・休職・転職などに関するコラムは、下記にまとめています。ぜひご覧ください。
目次
適応障害のある人に向いている仕事を探すときの4つの考え方

適応障害のある人は、向いている仕事を探すときに押さえておくべき考え方があります。
具体的には以下4つです。
- 主治医との繋がりを保つ
- 配置転換や業務内容の変更を話し合う
- 休職を検討する
- 一般論を踏まえた上で、「自分を基準に」「多角的に」検討する
これらについては、下記コラムで詳しく解説しています。適応障害と上手に向き合い、仕事を探したいときは、ぜひあわせて目を通してみてください。
適応障害のある人に向いてる仕事を探すときのポイント4選

適応障害のある人は、自分にとって向いてる仕事を探してみるのがオススメです。
具体的には以下4つのポイントを重視して選ぶのが効果的です。
- ポイント①業務内容
- ポイント②勤務形態
- ポイント③職場環境
- ポイント④福利厚生
仕事の向き不向きは人によって様々で、上述したポイント以外にも、興味・関心でも大きく変化します。
詳細については下記コラムで解説しています。参考にしながら自分に向いてる仕事を探してみてください。
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、適応障害の人のための就労移行支援事業所です。
- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月
新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。
適応障害のある人に向いてる仕事
適応障害でも続けやすい仕事を探している人(転職を検討している人)は、次の2点を意識してみてください。
- 業務が定型化しているか
- 職場環境で業務が左右されないか
適応障害のある人が続けやすい仕事の一例

業務内容が頻繁に変わるとストレスを感じやすい人は、定型化された業務であれば仕事を続けやすい可能性が高いです。
職場との不一致が大きく、ゆとりがほしい人は、自由度の高い業務が向いていると考えられます。
- 官公庁等の事務職
- データ入力管理業務
- 工場のライン担当
- 警備員
- 清掃員
- 検針員(ガス・電気)
- ファーストフード店(接客・調理)
- 配達員(郵便・新聞)
- スーパー(レジ・品出し)
- Webライター
- Webデザイナー
- 歩合制の営業職
- ドライバー(トラック)
- 翻訳家
- デイトレーダー
- アフィリエイター
- 製作者(音源・動画)
「実際のあなた」に向いている仕事は他にもあります
上記はあくまでも一般論です。
ご自身の性格、特性、職場の個別的な状況などによって、他にも向いている仕事はあります。逆に、上記の仕事が向いていない場合もあります。
「自分はどんな性格か」「この職場ならストレスを感じないか」など、あなた自身と勤め先との実際的な関係から、仕事の向き不向きを判断するようにしましょう。
仕事探しの際は、専門家を利用しましょう

適職を本格的に探したいなら、後述する就労移行支援事業所や、転職エージェントなどの専門家への相談をオススメします。
専門の支援員があなたの性格や特性に即した職種を提案してくれるでしょう。
適応障害のある人に向いてない仕事
適応障害のある人には、向いてる仕事がある一方で、できれば避けた方がいい仕事もあります。
ここからは適応障害のある人に向いてない可能性が高い仕事を紹介します。現在の症状を振り返りながら、自分にとって避けた方がいい仕事について見ていきましょう。
(参考:日本福祉教育専門学校「深田恭子さんも公表した「適応障害」とは何か。」、 福田尚法、森川友子「メンタルヘルス面で不安がある人に対する短期的就職支援方法に関する一提案」、 大阪精神障害者就労支援ネットワーク「精神障害者の一般就労のための特徴的な課題と就労継続支援における福祉・医療・企業の連携のあり方の調査研究」、 こころの耳「専門職として就職したものの事業撤退により専門外の仕事に従事したため休職に至った新入社員の事例:事例紹介」、 こころの耳「適応障害と私:こころの病 克服体験記」、 おおかみこころのクリニック「会社に行くのが怖い人は適応障害の可能性あり!仕事を続けるための対処法も紹介」、 おおかみこころのクリニック「適応障害の人にかける言葉3選|かけてはいけない言葉や支援のコツも」、 e-ヘルスネット「適応障害」、 こころの耳「ご家族にできること」、 大阪市「大阪市:【第39号】「家族が『うつ』になったら・・・~あせらず見守るために大切なこと~」医療法人 渡辺クリニック院長 渡辺 洋一郎 (…>文化・スポーツ・生涯学習>生涯学習)」、 NHK「適応障害とは?症状や治療法を解説 原因は強いストレス | NHK健康チャンネル」)
向いてない仕事①営業職

1つ目は「営業職」です。
その理由は、厳しいノルマが設定されていることが多く、強いプレッシャーによってストレスを抱えやすいためです。
営業職は基本的に断られることの多い職種。そのため、適応障害の症状によっては、気分の浮き沈みが激しくなり、辛く感じることも少なくありません。
適応障害があると、精神的にもろくなることもあります。そういった意味でも、営業職は避けた方がいい仕事と考えられます。
なお、賞与や条件などに惹かれてどうしても営業職に就きたいというときは、インサイドセールスやカスタマーセールスなど、厳しすぎるノルマがないものを選びましょう。
向いてない仕事②コールセンター
2つ目は「コールセンター」です。
コールセンターでは、通販サイトの対応をはじめ、商品や企業に対するクレーム対応などといった業務があります。
一般的な対応であればそこまでストレスを抱える機会はないものの、クレーム対応となれば厳しい言葉を受けることも珍しくありません。
あくまで商品や企業に対するクレームであっても、厳しい言葉や口調を浴びれば、どんな人も傷付くでしょう。
そういった意味でも、適応障害のある人は避けた方がいい職種と言えるでしょう。
向いてない仕事③技術職(プログラマーやエンジニアなど)

3つ目は「技術職(プログラマーやエンジニアなど)」です。
プログラマーやエンジニアといった技術職は、激務になりやすい職種です。長時間労働になったり、何日も泊まり込みで働いたりする人も中にはいるでしょう。
業務内容としても、アルファベットや記号をひとつでも間違うとエラーやバグなどにつながる恐れもあり、臨機応変さや慎重さが必要です。
適応障害のある人にとっては大きなストレスにつながりかねないことから、避けた方がいい職種と考えられます。
「実際のあなた」に向いている仕事である可能性はあります
上記はあくまでも一般論です。
ご自身の性格、特性、職場の個別的な状況などによって、いずれもあなたに向いている仕事である可能性はあります。
「自分はどんな性格か」「この職場ならストレスを感じないか」など、あなた自身と勤め先との実際的な関係から、仕事の向き不向きを判断するようにしましょう。
適応障害を経験した人が長く仕事を続けるためのポイント12選
精神科医であり医学博士の岡田尊司氏の著書『ストレスと適応障害 つらい時期を乗り越える技術』では、適応障害について「適応障害の特徴は、同じ環境(の変化)であっても、適応障害を起こすか否かは、個人差が大きいということである。その人にとっては非常に苦痛な環境も、別の人にとっては快適であるということもしばしばだ」としています。(参考:岡田尊司『ストレスと適応障害 つらい時期を乗り越える技術』 )
つまり、人によって適応障害につながる原因が違う(個人差がある)ために、周囲からの理解が得にくいということです。
適応障害を経験された人、さらには現在適応障害のある人が仕事を続けるためには、この特徴に留意し、工夫を取り入れながら取り組むことが大切です。
ここからは、適応障害の特徴を踏まえたうえで、適応障害を経験した人が長く仕事を続けるためのポイント12点を解説します。
就職または転職を検討している人は、参考のひとつとして今後にお役立てください。
なお、前提としては、「病院とのつながりを保つ」「自分一人で抱え込まず、(後で紹介するような)サポート団体を利用する」ということも大切です。
ポイント①症状について理解しておく

適応障害のある人が仕事を続ける場合は、自分自身の症状について知ることが大切です。
上述したように、適応障害の特徴は、環境(要因)・症状に大きな個人差があります。
誰かにとっては非常に苦痛な環境であっても、もう一方の誰かにとっては快適な環境であるケースも珍しくないというケースもあります。つまり、特徴・要因・症状の個人差がありすぎるために、周囲からの理解が得にくい場合もあるということです。
また、適応障害の代表的な症状には、「気分が塞ぐ(抑うつ気分)、イライラや不安が強い、集中力や根気がない、しなければいけないことに手がつかないといううつ状態によくみられる症状が多い」とあります。(参考:岡田尊司『ストレスと適応障害 つらい時期を乗り越える技術』 )
もし、周囲からの理解が得にくい職場で、抑うつ・うつ状態のときにみられる症状が出たときは、周囲に相談することもできず、一人で抱え込むという懸念もあります。
そうならないためにも、適応障害がありつつ仕事を続けるときは、必ず自分の症状について理解しましょう。そのうえで、どんな環境なら症状が見られにくいかを考え、理想的な職種・職場とはどんなところかを探してみましょう。
ポイント②柔軟な働き方が可能な職場を探す
適応障害の症状は、日によって強弱がみられることも珍しくありません。
そのようなときでも職場からの理解を得られ、休暇が取れるようであれば、長期にわたって働くことができるでしょう。
ポイント③求人票の内容を精査する

どれだけ条件の良い求人であっても、その内容に嘘・偽りはないかをきちんと調べることも大切です。
なかには人手不足を早く解決しようと、虚飾した好条件・好待遇の求人を公開する企業もないわけではありません。
魅力的な求人内容であったとしても、社員評価を閲覧できる情報サイトや口コミに目を通したりして、内容について精査しましょう。
ポイント④口コミ・SNSで企業の評判を調べる
求人票の項目でもお話ししたように、勤務先の評判はあらかじめチェックしておくことをおすすめします。
求人票の情報だと、企業の良い面しか把握できない可能性があり、働き始めたあとに適応障害の症状が悪化する懸念があります。
実際に働いた経験がある人の口コミや評価などは社員評価を閲覧できる情報サイトのほか、SNSでも確認できます。
ただし、口コミばかりを鵜呑みにするのは厳禁です。退社した人のなかにはネガティブな理由から退職を選んだ人も少なくないためです。
口コミやSNSなどを使って企業の評判を調べるときは、求人内容との齟齬や適応障害に対する理解度、各部署の雰囲気などをチェックすると良いでしょう。
ポイント⑤適応障害に対して理解があるかを調べる

働き続けられる仕事・職場を探すなら、適応障害に対して理解があるかを調べることも大切です。
適応障害には、環境(要因)・症状に大きな個人差があるという特徴があります。
そのことから、環境や要因によっては周囲から理解を得にくいことも少なくありません。
長く仕事を続けたいという意思をお持ちであれば、その意思を尊重し、さらには適応障害についても理解のある(深めてくれる)企業を探しましょう。
例えば、面接時に担当者に確認する、ご自身の傾向についてお伝えしてその反応を伺うなどして、理解があるかを調べてみてください。
ポイント⑥自分の長所を活かせる職場かを調べる
適応障害がありつつも働き続けられる仕事を探すなら、自分の長所が活かせる職場も有効です。
長所を大いに活かせる仕事であれば、適応障害があっても無理なく続けられる可能性があります。
そのためには、まず自分の長所について洗い出すことが大切です。
自分の長所・短所について紙に書き出し、どんな仕事が向いているのかを探ることで見つけやすくなるでしょう。
ポイント⑦同僚や上司を頼れるようになる

適応障害の人は、周囲からの評価が気になるため、職場でも萎縮しがちです。緊張状態が続くことでストレスが溜まりやすくなっています。
そのため、症状緩和や再発防止には、同僚や上司を少しでも頼れるようになることが有効です。困ったことがあれば、時間を取って、同僚や上司に相談するようにしましょう。
ポイント⑧規則正しい生活をする
不規則な生活が適応障害の症状を悪化させる場合があります。
- 睡眠不足で注意力が落ちてミスが多発する
- 腹痛のせいで仕事中も落ち着かない
- 二日酔いで体力がもたない
睡眠不足が数日間続くと、うつ病や統合失調症などのある人に似た脳機能の変化が見られ、抑うつ傾向が強まるという研究結果も出ています。(参考:Science Portal「睡眠不足で情動不安定や抑うつに」)
乱れたコンディションによって仕事に苦手意識がつかないよう、生活習慣を整えましょう。夜更かしや夜食を避けて早めに就寝するなど、規則正しい生活を送ることが大切です。
ポイント⑨完璧主義を解消していく

完璧主義だと、些細なミスでも自己評価の低下につながりやすくなります。「こんなミスをするなんて…」と自分を責めすぎることで、あらゆる仕事が自分にマッチしていないと感じやすくなります。
ミスは誰でもするものです。自分が気にしすぎているだけで、上司や同僚はほとんど気に留めていない場合も多々あります。完璧主義で自分を追い詰めることのないように、考え方を見直す視点も大切です。
ポイント⑩定期的にカウンセリングを受ける
定期的にカウンセリングを受けることで、適応障害の再発を防げる可能性があります。特に仕事のことを相談できる相手や友達が少ないという人は、カウンセリングの場でストレスを緩和するとよいでしょう。
カウンセラーは、ネット検索などで探すほか、主治医に紹介を依頼することもできます。なお、カウンセリングはいろいろな人や団体が行っていますが、一般論としては、臨床心理士または公認心理師が行うものは信用できます。
もちろん、カウンセラーとの相性も大切です。「このカウンセラーは合わない」と思ったら、我慢せずに自分に合う別のカウンセラーを探すようにしましょう。
勤務先に産業医がいる場合には、産業医を利用するのも一つの手段です。中立的な立場から相談を聴いてもらえるため、面談の結果が給与査定や昇進に響くこともなく、安心して話すことができるはずです。
労働者の健康管理に関して専門的な立場から助言や指導を行う医師のこと。産業医は労働安全衛生法に基づいて、常時50人以上の労働者を使用する事業所に1人以上、3,000人超の事業所では2人以上が配置されています。診察にあたって料金は発生しません。(参考:厚生労働省「産業医について」)
ポイント⑪情報入力を減らして休みを重視する

適応障害の再発防止のために、小まめに休みを入れて、仕事とのバランスを取ることを意識しましょう。特に、休んでいるときは、脳への情報入力を減らすように心掛けてください。
休みの日でも気がつくとスマートフォンを操作しているという人は、神経が休まっていない可能性があります。音楽や映像などを長時間視聴することでリフレッシュできていると思っている人も同様です。
情報に負荷を掛け続けていると、脳や目が疲れたままになりがちです。部署や担当業務が変わったタイミングなどは、特に脳が容量オーバーを起こしやすいときなので、日々の情報入力を減らす努力が必要になります。
ポイント⑫休職という選択肢を残しておく
モチベーションを高く保って仕事を続けることは素晴らしいことですが、「休むわけにはいかない」という気持ちがプレッシャーになっていることがあります。長く仕事を続けるためには、休職という選択肢も頭の片隅に残しておくことも大切です。
休職制度は法律で定められているものではなく、各勤め先ごとに定められています。まずは、ご自身の勤め先の規定について確認してみてください。
また、勤め先によっては、休職中も一部、給与が支給されるところがあります。給与支給がなくても公的な経済支援は複数ありますので、休職という選択肢も考慮に入れるようにしましょう。
仕事で適応障害の症状が進行しやすい人の特徴6選

仕事で適応障害になりやすい人には、以下の特徴が見られます。
- 完璧主義
- 人目に敏感
- 切り替えが苦手
- 相談相手がいない
- 他人の評価を気にしやすい
- ちょっとした言動に傷つきやすい
ただし念頭に置いてほしいのは、上記特徴がある人が全て適応障害になるわけではないということです。適応障害になるときは、「職場適性との不一致」などの「原因・ストレス」があるからです。
「適応障害は自分の性格や甘えによるものではないか」と自分を責めるのではなく、仕事や職場環境との相性を考えた上で、医師や支援者ともしっかり話をしましょう。
仕事で適応障害の症状が進行しやすいケース3選
「仕事による適応障害」の場合、役職や環境の変化に伴って発病するケースが多いようです。特に要注意な具体例と併せて紹介します。
ご自身にも思い当たるものがあるか、苦しくならない範囲で考えてみると、今後の参考になると思います。(参考:松﨑博光『新版 マジメすぎて、苦しい人たち:私も、適応障害かもしれない…』 )
変化①転職や異動で環境が変わった

転職や異動によって環境に変化があると、慣れない業務や人間関係に適応するために気を遣う機会が増えます。自覚がなくてもストレスが溜まりやすいときです。
研修環境に慣れてきたばかりの時期に、また新しい環境に移るときは要注意です。「新社会人生活」の諸々で蓄積した疲れも相まって、容量オーバーを起こして適応障害につながることがあります。特にメンターがいない職場では相談相手を作りづらいため、一層の注意が必要です。
変化②昇進で立場が変わった
昇進すると、部下や上層部などとの関係が変わり、気を遣うことが増えてきます。「従来の仕事」に加えて、上司や管理職としての新たなスキルが必要とされる時期です。
管理職になると、部下を指導・サポートする必要があります。年齢差などによってメンバーと意思疎通がうまく図れずに、パンクする人もいるでしょう。特に「扱いづらい部下」がいる場合は、注意が必要です。責任による重圧も増してくるときなので、昇進が適応障害のきっかけになることがあります。
変化③仕事に慣れて業務量が増えた

役職や環境の変化がなくても、「いつのまにか業務量が増えていたこと」が適応障害につながる場合があります。仕事に慣れてくると、本人も気づかないうちに働きすぎていたということは少なくありません。
同じ部署に長くいる中堅ポジションの実務担当者は、気がつくと仕事を任されがちです。本人も業務に慣れているので「これくらいは大丈夫」と軽く考えやすくなっています。しかし、業務量の変化に心身が適応できずに、いつのまにか調子を崩しているというケースがあります。
適応障害になったら仕事から距離を置くのが有効
適応障害かどうかに関わらず、体調が悪い場合は、病院に行くことをオススメします。
そして、適応障害と診断され、その原因(となるストレス)が仕事に関係するようなら、仕事・職場と距離をひとまず置きましょう。また、薬を処方されたら、用法・用量に従って、忘れずに服用しましょう。
「仕事と距離を置く」とは?

一般的には、次のような対応が考えられます。
- 有給休暇の取得
- 休職(※)
- 療養休暇(※)
※療養休暇や休職は、職場によって規定や申請方法が異なります。あなた一人での確認・申請が難しいなら、医師・上司・家族などを通じて対応しましょう。
無理に仕事を続けて症状が慢性化すると、適応障害はうつ病に移行する恐れがあります。うつ病になると、回復までの時間が長引く可能性があります。しっかり療養しましょう。
今すぐの退職はオススメしません
仕事と適応障害が関係する場合、「この仕事・職場は向いていない、今すぐ退職しなければ」と考える人もいるようです。ですが、退職は後からでもできます。
病気で判断力が鈍っているときに重大な決断をあせって行おうとせず、まずは「休む」という選択をオススメします。
休んでいる間に今後の方針を考えましょう

仕事・職場から離れているうちに、医師・上司・家族などとも話して、今後の方針を考えていきましょう。ただし、もちろん治療・療養が最優先です。
元の職場に復帰したい場合は
療養後に、退職・転職ではなく、元の職場に戻りたい場合には、次のような対応を職場と話し合いましょう。
- 異動や配置転換
- 業務量の調整
- 担当業務の変更
適応障害で仕事を休職したときの過ごし方
適応障害を完治させるために休職を選択する場合、まずは休養に専念してください。その上で、意識するとよいことをお伝えします。
なお、適応障害で休職した場合の過ごし方は下記コラムで詳しくまとめています。適応障害があり、現在休職を検討中の方はあわせてご覧ください。
過ごし方①ストレスを抱えない過ごし方を心がける

適応障害には、その原因となるストレスがあります。
適応障害の症状を悪化させないためにも、まずは原因となったストレスの根源から離れ、リフレッシュすることに専念しましょう。
そうすることで、適応障害の症状は回復していきます。
また、適応障害がある人にとっては、「適応障害の原因となったストレス」以外のストレスも大敵です。
症状の悪化、さらにはうつ病につながる懸念もあることから、できる限りストレスを抱えない過ごし方を心がけましょう。
過ごし方②職場へのホウレンソウは欠かさない
休職中は、定期的な面談や通院・カウンセリング内容の報告・診断書の提出を求める職場も珍しくありません。
適応障害について理解を深めてもらうためにも、報告・連絡・相談の「ホウレンソウ」を欠かさず行うよう努めましょう。
過ごし方③転職を含めて将来を考える

症状が緩和・回復しはじめると、今後について考えられる余裕ができていきます。
心身のバランスが安定しているときは、転職を含めて将来を考えてみるのもよいでしょう。
転職についての情報収集はもちろん、自分にとってどんな仕事が向いているのかを調べてみるのも効果的です。
転職を検討するときは、こちらを参考になさってください。
適応障害で休職中の方にオススメの考え方
休職中は「一刻も早く回復して職場に戻らないと!」という焦りが湧いてくるかもしれません。休んでいるあいだの業務が気になるという人もいるでしょう。そういう人には、以下のような考え方がオススメです。
- いまは思い切って休みを取り、回復を優先しよう
- 療養するのが仕事だと思ってしっかり休もう
- 復職のことは元気になって判断力が戻ってから考えよう
これらを意識することで、心身共に回復へとつながり、前向きな気持ちが持てるようになります。
休職中は、誰しも責任感の強さから、会社や周囲、将来に対して不安や心配事を抱えてしまうものです。
しかし、今はあくまで休職中であり、休んでも良いと許可を得ています。このようなときは、会社や仕事のことではなく、自分の体のことを最優先に考えるのが大切です。
休職中の過ごし方としては、心身の休息が最優先です。そのうえで、ここからは補足しておきたい2点について解説します。
通院は続けましょう

休職中は、医師の指示のもと、定期的な通院を続けてください。
あなた自身の回復過程を確認するためだけでなく、人事担当や上司への報告のためにも定期的な診察は必要です。薬を処方されている場合は、服薬を怠らないように気をつけましょう。
回復の兆候が見られたら
すでに回復の兆候が見られる段階では、以下のような過ごし方がオススメです。
- 仕事をしていたときと同じ生活リズムの維持を心がける
- 散歩など、無理のない範囲での運動を始める
- カフェや図書館などに通って、勤務訓練の準備をする
適応障害からの回復が見られれば、医師から、職場復帰に向けた具体的なプロセスに関する話が出てくるはずです。休職中の過ごし方も含めて、主治医との情報共有・相談を忘れないようにしましょう。
適応障害で仕事を休職した後の復職の流れ
適応障害で休職した後に復職をする場合、流れとして3つの過程を辿ることになります。「復職が怖い」とお思いかもしれませんが、きちんと手順を踏めば、大丈夫です。
流れ①医師から復職可能の診断を受ける

まずは、専門医から「復職が可能である」という診断書をもらう必要があります。復職のためには、基本的には人事部門への診断書の提出が必要です。「本人の希望」だけでは復職が認められないケースが一般的です。
医師と話す際には、体調だけでなく、日々の生活や行動についても聞かれるでしょう。生活習慣が整っていて、具合が安定していると判断されると、復職は近づきます。復帰直前に調子を崩さないよう、無理をせずに、医師に相談しながら手続きを進めることが大切です。
流れ②業務や異動について、上司や人事担当者と相談する
医師の許可が下りたら、復職後の仕事の内容や業務量について、上司や人事担当者と話を詰めていきます。
適応障害の原因になったストレスが何なのかを伝えながら、苦手な業務や職場環境を、きちんと伝えましょう。配置転換を打診される場合もあります。また、上司や人事担当者は、「復職直後は業務に慣れるまで疲れやすい」と理解しているはずです。そのため、「最初は時短勤務で」などと提案されることも多いです。
「自分は大丈夫だ」と思っていても、体力が戻っていないケースがほとんどなので、基本的には提案に乗ることをオススメします。
流れ③必要な人事書類を提出して復職する

業務調整が済んで必要な人事書類を提出したら、いよいよ復職です。勤め先によっては、「復職当日の前に、あいさつも兼ねて職場に来てみたら?」などと提案されることもあります。
復職当日の出勤のハードルを下げることにもつながりますので、可能であれば、職場を事前に訪問しておくとよいでしょう。
復職後は、適度に休暇を入れながら業務に慣れていくことが大切です。復職後もサポートをしてくれる人たちはたくさんいますので、安心してください。
職場によっては、復職後数週間などを目安に産業医面談がある場合もあります。無理をしていると感じることがあれば、その際に素直に伝えるようにしましょう。
適応障害で仕事を休職・退職したときの経済支援6選
適応障害で仕事を休職・退職した人が受けられる経済支援は複数あります。「実際にあなたが受給できるかどうか」「どの程度の経済支援を受けられるか」は、個々の状況によって異なります。
「経済的支援はたくさんある」と安心していただいた上で、「あなたに向いた支援」は、自治体の窓口などと相談することでわかっていくと思います。
経済支援①傷病手当金

傷病手当金は、病気による休業中に、健康保険の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられている制度です。「病気やケガで勤め先を休んでいて、かつ給料の支払いがない」などの人が対象になります。受給額は、「それまでの給料」などによって変わります。(参考:全国健康保険協会「傷病手当金」、「傷病手当金について」)
- 全国健康保険協会
- 各健康保険組合
- 各共済組合
傷病手当金の詳細は、下記コラムをご覧ください(うつ病の方に向けた内容ですが、適応障害の方にもほぼ当てはまる内容です)。
経済支援②自立支援医療制度
自立支援医療制度とは、精神疾患で継続的な通院が必要な場合などに、医療費の自己負担額を軽減できる公費負担の医療制度です。(参考:東京都福祉保健局「自立支援医療(更生医療) 」、東京都福祉保健局「心身障害者医療費助成制度(マル障)」)
通常3割の医療費自己負担を、原則1割まで軽減することができます(つまり、通院や薬の費用を通常の3分の1にすることができます)。
世帯の総所得額によって、自己負担上限額が定められていたり、対象外となったりする場合があります。また、具体的な内容・条件・名称は、自治体によって異なります。
- お住まいの市区町村の窓口
- (かかりつけの病院)
経済支援③失業手当(雇用保険給付)

失業手当は、適応障害に限らず、失職した人(仕事を辞めた人)が、就職するまでの一定期間、受給できる給付金です。(参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」)
原則的には、以下の2点が給付の条件になります。
- 退職までの一定期間、雇用保険に加入していたこと
- 求職活動を行っていること(窓口相談や職業訓練も含む)
受給期間や金額は、個々人の状況によって異なります。また、「基本手当」に加えて、病気やケガによって求職活動ができない状態の場合は、「傷病手当」という給付金を別途受給できることもあります(ただし、傷病手当は、先述した傷病手当金と同時受給はできません)。
経済支援④障害者手帳
適応障害の症状によっては、障害者手帳を取得できます。障害者手帳を取得すると、次のような支払いが減免されることがあります。
- 所得税・住民税
- 医療費
- 各種公共料金(公共交通機関の運賃、上下水道料金、NHK放送受信料、携帯電話料金、公共施設の入館料等)
また、失業保険の給付期間が延びたり、(再)就職や転職の際に障害者枠の利用ができたり、というメリットもあります。
障害者手帳によるメリットの詳細は、下記コラムをご覧ください。
経済支援⑤障害年金

障害年金とは、病気やケガで生活や仕事に支障が出ているときに、年金加入者が受給できる年金です。
「年金」というと「高齢者が受給するもの」というイメージもありますが、障害年金は、現役世代の方も受給できます。また、働きながら受給することもできます。
- 市区町村に設置された、障害年金相談センター
- NPO法人障害年金支援相談ネットワーク
障害年金の詳細は、下記コラムをご覧ください。
「適応障害だと障害年金を受給できるの?」とお聞きされることがあるので紹介しましたが、適応障害は、原則的には障害年金の受給対象ではありません。ただし、適応障害以外に、障害年金の対象となる病気・障害がある(または適応障害がうつ病相当であると認められる)場合などには、受給できることもあります。気になる方は、医師に相談してみましょう。
経済支援⑥生活保護
生活保護とは、病気やケガなどで就労できない人や、働いていても極端に収入が少ない人に現金を支給し、最低限の生活ができるように支援する制度です。(参考:厚生労働省「生活保護制度」)
食費・被服費・光熱費・家賃・医療費など、生活に必要な各種費用を受給できます。
- お住まいの市区町村の福祉事務所
- 市区町村役所の生活保護担当課
「適応障害だと生活保護を受給できるの?」とお聞きされることがあるので紹介しましたが、一般的には、「適応障害だから」という理由だけでの受給は難しいようです。状況によっては受給できるかもしれませんが、他の支援を検討・申請する方がより確実だと思います。
生活保護の詳細は、コラムをご覧ください(うつ病の方に向けた内容ですが、適応障害の方にもほぼ当てはまる内容です)。
⑦その他

「労災保険」「生活困窮者自立支援制度」という支援制度もありますが、これらも、生活保護と同じく「適応障害だから」という理由での受給は、一般的には難しいようです(状況によっては受給できるかもしれませんが、他の支援を検討する方がより確実だと思います)。
適応障害で「仕事が怖い」という人が利用できる復職支援2例
適応障害からの復職を考えている人の中には、仕事そのものに恐怖を感じて、復職に踏み切れない人もいます。そうした人に対しては「支援団体による相談支援」と「リワーク・プログラム」が有効です。
復職支援①各種支援団体での相談支援

適応障害に限らず、抑うつ症状などに悩んでいる人には、各種支援団体が相談支援を実施しています。
全国に設置されている精神保健福祉センターでは、メンタル不調について無料で相談支援を行っています。症状に関する悩みだけでなく、病院の選び方や、カウンセラーの探し方まで、精神保健に関わる幅広い相談に乗ってもらえることが特徴です。
相談支援を受ける際には、診断書は必要ありません。「自分が適応障害かどうかまだわかっていない」という人でも利用できます。
「病院に行くことに抵抗があるので、まずは精神保健福祉センターと話をする」という利用方法も可能です。(全国の一覧はこちらです)
復職支援②リワーク・プログラム
リワーク・プログラムとは、適応障害やうつ病などの精神疾患が原因で休職をしている人を対象とする、復職・再就職(転職)に向けたリハビリテーションのことです。(参考:一般社団法人 日本うつ病リワーク協会「リワークプログラムについて」)
参加者は、プログラムに応じて、以下のようなリハビリを受けられます。
- 通勤を想定した支援機関への定期的な通所
- 業務に類似した内容のオフィスワークや軽作業
- 職場でのコミュニケーションのための対人技能訓練
- ストレス対処に向けた自己分析や感情のマネジメント
原則的には「休職者」が利用できます(実施団体によっては、「退職者」も利用できます)。
利用には料金が掛かりますが、健康保険や自立支援医療制度による負担額の軽減が可能です。医療機関や地域障害者職業センター(全国の一覧はこちら)で実施されているため、気になる人は、お近くの団体に問い合わせてみるとよいでしょう。
リワークの詳細は、下記コラムをご覧ください。
補足:就労移行支援事業所

こちらで詳しく紹介しますが、一部の就労移行支援事業所にて、休職中の方の支援を行っている場合もあります。
その場合、自治体判断・要件をクリアする必要がありますが、私たちキズキビジネスカレッジでも休職中の方の利用実績あります。
ぜひご相談ください。
適応障害後の転職・再就職をサポートする団体3例
適応障害の後には、結果として元の職場を退職して新しい仕事を探す人もいます。
そんなときは、サポートする団体を利用することで、「あなたに合う仕事・職場」が見つかりやすくなり、心身の安定や長期就労にもつながります。
団体①転職エージェント

「元の職場への復帰」ではなく、転職を考えている方は、民間の転職エージェントの利用が考えられます。
転職先に適応障害のことを明かさないクローズ転職で利用できるのはもちろん、近年では、病気や障害のある方への転職支援も行っているところがあります。
転職エージェントは在職中・休職中・退職後のいつでも利用できます。いくつか話をしてみて、ご自分に合いそうなところを(並行的に)利用してみましょう。
団体②ハローワーク
ハローワークでは、障害について専門的な知識を持つ担当者が、仕事に関する情報提供や、就職に関する相談など、きめ細かい支援体制を整えています(参考:ハローワーク「障害のある皆様へ」)。
- 仕事の探し方や履歴書の書き方など、仕事に関する様々な相談
- 希望に応じて、より専門的なサポート機関など(障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、職業訓練)の紹介
- 障害者を対象とした求人情報の提供
ハローワークの全国一覧はこちらです。
団体③就労移行支援事業所

転職を考える場合には、就労移行支援事業所の利用もオススメです。就労移行支援事業所は、病気や障害のある方の就職・転職を援助する福祉サービスです。各事業所は、公的な認可を得た民間事業者が運営しています。
サービス内容は、下記のように多岐に渡ります。
- 転職のための知識・技能の習得
- 履歴書・経歴書の作成支援
- 職場体験実習(インターン)の紹介
- 転職先候補の紹介
- 転職後の職場定着支援など
利用の可否は、お住まいの自治体が、下記の条件などに基づいて判断します。
- 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などがある
- 18歳以上で満65歳未満の方
- 離職中の方(例外あり)
※上記を満たすなら、障害者手帳を所持していなくても利用可能です。
- お住まいの市区町村役所
- 各就労移行支援事業所
就労移行支援事業所の詳細は、下記コラムをご覧ください。
適応障害の方が就労移行支援事業所を通じて適職を見つけた体験談

20代・Fさん。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ通所期間1年1か月後に就職。就職後は定着支援も利用。
Fさんは現在、中小IT企業のシステムエンジニア(SE)として、一般枠の正社員で週に5日(2日出社、3日在宅)、フルタイムで働いています。働きはじめて半年が過ぎ、自信もついてきました。
そんなFさんですが、学生時代から発達障害(ADHD)の特性に悩み続け、新卒で入社した会社では環境が合わずに適応障害にもなりました。
詳細は下記からご覧ください。
改めて、適応障害とは?
ここまで、適応障害の人が仕事を続けるコツ、休職中の過ごし方、復職支援などを解説してきました。
この章では、改めて適応障害の概要を紹介します。(参考:アメリカ精神医学会『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、松﨑博光『新版 マジメすぎて、苦しい人たち:私も、適応障害かもしれない…』)
①適応障害の概要

厚生労働省e-ヘルスネットは、適応障害のことを次のように解説しています。
日常生活の中で、何かのストレスが原因となって心身のバランスが崩れて社会生活に支障が生じたもの。原因が明確でそれに対して過剰な反応が起こった状態をいう。
「適応障害(てきおうしょうがい)」
「原因として、『何かのストレス』が明確である」ということがポイントです。
②適応障害の症状の例
適応障害には、次のような症状の例があります。
憂鬱な気分(抑うつ気分)、不安感が高まる、無気力、集中力の低下、わけもなく悲しくなる、イライラする、細かいことがいつまでも気になる、記憶力の低下
衝動的な言動の増加、たばこや飲酒の量の増加、喧嘩や自傷行為、強い貧乏ゆすり等
動悸、頭痛、冷や汗、息苦しさ、過呼吸、手先や唇の震え、倦怠感、耳詰まり、耳鳴り
※ただし身体症状は、適応障害とは別の内臓疾患に起因する場合もあります。
③仕事現場での状態の例

適応障害になった場合、特に仕事の現場では、以下のような状態になることがあります。
- 欠勤、遅刻、早退が多くなる
- 出勤するだけで動悸や息苦しさを感じる
- 書類の記入ミスやデータの入力間違いが増える
- 同僚や取引先とのコミュニケーションで口論になる
- 話し合いを嫌がり、人付き合いを避けるようになる
- 業務中にイライラしたり泣きたくなったり情緒不安定になる
④適応障害の原因
適応障害は、「何かのストレス」が原因で起こります。特に仕事に関連して適応障害になったときは、次のような原因が考えられます。
- 職場環境
- 人間関係
- ハラスメント
- 担当業務
- ノルマやプレッシャー
- 働き方(勤務形態)
- 通勤手段
⑤適応障害は、ストレスの原因がなくなると続かない

適応障害は、「ストレスの原因がなくなった場合、症状はそれから6か月以上は続かない」と定義されています。(参考:アメリカ精神医学会『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』)
そのため、治療のためには、原因であるストレス(仕事の場合は仕事)から離れることが効果的です。仕事から離れて長期休暇を取るだけで回復する人もたくさんいます。
⑥薬物療法・心理療法もある
薬物療法や心理療法といった治療法もあります(復職後の再発や症状の慢性化を防ぐ効果もあります)。医師と話した上で、治療法を決めていきましょう。
文字どおり、抗不安薬や睡眠薬などの薬物を服用して症状を緩和していく治療法
認知行動療法など、自分の心に働きかけて「ストレス」の捉え方や付き合い方を変えていく治療法
⑦うつ病と適応障害は違うもの

うつ病と適応障害は症状が非常に似ていますが、次のような違いがあります。
- 適応障害:明確な原因(ストレス)がある。原因から距離を置くと症状は消える
- うつ病:明確な原因が不明なこともある。また、原因がなくなってもすぐには回復しない
その上で、適応障害による症状が悪化したり長引いたりすれば、うつ病に移行する可能性があります。
まとめ:仕事で適応障害になったら、まずは休暇を取ることが大切です

仕事での適応障害は、業務や職場環境への不適応(ストレス)が原因で起こります。仕事に関連して適応障害になったなら、まずは仕事から離れて休養を取ってください。その上で、専門医の診断に従いながら、ゆっくりと治療を進めていくことが大切です。
休職しても、経済的な支援はたくさんあります。また、復職や転職をサポートする団体もたくさんあります。安心して静養に励みましょう。このコラムが適応障害に悩んでいる人の助けになれば幸いです。
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
執筆寺田淳平
てらだ・じゅんぺい。
高校2年の春から半年ほど不登校を経験。保健室登校をしながら卒業し、慶應義塾大学に入学。同大学卒業後の就職先(3,500人規模)で人事業務に従事する中、うつ病を発症し約10か月休職。寛解・職場復帰後、勤務を2年継続したのち現職のフリーライターに。
2019年に一般財団法人職業技能振興会の認定資格「企業中間管理職ケアストレスカウンセラー」を取得。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→
適応障害の自分が長く仕事を続けるためのポイントを知りたいです。
一般論として、次の6点が考えられます。(1)同僚や上司を頼れるようになる、(2)生活習慣を整える、(3)完璧主義を解消していく、(4)定期的にカウンセリングを受ける、(5)休むときは脳への情報入力を減らす、(6)休職という選択肢を残しておく。詳細はこちらをご覧ください。
適応障害の自分が続けやすい仕事を知りたいです。
例として、次のような職種があります。官公庁等の事務職、データ入力管理業務、警備員、検針員、ファーストフード店、配達員、スーパーの店員。他にもあり、理由も併せて紹介しますので、詳細はこちらをご覧ください。