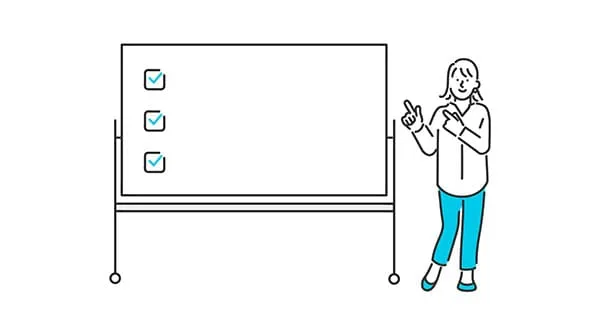適応障害で退職する方法と伝え方 退職前の確認事項や退職後に受けられる支援を解説

職場の人間関係や仕事のミスマッチが原因で起こる適応障害。
早めに退職して環境を変えた方がいいのでしょうか?
退職すべきか悩んでいる適応障害のあなたに向けて、適応障害で退職する方法と伝え方や退職前の確認事項、退職後に受けられる経済支援やサポート団体などを紹介します。
前提として、適応障害による退職・休職・転職などは「逃げ」ではありません。もし、「逃げ」だとしても問題ありません。
「人間誰しも、合わない環境はある」と考えることで、「次の一歩」にも進みやすくなると思います。
目次
適応障害で退職する方法と伝え方
この章では、適応障害で退職する方法と伝え方を解説します。
実際に「退職する」と決めたなら、職場にその意思を伝えましょう。
一般的には「退職したい」で話は通じる

この段階までに適応障害に関連する相談や休職などを行っていれば、「退職したい」と伝えるだけで、一般的には話が通じると思います。
諸々の事情で適応障害のことを相談できていなかった場合には、この段階で伝えてもよいでしょう。また、職場以外にしっかり相談ができているようなら、適応障害のことはあえて伝えないという選択もあります。
お勤め先のルールに従って申請
お勤め先のルールに従って、退職届を作成し、提出しましょう。通常は「自己都合退職」として処理されます。
退職事由をどう書くか?
退職届に書く退職事由・退職理由は、「一身上の都合」で大丈夫です。適応障害と関連させる必要はありません。
退職を引き留められたら?

退職の意図を伝えると、引き留められることもあります(この段階まで相談できていなかったのならなおさらです)。また、それまでの相談時よりも具体的・積極的な対応を提案されることもあります。
適応障害の原因であるストレス要因から離れられるような提案があれば、医師やカウンセラーなどにも改めて相談した上で、現職に留まるという選択肢もありえます。
退職がうまくいかなそうだったら?
退職届の受理を拒まれたり、引き留めを断りづらかったりする場合は、先述の法テラスなどに相談してみましょう。
- 法テラス(国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」)
- 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省の委託事業)
- 各市区町村役所が行う、法律やお悩みの相談会
適応障害の人が退職前にできる3つのこと:「まずは休職」がオススメ

この章では、「仕事・職場が原因で適応障害になったけど、退職はしたくない」とお思いの方のために、「退職しなくても『同じ勤め先』で働き続けるための方法」をご紹介します(「退職の決心がついている」という人も、念のためご覧になることをオススメします)。
まずは、「適応障害になっても退職しない方法はある」という安心材料になると思います。その上で、「実際のあなた」がどう実施していくか、別の方法はあるかなどは、職場の方・医師・就労支援を行う団体などに相談することで、より具体的に見つかっていくと思います。
※すでに退職済みの場合は、こちらの章に進んで問題ありません。
前提①症状が重いなら休みましょう
適応障害の診断が出ているかどうかに関わらず、現時点で出社拒否などの重い症状がある場合は、ひとまず休暇を取得して休むことを優先してください。
前提②医師の診断を受けましょう
「自分は適応障害かどうかわからない」という段階の方は、専門医の診断を受けましょう。適応障害であってもなくても、心身の不調は、治療につなげることが大切です。薬を処方された場合は、用法・用量に従って、忘れずに服用しましょう。
方法①休職を取る
「いきなり退職」ではなく、まずは休職を取りましょう。
「自分は休まなくて大丈夫」「休職せずに仕事を続ける方法はないか?」と思うかもしれませんが、適応障害を治していくためには、原因(=仕事・職場)から離れることが効果的です。「休職」という形がどうしても嫌なら、「長期の有給休暇」も主治医と相談してみましょう。
- 職場によっては、引き続き給料(の一部)を受け取ることができる
- 休養に専念できる(※1)
- 退職するかどうかをじっくり考えられる(※1)
- 休職者限定の支援を受けられる(※2)
- (主治医の許可があれば)休職中に転職活動を行うことも可能
※1:「退職するかどうか」という重大な決断は、あせって行わず、療養を行いながらじっくり考えることが大切です。
※2:求職者限定の支援には、傷病手当金やリワーク・プログラムなどがあります。
病気による休業中に、加入している健康保険からお金を受給できる仕組みのこと。後述するように、退職後も継続して受給できる場合があります。傷病手当金の詳細は、下記コラムをご覧ください(タイトルに「うつ病」とありますが、適応障害の方にも参考になる内容です)。
適応障害などの精神疾患が原因で休職している人を対象とする、復職・再就職(転職)に向けたリハビリテーションのこと。参加者は、対人技能訓練やストレス対処の講習を受けながら、安定した就労に向けた準備ができます。リワークの詳細は、コラムをご覧ください。
※その他、適応障害で休職中のオススメの過ごし方は、下記コラムをご覧ください。
方法②担当業務の内容・量を相談する

仕事の関係で適応障害になった場合、担当業務の内容や量があなたに合っていない可能性が高いです。それらの変更を上司や人事部門に相談することで、「原因」を解決できる場合があります。
職場として「すぐの」「本格的な」対応が難しくても、それらができるまでの一時的な対応として、時短勤務・リモートワーク・勤務日減などが可能になることもあります。また、あなたの知らない「効果的だった前例対応」などを紹介されることもあるでしょう。次項③とも共通します。
次項③との違いは、「これまでと同じ部署・同じ仕事で、量だけ減らす(同じ部署内での担当業務を変える)」などが解決策になりうることです。
専門医による診断書も提示しながら相談すると、「担当業務(量)の不一致が原因である」と話が通じやすいため、希望も通りやすくなります。
方法③配置転換・転勤を相談する
職場の人間関係や通勤手段(通勤時間なども含む)が、適応障害の原因になっていることもあります。その場合は、配置転換・転勤などを相談することで、解決につながることがあります。
前項②との違いは、「これまでと同じ業務の内容・量で、環境や同僚・上司などが異なる支社で働く」などが解決策になりうることです。
こちらも、診断書があった方が話は通りやすいでしょう。「異動しただけで適応障害が治った」という人も少なくありません。
補足:職場がいわゆるブラック企業で相談できない場合
勤め先がいわゆる「ブラック企業」で、相談できそうにない場合は、次のような相談先があります。
- 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省の委託事業)
- 法テラス(国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」)
- 各市区町村役所が行う、法律やお悩みの相談会
いわゆる「退職代行サービス」もありますが、そちらは「退職するためのサービス」ですので、「退職するかどうかの検討(と療養)が必要な段階」で最初に相談するのはあまりオススメしません。
適応障害の人が退職する前に気をつけるべき確認事項4点
すでに退職の決心がついている場合でも、手続きを進める前に確認しておいた方がいいことがあります。基本となる4つのポイントを押さえておきましょう。
確認①かかりつけ医の意見

かかりつけ医に意見を聞きましょう。医師からも退職前に「休職を取ってみたらどうか」と提案されることがあるかもしれません。最終的に退職を判断するのはあなた自身ですが、判断材料のひとつとして、意見を尋ねておきたい相手です。
確認②産業医の意見
勤め先に産業医がいるなら、その意見を伺うという手段もあります。産業医は中立的な立場から話をするため、面談の結果が給与査定や昇進に響くこともありません。
労働者の健康管理に関して専門的な立場から助言や指導を行う医師のこと。産業医は労働安全衛生法に基づいて、常時50人以上の労働者を使用する事業所に1人以上、3,000人超の事業所では2人以上が配置されています。診察にあたって料金は発生しません。(参考:厚生労働省「産業医について」)
確認③経済的な状況

退職前には、ご自身の経済的な状況も確認しておきましょう。特に家族がいる場合は、家庭内で経済面のことを話し合っておいた方が、安心して退職できるはずです。
お勤め先と勤続年数によっては、退職金が支給されます。また、後述するように、適応障害の方が利用できる公的な支援もあります。
確認④退職のメリットと注意点(医師などにも相談する)
退職前には、退職のメリットと注意点について、改めて考えるようにしましょう。それぞれ以下のポイントが挙げられます。
- 休養に専念できる
- 合わない職場環境から離脱できる
- 療養後には、心機一転して自分に合った職場を探せる
- 職歴にブランクができる
- 現在の給与がなくなる
仕事・職場に関連して適応障害になると、慌てて「退職したい」と思うかもしれません。しかし、繰り返すとおり、病気のときに焦って重大な決断はしない方がいいですし、退職は後からでもできます。まずは「休職しての療養」をお勧めします。また、休職中に転職活動をすることもできます。
適応障害で退職した人にオススメの3つの考え方
この章では、適応障害で退職した人が、次の一歩を踏み出すための考え方を紹介します。
考え方①「環境が合わなかった」と割り切る

適応障害で退職すると、「自分はつらいことから逃げたのではないか」と考えて、落ち込む人もいます。しかし、合わない環境から去ることは、「逃げ」ではありませんし、「逃げ」だとしても問題ありません。
「自分の能力や人格に問題があった」と考えずに、「環境が合わなかった」「合わない環境はある」と割り切ることが大切です。実際、新しい環境でリスタートを切ったことで好転したという人はたくさんいます。安心してください。
考え方②自分に合った仕事・職場を探す
退職後に転職活動をするときは、「その仕事・職場が自分に合うかどうか」を念頭に置いて就職先を考えましょう。逆に言うと、再度の職場不適応を避けるためには、「給与や待遇がいいから」などの理由だけで就職しないことが大切です。
一般的には、以下のような職場環境だと、ストレスがかかりにくいです。
- 無理をするような仕事ではない
- 日課の決まっているような仕事
- 仕事量が多くない
- 人間関係などが複雑ではない(無理に職場に馴染まなくてよい)
上記を受けて、一般的には、以下のような仕事・働き方が、適応障害でも続けやすいと言われています。
事務職、バックオフィス職、管理業務、警備員、工場のライン担当
Webライター、Webデザイナー、歩合制の営業職
自分がどんなことにストレスを感じやすいかを考えながら、また後述するサポート団体などとも話しながら、あなたに合った仕事を探しましょう。
その他、適応障害と転職についての詳細は、下記コラムをご覧ください。
考え方③支援を受けて次のステップを目指す

「新しい職種や次のステップを目指そう」という考え方を持つと、退職を「いいきっかけだった」と受け止められるようになります。
次のステップを目指す上では、支援を受けることが効果的です。たとえば、後述する就労移行支援事業所では、仕事に役立つ専門的なスキルの講習を、原則無料で受けることができます。前職では経験できなかった業務を学ぶことで、働き方の幅を広げるチャンスになります。
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、うつ病や発達障害などの人のための就労移行支援事業所です。
- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月
新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。
適応障害で退職した人が受けられる6つの経済支援

適応障害で退職した人が受けられる経済支援は複数あります。ただし、「実際にあなたが受給できるかどうか」「どの程度の経済支援を受けられるか」は、個々の状況によって異なります。
「経済的支援はたくさんある」と安心材料にしていただいた上で、具体的な利用方法には各窓口などに相談しましょう。
経済支援①失業手当(雇用保険給付)
失業手当は、適応障害に限らず、失職した人(仕事を辞めた人)が、就職するまでの一定期間、受給できる給付金です。(参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」)
原則的には、以下の2点が給付の条件になります。
- 退職までの一定期間、雇用保険に加入していたこと
- 求職活動を行っていること(窓口相談や職業訓練も含む)
受給期間や金額は、個々人の状況によって異なります。
経済支援②傷病手当金
傷病手当金は、病気による休業中に、健康保険の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられている制度です。「病気やケガで勤め先を休んでいて、かつ給料の支払いがない」などの人が対象になります。受給額は、「それまでの給料」などによって変わります。(参考:全国健康保険協会「傷病手当金」、「傷病手当金について」)
- 全国健康保険協会
- 各健康保険組合
- 各共済組合
傷病手当金の詳細は、下記コラムをご覧ください(うつ病の方に向けた内容ですが、適応障害の方にもほぼ当てはまる内容です)。
経済支援③自立支援医療制度

自立支援医療制度とは、精神疾患で継続的な通院が必要な場合などに、医療費の自己負担額を軽減できる公費負担の医療制度です。(参考:東京都福祉保健局「自立支援医療(更生医療)」、東京都福祉保健局「心身障害者医療費助成制度(マル障)」)
通常3割の医療費自己負担を、原則1割まで軽減することができます(つまり、通院や薬の費用を通常の3分の1にすることができます)。
世帯の総所得額によって、自己負担上限額が定められていたり、対象外となったりする場合があります。また、具体的な内容・条件・名称は、自治体によって異なります。
- お住まいの市区町村の窓口
- (かかりつけの病院)
経済支援④障害年金
障害年金とは、病気やケガで生活や仕事に支障が出ているときに、年金加入者が受給できる年金です。
「年金」というと「高齢者が受給するもの」というイメージもありますが、障害年金は、現役世代の方も受給できます。また、働きながら受給することもできます。
ただし、あなたの病気・障害が「適応障害のみ」の場合は、障害年金の受給対象にはなりません。別途、障害年金の対象となる病気・障害がある必要があります。
- 市区町村に設置された、障害年金相談センター
- NPO法人障害年金支援相談ネットワーク
障害年金の詳細は、下記コラムをご覧ください。
経済支援⑤障害者手帳
適応障害の症状によっては、障害者手帳を取得できます。障害者手帳を取得すると、次のような支払いが減免されることがあります。
- 所得税・住民税
- 医療費
- 各種公共料金(公共交通機関の運賃、上下水道料金、NHK放送受信料、携帯電話料金、公共施設の入館料等)
また、失業保険の給付期間が延びたり、(再)就職や転職の際に障害者枠の利用ができたり、というメリットもあります。
障害者手帳によるメリットの詳細は、下記コラムをご覧ください。
経済支援⑥生活保護

生活保護とは、病気やケガなどで就労できない人や、働いていても極端に収入が少ない人に現金を支給し、最低限の生活ができるように支援する制度です。(参考:厚生労働省「生活保護制度」)
食費・被服費・光熱費・家賃・医療費など、生活に必要な各種費用を受給できます。
- お住まいの市区町村の福祉事務所
- 市区町村役所の生活保護担当課
「適応障害だと生活保護を受給できるの?」とお聞きされることがあるので紹介しましたが、一般的には、「適応障害だから」という理由「だけ」での受給は難しいようです。状況によっては受給できるかもしれませんが、他の支援を(先に)検討・申請する方がより確実だと思います。
「適応障害と生活保護」の詳細は、下記コラムをご覧ください。
補足:経済支援⑦その他
「労災保険」「生活困窮者自立支援制度」という支援制度もありますが、これらも、生活保護と同じく「適応障害だから」という理由「だけ」での受給は、一般的には難しいようです。状況によっては受給できるかもしれませんが、他の支援を(先に)検討する方がより確実だと思います。
適応障害で退職した人が再就職するためには、就労移行支援がオススメ
適応障害で退職した人に特にオススメしたいサービスが、就労移行支援です。適応障害などを経験した方々のために、一般企業での再就職や仕事で独立をサポートしています。
※本格的な利用は、基本的には「退職した後の方(離職状態にある方)」が可能ですが、相談は退職前から可能です。
- 就労を希望する65歳未満の障害者の方が利用可能
- 利用料金は所得に応じて上限あり
- 利用可能期間は、原則として、最長24か月
※以上を踏まえた上で、お住まいの各地区町村が、個別に利用の可否を判断します。利用にあたって、障害者手帳の所持は必須ではありません。
- ビジネススキルの習得:PCスキル、コミュニケーション方法など
- 専門スキルの学習:会計、英語、プログラミング、マーケティングなど
- 体調管理やメンタル面の相談:個別支援計画にあわせた面談
- 就職活動のサポート:雇用枠の検討、面接対策など
- インターン先や就職先の紹介:あなたにあった職場探しの手伝い
また、就労移行支援事業所の種類によっては、就職後に「職場定着支援」も受けられます。職場定着支援では、就職後の労働環境や業務内容について、職場とあなたの間に入って調整を行います。
就労移行支援の詳細は、下記コラムをご覧ください。
適応障害で退職した人を支えるサポート団体7選:就職・生活・メンタル面など

適応障害の人を支えるサポート団体のなかには、下記のような相談先があります。
気になるところがあれば、話をしてみましょう。ここで言う「障害者」には、「適応障害の方」も含みます。
各相談先は機能が異なるため、「紹介する順番にオススメ」というものではありません。それぞれ、「自分が受けたいサービスを行っているか」を確認して、問い合わせてみましょう(または、市区町村役所の障害福祉担当課に、「自分に向いている相談先」を聞く方法もあります)。
サポート団体①精神保健福祉センター
こころの健康についての相談、精神科医療についての相談、社会復帰についての相談など精神保健福祉全般にわたる相談を行っています。(全国の一覧はこちら)
サポート団体②ハローワーク
ハローワークでは、適応障害などの病気・障害について専門的な知識を持つ担当者が、仕事に関する情報提供や、就職に関する相談など、きめ細かい支援体制を整えています。(全国の一覧はこちら)
サポート団体③基幹相談支援センター
「地域の相談支援の拠点」として、適応障害経験者などの方々のための総合的な相談を行ったり、より適切なサポート団体との連携を行ったりします。
サポート団体④自助会・互助会・ピアサポート
「同じ悩みを抱えている人たち」が互いに支え合い、情報交換などを行う団体の総称です。お悩みを打ち明けたり、対処方法などを共有できたりします。具体的な実施内容や目的は、会によって様々です。
サポート団体⑤地域障害者職業センター
ハローワークが行う職業紹介等の業務と連携して、適応障害経験者などの方々の職業に関する能力の判定、職業相談、職業指導および就職後のアフターケアなどを行っています。(全国の一覧はこちら)
サポート団体⑥障害者就業・生活支援センター
適応障害経験者などの方々の職業生活における自立を図るため、就業面及び生活面における一体的な支援を行っています。(全国の一覧はこちら)
サポート団体⑦発達障害者支援センター
※適応障害の背景に、(本人も気付いていない)発達障害の特性が関連することもあります。
発達障害のある方やその家族が、日常生活から仕事に関することなど、様々なことを相談できます。発達障害と診断されていなくても相談可能です。(全国の一覧はこちら)
改めて、適応障害とは
改めて、適応障害の概要をお伝えします。既にご存知かもしれませんが、これまでに紹介した内容の理解も深まると思いますので、ぜひご覧ください。
適応障害とは、仕事や職場の人間関係などから生じるストレスが原因で、社会生活が著しく困難になっている状態のことです。情緒面・行動面・身体面に、以下のような症状があらわれます。
憂鬱な気分(抑うつ気分)、不安感が高まる、無気力、集中力の低下、わけもなく悲しくなる、イライラする、細かいことがいつまでも気になる、記憶力の低下
衝動的な言動の増加、たばこや飲酒の量の増加、喧嘩や自傷行為、強い貧乏ゆすり等
動悸、頭痛、冷や汗、息苦しさ、過呼吸、手先や唇の震え、倦怠感、耳詰まり、耳鳴り
※ただし身体症状は、適応障害とは別の内臓疾患に起因する場合もあります。
適応障害とうつ病の違い
うつ病と適応障害の症状は非常に似ています(適応障害はうつ病に移行する可能性もあります)。しかし、適応障害とうつ病には、「ストレス要因の有無と回復にかかる時間」に違いがあります。(参考:アメリカ精神医学会『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、松﨑博光『新版 マジメすぎて、苦しい人たち:私も、適応障害かもしれない…』)
- 適応障害:明確な原因(ストレス)がある。原因から距離を置くと症状は消える
- うつ病:明確な原因が不明なこともある。また、原因がなくなってもすぐには回復しない
適応障害は、退職すれば治りやすくなることもある
以上から、適応障害の原因に仕事・職場が関係する場合、「適応障害は退職すれば治る」という話は、ある程度は真実と言えるかもしれません。
ただしもちろん、「退職しなければ治らない」という意味ではありません。
これまで述べてきたように、退職せずに原因から離れる方法としては、まずは休養がありますし、その後の異動や業務量調整なども考えられます。「今すぐに退職しなければ」などと思いつめないようにしましょう。
まとめ:適応障害の人が退職前にできることはたくさんあります!

適応障害になると、体調不良も相まって、すぐに退職を決断しそうになるかもしれません。
しかし、退職をする前にも、休職を取ったり、人事部門に業務調整を申し出たりと、できることはたくさんあります。
退職を焦る前に、まずは専門医に相談した上で、自分ができることを考えてみましょう。
もし退職をすることになったとしても、経済支援や、再就職に向けた支援は多々ありますので、ご安心ください。
この記事が、適応障害で退職を検討している人の助けになれば幸いです。
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
執筆寺田淳平
てらだ・じゅんぺい。
高校2年の春から半年ほど不登校を経験。保健室登校をしながら卒業し、慶應義塾大学に入学。同大学卒業後の就職先(3,500人規模)で人事業務に従事する中、うつ病を発症し約10か月休職。寛解・職場復帰後、勤務を2年継続したのち現職のフリーライターに。
2019年に一般財団法人職業技能振興会の認定資格「企業中間管理職ケアストレスカウンセラー」を取得。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→