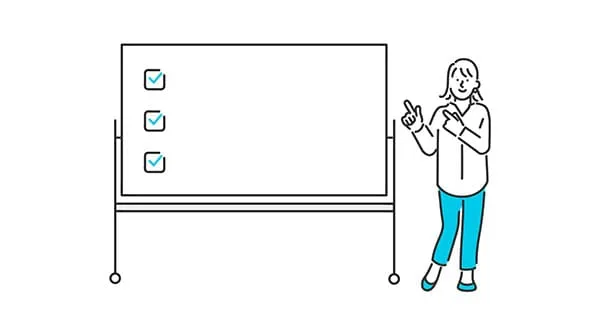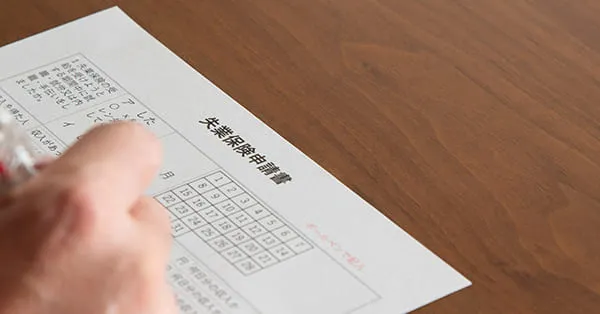自律神経失調症のある人が仕事を続けるための対策 仕事探しのコツを解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
自律神経失調症のあるあなたは、「仕事を続けるのがつらい」と悩んではいませんか?
自律神経失調症は周りの人になかなか気付いてもらえないため、仕事の場で「甘え」とかんちがいされることも少なくありません。
また、自律神経失調症は風邪などと違ってすぐに完治するものではないため、職場の人の理解を得るのが難しいと思います。
筆者も10年以上、当事者として自律神経失調症と向き合ってきました。
このコラムでは、自律神経失調症のある人が仕事を続けるための対策や仕事探しのコツ、仕事以外の場面でうまく付き合う方法を解説します。
あわせて、自律神経失調症のある人が利用できる支援制度と支援機関を紹介します。
自律神経失調症と仕事の両立でお困りの人はぜひ読んでみてください。
目次
自律神経失調症のある人の仕事上の困難3選
この章では、実際に自律神経失調症のある筆者の視点も交えて、自律神経失調症のある人が抱える、仕事上の困難を解説します。
困難①調子の波が大きい

1つ目は「調子の波が大きい」です。
自律神経失調症のある人は、交感神経と副交感神経のバランスが不安定です。したがって、ちょっとしたストレスや疲労が原因で大きく調子を崩すケースが多いです。
筆者の場合は、平日の仕事で疲れ切ってしまい、反動で休日は寝っぱなしになることで、生活リズムが乱れました。
その結果、月曜日になっても心身がスッキリせず、仕事がはかどらないということが多々ありました。
調子が出ても、無理をするとすぐにダウンするため、「調子の波が大きい」という悩みを持つ人も多いでしょう。
困難②疲れやすい
2つ目は「疲れやすい」です。
自律神経失調症の場合、気持ちの上では休みたいのに、交感神経優位による身体の緊張状態が続くため、心身ともにリラックスできません。
身体は疲れているのに、目が冴えて眠れない日が続くなど、疲労回復に困難が生じやすいのが、自律神経失調症のある人の特徴でもあります。
反対に、急に副交感神経が優位になり、身体がリラックスモードに切り替わって、仕事中に眠くなったりだるくなったりすることも多いです。
その結果、業務がはかどらずにスケジュールが圧迫されていくこともあります。
このような「自分ではどうにもならない疲れやすさ」も自律神経失調症のある人の悩みでしょう。
困難③周りに理解してもらえない

3つ目は「周りに理解してもらえない」です。
自律神経失調症は基本的に「正式な病名」ではない上に、その症状は大なり小なり自律神経失調症のない人にも見られます。
そのため、同僚や家族に症状を訴えても「休めばすぐに治るのではないか」と、理解してもらいがたく、なおかつ悩みを軽んじられやすいのです。
筆者が勤めていた職場でも、「それくらいの不調は誰にでもあるから気にしすぎではないか」という疑問を投げかけてくる人がいました。
周囲からの理解を得られないことで、症状があっても「自分が神経質なだけなのではないか」と疑い、余計なストレスを抱えることになります。
このように、自律神経失調症のある人の中には、仕事の場で「周りに理解してもらえない」という困難を抱えている人も多いでしょう。
自律神経失調症のある人が仕事を続けるための対策7点
この章では、自律神経失調症のある人が仕事を続けるための対策を解説します。(参考:原田賢『忙しいビジネスパーソンのための自律神経整え方BOOK』)
前提:まずは医師の判断に従うこと

前提として大切なのは、まずは医師の判断に従うことです。
医療機関を受診していない段階で、自己判断で「自律神経失調症ではないか」と考えている人は、ひとまず医療機関で医師の診断を受けましょう。かかるべき科については、こちらで解説しています。
その上で、例えば寝付けないという人は、処方されている睡眠薬をきちんと服用して、生活リズムが乱れないように心掛けましょう。
自己判断で薬の服用を中止することは絶対にやめてください。
対策①周囲の人に理解を求める
1つ目は、「周囲の人に理解を求める」です。
仕事は一人では成り立たないことが多いため、周囲の人の理解が必要になります。
特に、自律神経失調症のある人は一日のうちであるタイミングを境に、「今日はもう仕事ができない」と、疲労がピークに達することがよくあります。
そのようなときに、周りの人の理解があるだけで休みが取りやすくなるなど、精神的に余裕が生まれます。
自律神経失調症のある人は、できるだけ周囲の人に理解を求めるようにしましょう。
対策②産業医に相談する

2点目は、「産業医に相談する」です。
特に、自律神経失調症について仕事場で理解を得られずに困っている人には、産業医面談が有効です。
産業医とは、労働者の健康管理について指導やアドバイスを行う医師のことです。(参考:厚生労働省「産業医について」)
現在では、労働安全衛生法に基づき常時50人以上の労働者が在籍する事業所に1人以上、3000人超の事業所では2人以上の産業医の配置が義務付けられています。
以上の条件を満たしていれば、あなたのお勤め先にも産業医がいるはずです。
「産業医面談の内容次第では、人事査定に影響があるのではないか」と心配されるかもしれませんが、産業医は中立的な立場で診断を行います。ご安心ください。
もし、お勤め先が診断結果を求めても、個人情報保護の観点から共有してよいかを原則ご本人に確認することになります。
その上で、必要であれば、自律神経失調症の症状などについて、上司に説明を行ってもらったり、業務内容について助言をしてもらうことができます。
面談には、料金なども発生しません。仕事の悩みを産業医に打ち明けてみるとよいでしょう。
対策③できるだけ残業しない
3点目は、「できるだけ残業しない」です。
遅くまで残業をすると、ストレスが蓄積するだけでなく、生活習慣の乱れにもつながります。
結果として、自律神経失調症の悪化を招きかねません。
自律神経失調症の症状を軽減させて、長く勤め続けるためにも、できるだけ残業は避けるようにしましょう。
対策④定期的に休憩をはさむ

4点目は、「定期的に休憩をはさむ」です。
自律神経失調症のある人は、疲れやすいだけでなく、神経のバランスを崩しているために回復に時間がかかりやすい傾向にあります。
そのため、体力や気力が尽きる前に、小まめに休憩を取ることが大切です。
職場によっては、仕事中に休憩をはさむのは勇気がいるかもしれません。
そういった場合はこの章の冒頭で述べたように、周囲の理解を得ることからはじめてみてください。
また、一日のうちの休憩だけでなく、「休暇」を定期的に取得することも大切です。
忙しい時期には連勤になりがちですが、少しでも疲れを感じたら早い段階で休暇を入れるようにしましょう。
対策⑤半日休をうまく活用する
5点目は、「半日休をうまく活用する」です。
自律神経失調症のある人は、時期によって「半日であれば仕事ができるけれど、フルタイムだと厳しい」ということがあるかと思います。
このような場合に全日休を取ると、仕事に穴が空くだけでなく、翌日の出勤時に精神的なハードルが上がるという面があります。
もちろん、体調次第では全日休を取ることが望ましい場合もあります。
ですが、半日の勤務の方がトータルで見たときにストレスが少なく済むのであれば、半休をうまく活用して、あなたが働きやすい状況を作れないかを考えてみるとよいでしょう。
対策⑥リラックス法を取りいれる

6点目は、「リラックス法を取りいれる」です。
具体的なリラックス法には、以下のようなものがあります。
- 深呼吸をする
- ストレッチ、ヨガをする
- 職場の近くを散歩する
- マインドフルネスを実践する
個人的には、深呼吸のメソッドなど呼吸法を身につけることが特にオススメです。
動悸を静められるだけでなく落ちついた気持ちで仕事ができるため、実践するのとしないのとではその日一日の疲労度が大きく変わってきます。
書店であなたが実践しやすそうな実用書を探してみてください。
リラックスに向いているとされる、ラベンダーの精油をティッシュに数滴たらし、深呼吸するのもオススメです。
また、ヨガやストレッチも、ものによっては仕事の合間に実践することができます。
自律神経に焦点を絞った呼吸法や自律神経に効くヨガ・ストレッチについては、以下の書籍がオススメです。興味があれば手に取ってみるのもよいでしょう。
宮浦清・著、有田秀穂・監修『1日1分 自律神経を整える呼吸CDブック』
根来秀行『ハーバード&ソルボンヌ大学 根来教授の 超呼吸法』
崎田ミナ・著、福永伴子・監修『自律神経どこでもリセット! も~っと ずぼらヨガ』
対策⑦勤務時間を変更する
最後の対策は、「勤務時間を変更する」です。
お勤め先にもよりますが、大抵の職場では、短時間勤務制度など、何らかの事情がある人向けに、勤務時間を変更する制度があるかと思います。
自律神経失調症のある人は、その時々に、調子の悪い時期とそうでない時期があるかと思いますので、不調が続いているときは無理をせずに、勤務時間を変更するとよいでしょう。
自律神経失調症のある人の仕事探しのコツ3選
この章では、自律神経失調症のある人に向けて、仕事探しのコツを紹介します。
前提:周囲を頼る姿勢を持つこと

大切なのは、ひとりで抱え込まずに周囲を頼る姿勢を持つことです。
ここで言う「周囲」とは、医師だけでなくご家族や支援者も含みます。
自律神経失調症になると、周りの理解を得るのが難しくなるため、「誰も分かってくれない」と殻にこもりたくなることもあるかと思います。
しかし、周囲の人に悩みを話すこと自体が、ストレスの解消につながります。
また、あなたの気づかなかった視点や打開策を提示してもらえることもあります。
とくに仕事探しのときには、情報のやり取りが重要になりますので、ぜひ周囲を頼るようにしてください。
コツ①勤務形態が柔軟な仕事を探す
1点目は、「勤務形態が柔軟な仕事を探す」です。
自律神経失調症の場合、こちらで解説したように調子の波が大きいなど、ちょっとしたトラブルやストレスで調子を崩すことが多々あります。
そうしたときに、勤務時間や勤務形態が厳格な仕事に就いていると、安定して働くことができません。
職場の同僚に負担を掛け、本人としても職場に居づらい状況になりやすいです。
そのため、自律神経失調症があって仕事探しをされているなら、フレックス制や裁量労働制を採用しているような、勤務形態が柔軟な仕事を選ぶようにしましょう。
「IT系やWEB系の企業、エンジニア職などではフレックス制を採用しているところが多いです。
また、マイペースに仕事ができるフリーランスなども自律神経失調症のある人にとってはストレス負荷が少なく済むためオススメです。
ただし、勤務形態が柔軟だからといって、夜更かしをしたり生活リズムが乱れたりすると、自律神経失調症が悪化します。その点には注意してください。
コツ②福利厚生制度の整った職場を探す

2点目は、「福利厚生制度の整った職場を探す」です。
自律神経失調症の場合、朝の起床に時間がかかったり、通勤中の電車の中で気分が悪くなることがあります。
そのようなときに、時差出勤に切り替えたり短時間勤務の申請ができると、気持ちにゆとりを持って仕事ができます。
また、「長期欠勤の取り扱い」や「休職制度が整っているかどうか」を確認することも大切です。
自律神経失調症は、うつ病などに比べて復職までにかかる時間が比較的短くすむため、短いスパンでまとまった休みを取る人もいます。
そのたびに手続きが煩雑だと、自律神経失調症の回復も滞ります。時短勤務や休職制度といった「福利厚生の整った職場を探す」ことが仕事を長続きさせるコツです。
コツ③支援機関を利用する
最後のコツは「支援機関を利用する」です。
支援機関の中には、うつ病や適応障害などの障害によって就労が難しい人向けに、福祉サービスを実施しているところがあります。
例えば、障害者総合支援法にもとづいて設置されている「就労移行支援事業所」などは、オススメです。
就労移行支援事業所では、体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができます。
就労移行支援事業所については、こちらで解説します。
就労移行支援については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、自律神経失調症のある人のための就労移行支援事業所です。
- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月
新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。
仕事以外の場面で自律神経失調症とうまく付き合う方法3選
自律神経失調症は、仕事による過労以外にも、生活習慣や睡眠の乱れが原因で、症状が出現したり、悪化したりすることがあります。
この章では、自律神経失調症のある人が、仕事以外の場面で自身の症状とうまく付き合う方法を紹介します。
方法①生活習慣を見直す

1つ目の方法は、「生活習慣を見直す」ことです。
仕事による疲れ以外に、交感神経が高ぶるような原因がないかをよく考えてみましょう。
例えば、以下のようなことに思い当たることはありませんか?
- 脳の報酬系が作用しやすいSNSを見るのをやめられない
- 深夜まで起きてネットサーフィンやゲームをしている
また、副交感神経のスイッチを入れる方法には、入浴や瞑想、ストレッチやマッサージがあります。
お風呂に浸かっていない方は、38℃程度のぬるめのお風呂に入ってみるのもオススメです。
お風呂では、スマートフォンを物理的に遠ざけられるので、あえて何もしない時間を入浴で作ってみてはいかがでしょうか?
方法②睡眠の質を向上させる
睡眠不足が原因で、自律神経失調症を発症したり、悪化している場合は、睡眠をしっかり摂ることが大切です。
処方される睡眠導入薬や睡眠薬のほか、起床から1時間以内に日光を浴びたり、5分程度の散歩も寝つきの良さを高めます。
寝る前にスマートフォンをオフにして、光や音の刺激を遠ざけるのもオススメです。
方法③食事・運動に気を付ける

自律神経失調症を直接改善するわけではありませんが、タンパク質の豊富な食事を摂ることで、寝つきがよくなったり、睡眠の質が向上したりします。
必須アミノ酸のトリプトファンは、別名「幸せホルモン」のセロトニンに変化し、セロトニンは「睡眠ホルモン」のメラトニンに変化するからです。
「朝は食欲がない」という方は、プロテインシェイクを飲んだり、トリプトファンが豊富なバナナを朝食に選びましょう。
朝食を摂ると身体のリズムが整うため、抜いてはいけません。
また、ウォーキングは交感神経を鎮めて、副交感神経を優位にさせます。
緊張が続いたときは、会社のまわりを散歩したり、1駅分歩いて出社するのもオススメです。(参考:ジョンJ.レイティほか『脳を鍛えるには運動しかない! 最新科学でわかった脳細胞の増やし方』)
自律神経失調症のある人が利用できる支援制度6選
自律神経失調症があると、会社で働き続けることに困難を感じたり、収入の不安から、ますます症状が悪化することもあるでしょう。
しかし、自律神経失調症の方には、各種支援制度があるので、会社で働けなくなった場合は、これらの支援制度を利用して、治療に専念できます。
この章では、自律神経失調症のある人が利用できる支援制度を紹介します。
支援制度①傷病手当金

傷病手当金とは、自律神経失調症を含む何らかの病気やケガ、障害のために仕事を休む場合に「健康保険」の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた支援制度のことです。国民健康保険の加入者は対象外です。(参考:全国健康保険協会「傷病手当金」、全国健康保険協会「傷病手当金について」)
傷病手当金は、退職前の在職中に受給するお金です。ただし、一定の条件を満たせば、退職後も継続して受給できます。
傷病手当金の受給対象は、病気やケガ、障害によって就労不能であり、十分な給与が支給されない人です。そのため、医師の診断書が必要です。
傷病手当金の窓口は、全国健康保険協会や各健康保険組合、各共済組合です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の例では、以下のすべての条件を満たしている必要があります。
- 業務外の病気やケガ、障害で療養中であること
- 療養のための労務不能であること
- 4日以上仕事を休んでいること
- 給与の支払いがないこと
各条件には、さらに「給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給される」などの補足が付いています。
そのため、対象となる協会・組合に問い合わせたりウェブサイトを参照したりして、しっかりと条件を確認することが大切です。
また、傷病手当金の受け取りのためには、会社の記載する給与額や、医師が記載する、自律神経失調症などの病気であることを証明する書類などの提出が必要になります。
また、傷病手当金の受け取りのためには、基本的に自律神経失調症などの病気であることを証明する診断書の提出が必要になります。
具体的な支給額は、対象者の標準報酬月額などによって異なります。
さらに詳しい支給額を知りたいという方は、まずは職場の人事部に一定期間の給与額などを確認した上で、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。
気になる方は、ご自身の加入している健康保険に問い合わせてみましょう。
傷病手当金については、以下のコラムで解説しています。うつ病のある人に向けた内容ではありますが、参考になるはずです。ぜひご覧ください。
支援制度②失業保険(失業手当、雇用保険給付)
失業保険(失業手当、雇用保険給付)とは、失職した人が就職するまでの一定期間に給付金を支給する支援制度のことです。
原則、以下の2点が条件です。
- 退職までの一定期間、雇用保険に加入していたこと
- 求職活動を行っていること
ここで言う求職活動とは、企業への面接訪問などに限らず、窓口相談や職業訓練も含まれています。それらの活動ができる場合、「就職活動をして労働する」ことができない人でも条件を満たすことは充分可能です。
具体的な受給期間(90日~360日)や金額(在職中の給与の約50~80%)は、その人の状況によって異なります。また、うつ病などの病気によって求職活動条件を満たせない場合には、受給期間を延長することも可能です。
また、これまで述べてきた失業保険は「基本手当」と呼ばれるものになります。
病気やケガ、障害によって15日間以上、引き続いて求職活動ができない場合は、「傷病手当」という別の給付金を受給することができます。
なお、雇用保険上の傷病手当は、こちらで解説した傷病手当金とは異なることに加えて、傷病手当と傷病手当金、失業手当を同時に受給できない点には注意してください。また、公務員は対象ではないため、注意してください。
申請は、お住まい自治体に設置されているハローワークで行なえます。(参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」)
気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。
失業保険については、以下のコラムで解説しています。うつ病のある人に向けた内容ではありますが、参考になるはずです。ぜひご覧ください。
支援制度③自立支援医療制度

自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療に関する医療費の自己負担額を軽減する公費負担の支援制度のことです。うつ病もその支援の対象です。
(参考:厚生労働省「自立支援医療について」、厚生労働省「自立支援医療制度の概要」、東京都福祉保健局「自立支援医療(更生医療)」)
通常、医療保険による医療費の自己負担額は3割です。自立支援医療制度を利用すれば、原則1割まで軽減することができます。この制度は、指定の医療機関・薬局のみで利用可能です。
世帯の総所得額によっては利用の対象外となる、場合があります。
さらに、自己負担額には、所得に応じて上限が設定されています。1割負担であっても、月額の上限以上となる金額は、原則として負担を免除されます。ただし、世帯の総所得額によっては、自己負担額が変動したり、対象外になったりする場合があります。
また、費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない場合や所得の程度に応じて、さらに軽減措置が行われます。
自立支援医療は、下記の3種類に分けられます。
- 精神通院医療:精神疾患の治療など
- 更生医療:身体障害に関わる治療など
- 育成医療:身体障害がある子どもに関わる治療など
特定の精神疾患がある人以外に、身体障害者手帳を持つ人なども対象です。
具体的な支援内容や条件、名称は、自治体によって異なります。
気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。
支援制度④生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援制度とは、仕事や住まいの確保に困窮している人に対して、各々の生活状況に応じた支援を提供する支援制度のことです。(参考:厚生労働省「制度の紹介」、東京都福祉保健局「生活困窮者自立支援制度について」)
生活困窮者自立支援制度は、こちらで解説する生活保護の受給に至る前に、対象の人の自立を促進することを目的に制定されました。
経済や就労、住居確保といった幅広い分野について相談することができ、要件を満たす人には家賃相当額を支給するなど経済的な支援も行っています。
また、自立相談支援機関が作成した支援プランに沿って、一定期間、支援員が生活を立て直すためのサポートをしている場合もあります。
生活困窮者自立支援制度の支援内容は多岐に渡り、その内容は自治体によっても異なります。
気になる方は、お住まいの自治体の生活保護を担当する部署・窓口に相談してみてください。
支援制度⑤生活保護

生活保護とは、生活に困窮している人や病気やケガ、障害などで就労できない人に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活の保障と自立の助長を目的とした支援制度のことです。(参考:厚生労働省「生活保護制度」)
生活に必要な最低限度のお金を持つことが困難な人がお金を受給できる制度とも言えます。
生活保護で受給できるお金には生活扶助(食費・被服費・光熱費など)や住宅扶助(アパートなどの家賃)、医療扶助(医療サービスの費用など)などがあります。
- 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費など)
- アパートなどの家賃
- 義務教育を受けるために必要な学用品費
- 医療サービスの費用
- 出産費用
- 就労に必要な技能の修得などにかかる費用
- 葬祭費用
また、受給金以外にも、国民年金保険料や住民税、NHK放送受信料などの税金・公共料金の支払いが減免されることがあります。
申請は、お住まいの自治体を所管する福祉事務所で行なえますが、まずは、お住まいの自治体の生活保護を担当する部署・窓口に相談してみてください。
ただし、生活保護は「最後のセーフティネット」とも呼ばれるように、本当に支援が必要な人だけを対象とする支援です。一般的に審査が厳しく、生活保護以外の支援を提案されたり、申請が却下されたりする可能性があるということは、心に留めておいてください。
生活保護については、以下のコラムで解説しています。うつ病のある人に向けた内容ではありますが、参考になるはずです。ぜひご覧ください。
支援制度⑥生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度とは、所得の低い人や障害のある人などの生活を経済的に支えつつ、その在宅福祉や社会参加の促進を図ることを目的に貸付を行う支援制度のことです。銀行などと比べて、低い金利でお金を借りることができます。
(参考:全国社会福祉協議会「生活福祉資金」、厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧」、政府広報オンライン「生活にお困りで一時的に資金が必要な方へ「生活福祉資金貸付制度」があります。| 暮らしに役立つ情報」)
対象となるのは、「低所得者世帯」「障害者世帯」「高齢者世帯」です。障害のある人の場合は、障害者手帳などの交付が前提となります。
生活福祉資金貸付制度は大きく分けて下記に分類されます。
- 生活福祉資金貸付制度の種類
- 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
- 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
- 教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
- 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
この制度は、あくまで「貸付」です。返済の義務があるという点は注意しましょう。
気になる方は、お住まいの自治体の生活保護を担当する部署・窓口に相談してみてください。
自律神経失調症のある人が利用できる支援機関
自律神経失調症のある人は、求職時に自分の症状に合った、無理のない職場をご希望ではないでしょうか?
しかし、転職活動は気力・体力ともに消耗が激しいため、ひとりで転職活動が難しいという人もいるでしょう。
この章では、自律神経失調症のある人が利用できる支援機関を紹介します。
支援機関①就労移行支援事業所

就労移行支援とは、一般企業などへの就職を目指す、病気や障害のある方向けに、「障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」に基づいて行われる福祉サービスのことです。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
実際のサービスは、国の基準を満たした様々な民間の「就労移行支援事業所」が行います。
就労移行支援事業所では、体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができます。
さらには、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労移行支援事業所は各地にあります。私たち、キズキビジネスカレッジ(KBC)もその一つです。それぞれ特徴が異なるため、気になるところがあれば問い合わせてみてください。
就労移行支援事業所については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、自律神経失調症のある人のための就労移行支援事業所です。
- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月
新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。
支援機関②地域障害者職業センター
地域障害者職業センターとは、病気や障害のある人に対して、職業評価や職業指導、職業準備訓練、職場適応援助などの専門的な職業リハビリテーションを提供する支援機関のことです。
(参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センターによる支援」、厚生労働省「地域障害者職業センターの概要」)
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しており、障害者雇用促進法に基づいて、全国47都道府県に設置されています。
ハローワークや医療・福祉機関と連携しているため、仕事に関する相談や訓練、復職するためのサポートを行っています。
病気や障害に悩む当事者だけでなく、障害のある人を雇用する事業所に対して、雇用管理に関する相談・援助も行っています。
仕事を両立したい人や就労状況について相談したい人におすすめです。
支援機関③障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターとは、雇用や保健、福祉、教育に関する関係機関と連携し、障害のある人の雇用の促進・安定を目的とした一体的な支援を行っている支援機関のことです。
(参考:厚生労働省「障害者雇用促進法制の整備について」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」)
障害のある人の就職活動の支援や求人の紹介、職場定着のためのサポートなどを行います。
就労面だけでなく、金銭管理などの経済面や生活面のことまで、日常および地域生活に関する支援も行っています。
生活習慣や金銭管理、健康管理などについても幅広く相談できるため、生活面のサポートも受けたい人におすすめです。
2023年4月1日時点で、全国に337箇所設置されています。
支援機関④ハローワーク(公共職業安定所)
ハローワーク(公共職業安定所)とは、仕事を探している人に対して、就労に関連するサポートを行っている支援機関のことです。
(参考:東京労働局「東京ハローワーク」、厚生労働省「こころの健康サポートガイド」、厚生労働省「ハローワークにおける障害者の就労支援」)
主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示などを行っており、具体的な支援内容は事業所によって異なりますが、一般的には以下のような幅広いサポートを行います。
- 仕事で活かせる知識・技能の習得
- 仕事で活かせる知識・技能の習得
- 仕事や私生活で活かせるメンタル面のサポート/li>
- 「どのような仕事や働き方が向いているのか」のアドバイス
- 転職先候補の業務や雰囲気を体験できる「職場体験実習(インターン)」の紹介
- 履歴書・経歴書・エントリーシートの作成支援
- 面接対策
- 転職後の職場定着支援
ハローワークでは、自律神経失調症に限らず、病気や障害のある人に向けた支援を行っています。
ハローワークで求職登録を行うと、病気・障害の特性や希望職種に応じた職業相談を受けられます。
自律神経失調症があることや自律神経失調症のある人向けの求人を探していることを伝えると、自律神経失調症のある人に向いていると思われる求人情報を紹介してもらえます。
ほかにも、「自律神経失調症がある状態でどのように就職活動をすればよいのか?」「面接や履歴書には自律神経失調症の経験をどのように記載すればよいのか?」など、自律神経失調症のある人の就職活動や履歴書の書き方、面接での自律神経失調症の伝え方など、細かい疑問も解決できます。
また、ハローワークには、住まいや生活に関する総合相談を行う窓口もあります。経済面や生活面などについても幅広く相談できるため、心配がある場合は相談してみましょう。
支援機関⑤地域若者サポートステーション(サポステ)

地域若者サポートステーションとは、働くことに悩みを抱えている15〜49歳までの就学中でない人のサポートを目的とした支援機関のことです。「サポステ」とも呼ばれています。(参考:厚生労働省「地域若者サポートステーション」)
厚生労働省委託の支援機関であり、病気・障害の有無を問わず、就業中ではない人の就職から職場定着までを全面的にバックアップします。
地域若者サポートステーションでは、一般的に以下のような支援を行っています。
- コミュニケーション講座
- ジョブトレ(就業体験)
- 就活セミナー(面接・履歴書指導など)
- 集中訓練プログラム
- パソコン講座・WORK FIT・アウトリーチ支援
支援機関⑥転職エージェント
転職エージェントとは、転職を希望する人をサポートする人材紹介サービスのことです。
現代の仕事探しにおいて、転職エージェントの利用は一般的な方法です。民間の転職エージェントも、うつ病のある人が利用できる支援機関と言えます。
近年では、病気や障害のある人に特化した転職支援を行う転職エージェントも増加しています。
ご自身に合いそうな転職エージェントを並行的に利用してみましょう。
一般の転職エージェントの例自律神経失調症で仕事に悩む人のQ&A3選
この章では、自律神経失調症で仕事に悩む人からよく聞かれる質問とその回答を紹介します。
仕事だけでなく「診療科がわからない」といった基本的な質問にも答えています。自律神経失調症のある人は一緒に確認していきましょう。
Q1.自律神経失調症は何科にかかるべき?

自律神経失調症の場合、症状が多岐に渡るため、最初にかかるべき科が明確にあるわけではありません。
基本的には、あなたが特に不調を感じる部位にあわせて、病院を受診してみましょう。
たとえば、動悸や息苦しさが強いのであれば「循環器内科」を、腹痛や胸やけが続くのであれば「消化器内科」を受診するようにしましょう。
どこが一番不調なのかが明確でない場合は、ひとまず「総合内科」にかかることをオススメします。
また、身体症状よりもメンタル面に不調を感じるようであれば、迷わずに「心療内科」へ行ってください。
私の場合は最初に胃痛が数ヶ月続いていたため、消化器内科へ行って検査を受けました。
しかし、特に原因が見つからなかったため、医師に仕事の状況や生活について話したところ、ストレスの影響が大きいかもしれないと言われ、心療内科を勧められるとともに、自律神経失調症の可能性があると診断されました。
このように、「まずはどこかの診療科にかかって、その後にセカンドオピニオンを受ける形で別の科へかかり、治療を開始する」というのが一般的です。
Q2.自律神経失調症で休職はできるのか?
結論から申し上げますと、「自律神経失調症のみ」で休職できるかどうかは医師の判断によります。
また、休職をする際に多くの場合必要とされる「医師による診断書」という観点からは、自律神経失調症のみで休職をすることは難しいかもしれません。
お勤め先の休職制度にもよりますが、基本的に休職をするときには、「医師による診断書」が必要です。
しかし、こちらで解説しているとおり、自律神経失調症は医学的に正式な疾患名ではありません。
それゆえ原則的には、診断書に「自律神経失調症」とだけ記載されることはないかと思います。
自律神経失調症の症状を訴えて心療内科などを受診した場合、自律神経の失調の原因が「適応障害」や「うつ病」にあると診断されることが少なくありません。
私自身、休職を経験していますが、そのときの診断書には「適応障害、抑うつ症状、自律神経失調」というように複数項目に渡って記載されていました。
この場合であれば診断書が発行されますので、休職の手続きを取ることは可能です。
まずはかかりつけ医に相談して、休職を検討していることを伝え、自律神経失調症に関連した診断書を出すことができるかをたずねるのが良いかと思います。
Q3.仕事を続けながら自律神経失調症は治せるのか?

「症状が見られなくなる程度に回復する」という意味では、仕事を続けながらでも治すことは可能です。
ただし、自律神経失調症はストレスや生活習慣が原因であることが多いです。
そのため、仕事で大きなストレスを感じたり、不規則な生活が続いたりすると、また自律神経失調症が再発する可能性は十分あります。
個人的な経験に即していえば、「完治」はなくても日ごろからハメを外しすぎたりしないように、生活リズムや仕事量への注意を怠らなければ、自律神経失調症に悩まされることはずっと減ります。
日常生活や仕事の中で、こちらで解説したとおり、自分なりの回復方法を身につけたりすることで、「自律神経が崩れにくい心身を作ること」が大切です。
自律神経失調症のある部下への接し方
部下や同僚に自律神経失調症の症状があるという人もいるのではないでしょうか?
この章では、自律神経失調症の部下がいる人に向けて、自律神経失調症のある部下への接し方を解説します。
接し方①残業を減らす
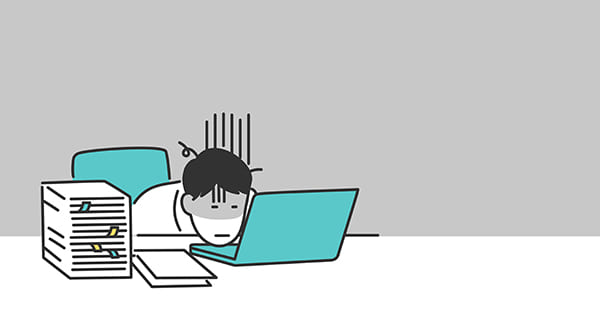
自律神経失調症のある部下への接し方の1つ目は、残業を減らすことです。
定時退勤や時短勤務ができるよう業務を軽減して、本人の身体的疲労を軽減できるよう努めましょう。
そもそも業務量が減っていない場合、精神的な負担を軽減するために、自宅に仕事を持ち帰って、症状を悪化させることも考えられます。
勤務時間内にゆとりを持って業務に取り組めるよう、業務量の調整をしましょう。
接し方②業務内容に配慮する
自律神経失調症のある人は、元気な時よりも、脳の判断能力や処理能力が低下していることがほとんどです。
また、精神的負荷が原因で肉体も疲弊するため、社外の折衝業務やマネジメント業務を避けるように気遣いましょう。
接し方③周囲に個人情報を漏らさない

コンプライアンス的にも、個人情報保護の観点からも、その人の自律神経失調症のことを周囲に漏らしてはいけません。
周囲の人に急に業務量が減ったことをいぶかしむ様子が出たら、「体調不良」とだけ伝える程度でとどめておくことをおすすめします。
本人と話す際は、必ず別室で話し、周囲に情報が漏れないよう気をつけましょう。
接し方④休職の診断が出たら休職させる
主治医から休職の診断が出た場合、すみやかに休職の措置を取りましょう。
やむを得ず業務の引継ぎを聞く場合は、本人が快諾した時のみにし、基本的には業務に関する連絡は控えるなど、配慮しましょう。
自律神経失調症とは?
この章では、自律神経失調症の概要や症状、原因、治療方法について解説します。
自律神経失調症の概要
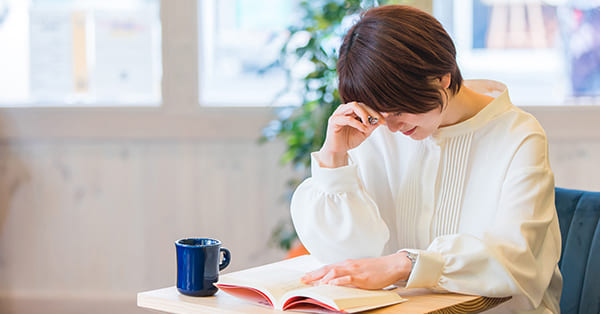
自律神経失調症とは、身体を活発に動かすときに働く「交感神経」と、身体を休めるときに働く「副交感神経」の2種類からなる自律神経のバランスが崩れることによって、明らかな病気がないにも関わらず、心身に様々な症状が生じている状態のことです。
(参考:厚生労働省「自律神経失調症」日本臨床内科医会「自律神経失調症」、こころの耳「自律神経失調症」)
人は普段、交感神経と副交感神経の2つの神経をバランスよく働かせることで、身体の状態を調節しています。
しかし、緊張が続いて交感神経が優位の状態に偏り、リラックスできないことで、不調が生じて心身のバランスが崩れると、自律神経失調症と診断されます。
ただし、自律神経失調症は、医学的には正式な病名ではありません。
診断書に記載されるような病名は、より詳しい検査を経た後に、適応障害やうつ病など、自律神経の乱れを含む「一定の診断基準」に応じて確定されます。
しかし、自律神経失調症自体には、検査値で明確に区別できるような統一された診断基準がありません。
自律神経失調症は、「病気」ではなく、自律神経の失調に関連して症状が生じている「状態」の総称であるという点には注意が必要でしょう。
自律神経失調症の症状
自律神経失調症の症状には、以下のようなものがあります。
- 倦怠感、疲労感
- 微熱
- 息切れ、動悸
- 手足のしびれ
- めまい
- 頭痛、頭重
- 不眠
- 食欲不振
- 腹痛
- 肩こり
以上の症状は、自律神経失調症のある人に限らず、誰にでもしばしば見られる症状です。
また、自律神経失調症以外の病気が原因でも起こりうる症状です。
自律神経失調症によるかどうかに関わらず、以上の症状については病院で検査を受けた結果、適応障害などのなんらかの具体的な診断が下されます。
その診断結果に合わせた治療をすることで、快方に向かっていくのが通常の流れでしょう。
しかし、以上のような症状に関する検査をしても、病気を特定できなかったり、検査結果から症状の重さを説明できなかったりするときには、「自律神経失調症」と暫定的に診断されることがあります。
自律神経失調症の原因

自律神経失調症を発症する明確な原因は明らかになっていません。さまざまな要素が組み合わさり、発症すると考えられています。
ただし、間接的には、以下の2点が原因であることが多いとされています。
- 精神的、身体的ストレス
- 生活習慣の乱れ
例えば、緊張したり不安になったりしたとき、あなたにも手足が冷たくなったり、息苦しくなった経験があるのではないでしょうか?
こうした緊張状態が長引くことにより、身体がリラックスした元の状態に戻せなくなることが、自律神経失調症につながるのです。
また、夜更かしなどで生活リズムが乱れると、不眠や眠りの浅さから寝不足を感じやすくなります。それらが自律神経失調症の原因になる人もいます。
自律神経失調症は、このようなストレスや生活習慣の乱れに対して、身体が発している警報ととらえるとよいでしょう。
自律神経失調症の治療法
自律神経失調症の治療法には、一般的に以下の2つがあります。
- 薬物療法
- その他の治療
薬物療法では、自律神経失調症の方の症状から、抗不安薬・抗うつ薬・睡眠導入剤・睡眠薬・頭痛薬などが処方されます。
症状によっては、自律神経のバランスを整える漢方薬が処方されることもあります。
また、自律神経失調症は、筋肉の緊張やストレスが原因の1つと考えられているため、筋弛緩法やマッサージ、自律訓練法やストレスそのものから引き離す治療が取り入れられることもあります。
まとめ:自律神経失調症でも、対策次第で無理なく働き続けられます

仕事をする上では同僚との協力が欠かせません。
特に、自律神経失調症の症状で調子を崩しやすい人ほど、周りに頼るべき人がいるということが心の支えになるかと思います。
また、同僚でなくても、医師や専門家、就労支援機関など、サポートしてくれる人がいるというのも安心につながるでしょう。
ぜひ、ひとりで抱え込まずに、周囲の人を頼るようにしてください。
このコラムが、自律神経失調症で仕事に悩む人の助けになれば幸いです。
私は自律神経失調症がありますが、仕事を続けたいです。
自律神経失調症のある人が仕事を続けるための対策として、以下が考えられます。
- 周囲の人に理解を求める
- 産業医に相談する
- できるだけ残業しない
- 定期的に休憩をはさむ
- 半日休をうまく活用する
- リラックス法を取りいれる
- 勤務時間を変更する
詳細については、こちらで解説しています。
自律神経失調症は何科にかかるべきですか?
自律神経失調症の場合、症状が多岐に渡るため、最初にかかるべき科が明確にあるわけではありません。
詳細については、こちらで解説しています。
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
執筆寺田淳平
てらだ・じゅんぺい。
高校2年の春から半年ほど不登校を経験。保健室登校をしながら卒業し、慶應義塾大学に入学。同大学卒業後の就職先(3,500人規模)で人事業務に従事する中、うつ病を発症し約10か月休職。寛解・職場復帰後、勤務を2年継続したのち現職のフリーライターに。
2019年に一般財団法人職業技能振興会の認定資格「企業中間管理職ケアストレスカウンセラー」を取得。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→