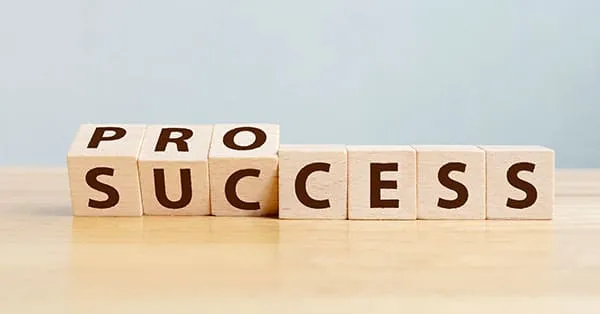【最新版】うつ病での休職による傷病手当金の支給条件や申請方法を解説(法改正を反映)
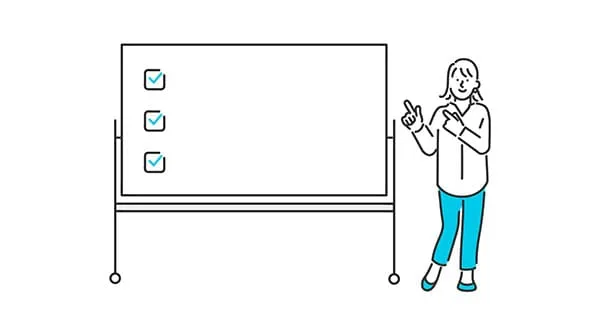
この記事では、うつ病での休職による傷病手当金の支給条件や申請方法を解説します(最新の2022年1月の法改正を反映)。
あわせて、うつ病の人が受けられる傷病手当金以外の経済的支援やうつ病からの復職・再就職・転職方法もあわせて解説します。
なおこのコラムは、全体的に、キズキビジネスカレッジ(KBC)の知見及び、下記の各サイトを参考に執筆しています。
目次
傷病手当金とは?
傷病手当金とは、病気やケガによって会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される手当金です。
対象は、健康保険に加入してる被保険者やその家族です。うつ病によって休職した場合も健康保険に加入していれば傷病手当金を受け取ることが可能です(ただし、任意継続や国民健康保険を除く)。※こちらの章で、もう少し詳しく紹介します。
傷病手当金のほかにも、うつ病の人が受けられる「公的・経済的なサポート」はたくさんあります。
また、うつ病で経済的支援を受けることは恥ずかしいことではありません。
ご安心いただいた上で、ご自分の状況に合った支援を探すことで、経済的に安心して治療・休養に専念することができるはずです。
詳しい人や頼れる人に相談しましょう

傷病手当金も、それ以外のサポートも、うつ病を治療中のあなた一人で検討・申請するのは難しい部分もあると思います。役所や福祉事務所の窓口、主治医などに相談することで、傷病手当金に限らず、あなたに必要なサポートが得られていくと思います。
特に傷病手当金の相談先には、以下のような例があります。
- ご自身が加入している健康保険
- 社会保険労務士
- お勤めの先の担当部署
うつ病の人も受給できる「傷病手当金」の概要
「傷病手当金」の概要をご紹介します。うつ病で仕事を休んでいる方も、対象になります。
(ただし、状況(既に他の受給金を受け取っているなど)によっては、「必ず受給できる」というものではありません)。
①傷病手当金とは
「傷病手当金」は、病気やけがのために仕事を休み、十分な報酬が受けられないときに、健康保険(社会保険)の加入者とその家族に支給されるお金のことです。
- 支払いはそれぞれが加入している保険から行われます
- 受給できる最長の期間は原則として1年6か月です
②「国民健康保険」の加入者は対象外
障害手当金は、「国民健康保険」の加入者には適用されません。自営業・フリーランス・主婦・主夫などの国民健康保険に加入している方は、こちらの章までお進みください。国民健康保険加入者が利用できる支援制度もたくさんありますのでご安心ください。
傷病手当金の詳細:条件、金額、期間、申請の流れを解説
ここからは、もう少し詳しく傷病手当金についてご紹介していきます。(※「実際のあなた」が利用できるかどうか、それぞれの条件が当てはまるかどうかなどは、支援者も交えつつ、前述の相談先と話すことをオススメします。)
①うつ病の人が傷病手当金を受給できる条件

うつ病の人が傷病手当金を受給できる条件は、以下の4つです。
条件(1)うつ病の原因が、仕事「以外」の事由であること
「仕事中や通勤中の病気やケガ」は労災保険の対象になり、傷病手当金は支給されません。
条件(2)うつ病の療養のために仕事が継続できないこと
「療養」には、入院だけではなく自宅療養も含まれます。
仕事の継続が困難かどうかは、本人の主観ではなく、医師の診断や仕事内容などを元に客観的に判断されます。
条件(3)連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
傷病手当金は、療養のために会社を休んだ日が連続して3日間あった上で、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。
- 連続して休んだ3日間を、「待期」と言います。3日間の「待期」の後の、4日目以降の給与分が支払われます。
- 飛び飛びで3日間休んだ場合には、支払い対象になりません。
条件(4)休んでいる期間の給料が支払われていないこと
休んだ期間の給料が支払われている場合は、傷病手当金を受け取ることはできません。ただし、支払われた給料が傷病手当金よりも少なければ、その差額を受け取ることはできます。
②傷病手当金で受給できる金額
傷病手当金では、「支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額」を30日で割った金額の2/3が、1日当たりの金額として受給できます。
別の言い方をすると、1か月で受給できる最高額が、過去1年間の平均月収の約2/3になります。
傷病手当金の受給者も、社会保険料や住民税を支払う必要はあります。
傷支給開始日とは、最初に傷病手当金が支給された日のことです。
支給開始日の以前の勤務期間が12か月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
・支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
・(日本年金機構が定める)標準報酬月額の平均額である、30万円(支給開始日が平成31年4月1日以降の方)
③傷病手当金が受給できない・または減額されるケース

次の条件に当てはまる場合は、障害手当金は受給できません。ただし、傷病手当金の金額の方が各金額よりも大きい場合には、差額を受給できます。
- 休んだ期間の給与支払いがあった場合
- 障害年金・障害手当金を受給している場合(※)
- 老齢退職年金を受けている場合
- 出産手当金を同時に受けられる場合
- 労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合
※特に障害手当との併用受給については、こちらの章で解説します。
④重複受給したお金は返金する必要がある
傷病手当金を(満額)受け取った後に、上記の重複に該当していることが判明した場合は、傷病手当金を返却する必要があります。「それぞれの申請と受給の時期の差」などによって、結果として(意図せず)重複する場合もありますので、詳細は、後述する相談先に相談してみましょう。
⑤傷病手当金を受給できる期間〜法改正で事実上延長となりました〜

この部分が、2022年に法改正された部分です。
傷病手当金を受給できる最長の期間は、原則として1年6か月とお伝えしました。
改正前は、初回受給から1年6か月の間に働いた期間(=仕事を再開して、傷病手当金の受給を中断する期間)があった場合、受給可能期間の1年6か月のうちに、その「働いた期間」も含まれる仕組みになっていました。
つまり、一度仕事に復帰して、その後で再び働けなくなった場合、実際に受給できる期間は1年6か月よりも短かったと言うことです。
2022年の法改正後(受給開始日が令和2年7月1日以降の場合)は、「受給開始日から通算して最長1年6か月までの期間」で受給できるようになりました。つまり、途中で働いて再び働けなくなったときでも、実際に最長で1年6か月受給できるようになったのです。
「傷病手当金の再受給」については、こちらの章で解説します。
⑥傷病手当金申請の流れ
申請の流れは以下のとおりです。
- 加入している健康保険の事務所に問い合わせる
- 書類を入手して記入
- 勤務先と医師に、所定欄に記入してもらう
- 書類を提出する
「申請には期限がある」という点には注意が必要です。申請期限は、「働けない日ごとに、その翌日から2年間」です。
⑦退職後も傷病手当金を受給できるケース

傷病手当金は、次の2点を満たしている場合には、退職後も引き続き受給可能です。
- 被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること
- 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は受け取れません。
退職後に引き続きの受給ができない方は、後で紹介する別のサポートの受給を検討してみることをオススメします。
うつ病が再発した場合でも、再受給できるケースもあります

うつ病が再発した場合(一度仕事に復帰した後に、再度働けなくなった場合)も、傷病手当金を再受給できるケースがあります。(参考:厚生労働省 こころの耳「第7回 こころの病で再休職した場合、傷病手当金を再度支給できる仕組みはあるの?」)
①「最初の受給から、勤務再開期間を除いて1年6か月以内」の場合
「最初の受給のときと同じうつ病」を理由として申請(受給)できます。
②「最初の受給から勤務再開期間を除いて1年6か月を過ぎていた」場合
「最初の受給のときと同じうつ病」を理由とする申請(受給)はできません。ただし、次項③の場合は申請可能です。(受給できるかどうかは改めて審査があります)
③「最初のうつ病」が完治した場合
「最初のうつ病」が完治している場合、「再発したうつ病」や「別の病気・けが」を理由とする申請(受給)は可能です。その場合、最長の受給期間は、再び1年6か月になります。
ここで言う完治とは、「社会的な完治」を意味します。
「本人が治ったと主観的に感じているだけ」や「医師が完治したと診断しただけ」では認められません。「通常の社会生活に復帰した(=社会的に完治した)後に再発した」と認められた場合のみ、新規に受給することができます。
「傷病手当金」は、「障害年金」と併用できるケースがあります

「障害年金」とは、傷病手当金と同じく、うつ病などの病気やケガで障害を負った場合に支給される年金です。年齢に関係なく、年金加入者であれば若い人でも受給できます。
①「傷病手当金」と「障害年金」の同時受給
同一のうつ病を理由に、「傷病手当金」と「障害年金」の両方に申請する場合、「傷病手当金」の金額の方が大きければ、「障害年金」との差額を受給できます。「障害年金」の金額の方が大きい場合は、「傷病手当金」の受給はできません。(参考:協会けんぽ※PDF「障害年金との調整」)
なお、差額の調整を行わずに「傷病手当金」と「障害年金」を同時に受給していた場合は、調整の上、「傷病手当金」を返還する必要が生じます。
(その代わり、うつ病と認定された日からの分、障害年金が支給されます)両方の申請・受給をするときは、両方の申請先に必ず連絡をしておきましょう。
ただし現実的には、それぞれの申請・受給の時期が異なるため、「結果として調整前に両方の満額を受け取り、事後的・事務的に返還手続きを行う」ことはあるようです。
②「傷病手当金」と「障害年金」の違いの例

その他、「傷病手当金」と「障害年金」には、次のような違いがあります(一部です)。
- 障害年金は、心身の状態が「障害の基準」に該当している間はずっと受給できる
(傷病手当金は、働き始めたら支給がストップされる。また、同一の理由による受給は最長で1年6か月) - 障害年金は、国民健康保険の加入者も受給できる
(障害手当金は、国民健康保険の加入者は対象外) - 障害年金は、その理由となるうつ病(などの病気・けが)の初診日から1年6か月後から申請できる
(傷病手当金は、休んで4日目から申請できる)
「今のあなたの状況」でどちらを(または両方を)申請すべきかなどについては、専門家に相談しましょう。
③障害年金の詳細
「障害年金」の種類や金額などの詳細は、下記コラムをご覧ください。
うつ病の人が受けられる、傷病手当金以外の経済的支援8選

うつ病の人が受けられる経済的支援(お金を受給できる支援と、各種支払いが減免できる支援)は傷病手当金だけではありません。支援制度は他にもたくさんありますので、ご安心ください。
この章では、代表的なものを簡潔に紹介します。詳細は、下記コラムで紹介しています。よければご覧ください。
「実際のあなた」が利用できるかについては、各窓口や専門家などに相談してみましょう。
傷病手当金も含めて、経済的支援を受けることは、決して恥ずかしいことではありません。各種支援を受けつつ、経済的に安心して、うつ病の治療・休養に専念することで、「次の一歩」にも進みやすくなります。
支援①特別障害者手当

特別障害者手当とは、「精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方」が、月額27,350円を受給できる制度のことです。相談先は、市区町村役所です。
ただし、ご本人・配偶者・同居のご両親などの前年の所得が一定の額以上であるときは支給されません。(参考:厚生労働省「特別障害者手当について」)
支援②失業手当(雇用保険給付)
失業手当とは、うつ病に限らず、失職した人が再就職するまでの一定期間に受給できる給付金です。窓口は、各自治体に設置されているハローワークです。(ハローワークの全国一覧はこちらです)
支援③労災保険

労災保険とは、業務や通勤中にケガや疾病といった「労働災害」が発生した場合に、その補償を得られる制度です。アルバイトやパートタイマーなども利用できます。
ただし、一般的にうつ病などの精神障害の労災認定は非常に難しいと言われています。気になる人は、労働基準監督署(全国の一覧はこちら)やお勤め先の人事部などに相談してみましょう。
支援④生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援制度は、うつ病に限らず、仕事や住まいの確保に困窮している方を支援する国の制度です。
- 詳細は、厚生労働省ウェブサイト「制度の概要」をご覧ください。
- 窓口は、お住まいの都道府県または市の担当部署です。
支援⑤生活福祉資金制度
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、(うつ病の人を含む)障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。(参考:全国社会福祉協議会「福祉の資金(貸付制度)」)
それぞれの世帯の状況と必要に合わせて、生活な必要な資金を借りることができます。
窓口は、市区町村社会福祉協議会です。(全国の一覧はこちらです)
支援⑥自立支援医療制度

自立支援医療制度とは、うつ病で継続的な通院が必要な場合などに、医療費の自己負担額を軽減する公費負担の医療制度です。
お住まいの自治体の福祉課などの窓口、病院、市区町村に設置されている「障害者就業・生活支援センター」で相談してみましょう。
支援⑦生活保護
生活保護制度は、うつ病かどうかに関わらず、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とするものです。
相談窓口は、お住まいの地域の福祉事務所(ない町村の場合は町村役場)の生活保護担当課です。生活保護の詳細は、下記コラムをご覧ください。
生活保護は、一般的には「うつ病だから」という理由「だけ」での受給は難しいです。また、生活保護よりも、「他の公的な支援」の申請(・受給)が優先されます。先に「生活保護以外の支援」を当たることをオススメします。
支援⑧障害者手帳による税金などの減免

うつ病の症状によっては、障害者手帳を取得できます。障害者手帳を取得すると、次のような支払いが減免されることがあります。
- 所得税・住民税
- 医療費
- 各種公共料金(公共交通機関の運賃、上下水道料金、NHK放送受信料、携帯電話料金、公共施設の入館料等)
また、失業保険の給付期間が延びたり、(再)就職や転職の際に障害者枠の利用ができたりというメリットもあります。
障害者手帳によるメリットの詳細は、下記コラムをご覧ください。
うつ病からの復職・再就職・転職方法
うつ病の病状が落ち着いてきたら、復職(元の職場への復帰)・再就職・転職も見えてきます。
うつ病を経験した後の復職・再就職・転職は、もちろん可能です。詳細は、下記のコラムをご覧ください。
復職はこちら
再就職はこちら
転職はこちら
再就職・転職を目指すなら、就労移行支援事業所がオススメ!

特に再就職・転職を目指す方には、就労移行支援事業所の利用がオススメです。
就労移行支援事業所とは、「病気や障害のある人の(再)就職・転職を援助する福祉サービス」のことです。
各事業所は、公的な認可を得た民間事業者が運営しています。そのサービス内容は、次のように多岐にわたります(一例であり、事業所ごとに様々なサービスを行っています)。
- 転職のための知識・技能の習得
- 履歴書・経歴書・エントリーシートの作成支援
- メンタル面のサポート
- 再就職・転職先候補や、職場体験実習(インターン)の紹介
- 転職後の職場定着支援
利用の可否は、お住まいの自治体が、下記などに基づいて判断します。
- 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などがある
- 18歳以上で満65歳未満の方
- 離職中の方(例外あり)
※上記を満たすなら、障害者手帳を所持していなくても利用可能です。
ご自身が利用できるかどうかは、自治体や、各就労移行支援事業所に相談してみましょう。
就労移行支援についてさらに詳しく知りたい方は、下記コラムをご覧ください。
適職を見つけたいうつや発達障害のあなたへ
- 初任給
- 38万円
のケースも
- 就職まで
- 4ヶ月
※1
- 就職率
- 83%
※2
※1:他社就労移行支援事業所では通常1年半(自社調べ)
※2:他社就労移行支援事業所では約52%(自社調べ)
ご相談・資料請求は無料です!
お好みの方法でご連絡ください
まとめ:公的なサポートを受けることは決して恥ずかしいことではありません

うつ病の人は、条件に合えば傷病手当金を受給することは可能です。傷病手当金に限らず、公的なサポートを受けることは、決して恥ずかしいことではありません。
詳しい人に相談しながら、あなたに合うサポートを探しましょう。各サポートを受けながら治療も続けることで、うつ病の寛解や、就職や転職などの「次の一歩」も近づいてくるはずです。
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
執筆内田青子
うちだ・あおこ。1982年生まれ。上智大学文学部卒。
大学卒業後、百貨店勤務などいくつかの仕事を経た後、2018年から発達障害・不登校・中退経験者などのための個別指導塾・キズキ共育塾で講師として国語(現代文・古文・漢文)と小論文を指導し、主任講師となる。
並行して、聖徳大学通信教育部心理学科を卒業。現在、公認心理師の資格取得を目指して、発達障害や不登校支援についてさらに勉強中。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→
うつ病の自分は、傷病手当金を申請・受給できるのでしょうか。
条件を満たせば可能です。傷病手当金の条件、金額、期間、申請の流れなどは、こちらをご覧ください。
うつ病の自分が受けられらる、経済的な支援を知りたいです。
傷病手当金以外にも、特別障害者手当、失業手当(雇用保険給付)、生活困窮者自立支援制度、生活福祉資金制度、自立支援医療制度などが考えられます。詳細はこちらをご覧ください。