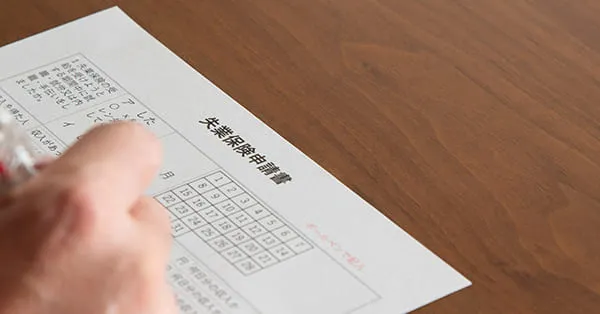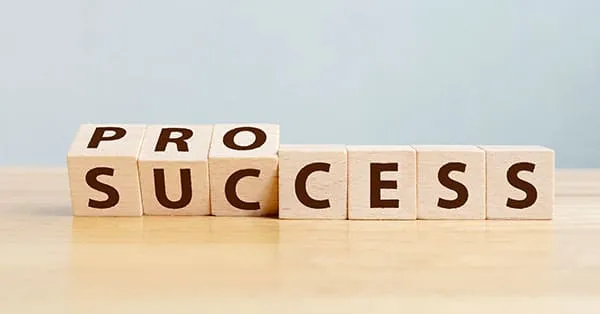うつ病の初期症状とは? うつ病のある人が仕事中にとる行動や日常生活で見られるうつ病のサインを解説

こんにちは、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
仕事をしているときにふと、「これはうつ病の初期症状かもしれない」と感じることがありませんか?
しかし、実際にうつ病かどうかを見分けるのは容易ではありません。
あなたも、以下のようにうつ病かどうかの区別がつかずに悩んではいないでしょうか?
- 仕事をしていたら憂鬱になることくらいあるはず…
- 仕事で落ち込んでもまだ病院に行くほどじゃないはず…
- 気が滅入るのは確かだけど、うつ病かどうかわからない…
このコラムでは、お仕事をしている人向けに、うつ病の初期症状や対策、利用できる支援機関やサービスについて解説いたします。
ご本人はもちろん、「あの人はうつ病になりかけているかもしれない」と思っているご家族や職場の人の参考にもなるかと思います。
セルフケアの方法まで紹介しますので、うつ病の初期症状でお悩みの人は、ぜひ本コラムを参考にしてください。
ただし、あくまでも「参考」です。
このコラムを読んで「うつ病かもしれない」と思い当たったときは、本当にうつ病かどうか、ケアや治療をどうするかについては、医療機関にきちんと見てもらいましょう。
目次
日常生活で見られるうつ病の初期症状10点
うつ病は、放置しているといつの間にか重症化するケースもあります。
そのため、うつ病は初期症状が出たタイミングで気づき、早急に対処する必要があるのです。
この章では、日常生活で見られるうつ病の初期症状を、身体面・精神面・行動面に分けて紹介します。
初期症状①身体面にあらわれるうつ病の初期症状4点

身体面にあらわれるうつ病の初期症状は、主に以下の4つに分けられます。
- 睡眠障害:寝付けない、目が覚める
- 慢性疲労:だるい、身体が重い
- 微熱:熱っぽさが続いている
- 身体の痛み:原因不明の頭痛や腹痛がある
以上の4つに共通するのは、「慢性的に続く」という点です。
たとえば、疲労の場合、通常は休養を取れば解消されるはずです。
頭痛や腹痛も一過性の場合が多いでしょう。
しかし、うつ病の場合、波はあるものの症状が長く続きます。
とはいえ、うつ病以外の疾患による症状の可能性もあるため、身体の痛みなどを感じた際にはまず内科を受診するようにしましょう。
内科を受診して、特に原因が見つからなかったり自律神経失調症などと判断されたり、ストレスの影響であると明言されたりしたら、うつ病を疑ってみてください。
ちなみに私の友人が仕事をしながら「うつ病かもしれない」と思ったときは、上記の4つすべてを初期症状として感じていたそうです。
何度か内科へ通院はしましたが、いつも自律神経失調症としか診断されなかったため、メンタルクリニックを訪れたところ、はじめてうつ病という診断をくだされたと言います。
上記の初期症状をもとに、病院へ行っても解決しない場合は、心療内科などにセカンドオピニオンを求めてみるといいでしょう。
初期症状②精神面にあらわれるうつ病の初期症状3点
精神面で見られるうつ病の初期症状としては、主に以下の3つです。
- 感情の鈍麻:憂鬱で気が晴れない
- 欲求の減退:食欲や性欲が著しく減った
- 意欲の低下:何もする気になれない
以上の中でも特に注意してほしいのは、3番目の「意欲の低下」です。
うつ病になると、それまで楽しめていた趣味や他人に対する関心をすっかり失う場合があります。
これは、普段からあまり行動的でなかったり外向的でなかったりするタイプの人には気づきにくい点です。
人によっては「疲れているだけだろう」とか「忙しいから興味を持てないだけだろう」と思って見逃がすこともあります。
感情や欲求だけでなく意欲も減退していないか、自分の心を注意して観察してみましょう。
初期症状③行動面にあらわれるうつ病の初期症状3点

行動面に見られるうつ病の初期症状としては、主に以下の3つがあります。
- ボーっとすることが増えた
- 時間を守れなくなった
- 人との接触を避けるようになった
以上の3点は、自分ひとりではなかなか気づきにくいかもしれません。
特に1番目と2番目のサインは、周囲の人がうつ病の初期症状を疑いはじめたときにまず挙げる症状です。
ちなみに2番目は、うつ病経験のある友人の話としては、時間の感覚が狂ったことに由来するようです。
「ボーっとすることが増えた」せいもあるかもしれませんが、気がつくとあっという間に締め切りや約束の時間になって、慌てて支度を始めるといった感覚です。
結果として遅刻が増えるという現象で自覚されます。
うつ病を疑いはじめたときは、自分上記のような傾向が最近ないかを身近な人に尋ねてみるといいでしょう。
うつ病のある人が仕事中にとる行動10点
日常生活に限らず、うつ病のある人は仕事中でも特定の行動をするケースがあります。うつ病かも?と感じている場合は、チェックしてみましょう。
この章では、うつ病のある人が仕事中にとる行動を紹介します。(参考:坪井康次・監修『患者のための最新医学 うつ病 改訂版』)
行動①物忘れやケアレスミスが多くなる

うつ病になると、これまで仕事ができていた人でも、物忘れやケアレスミスが増えます。
理由としては、あまり寝れなかったりだるさが続いたりすることにより、仕事に集中できなくなるからです。
具体的に見られる行動として、以下のような行動が挙げられます。
- 大事な約束をすっぽかす
- 文面の誤字脱字が多くなる
最近になって注意されることが増えてきたと感じたら、注意しましょう。
行動②同僚との会話を避けるようになる
うつ病になると、他人との会話を避けるようになります。なぜなら、憂鬱だったり意欲が低下したりすることで、他人と会話する気力が残っていないからです。
たとえば、以下のような傾向が見られはじめたら、うつ病の初期症状である可能性があります。
- 会議で発言しないことが増えた
- 食事や飲み会の誘いを断ることが増えた
周りとのコミュニケーションが取れているか、今一度気にかけてみましょう。
行動③遅刻や欠勤が増える

遅刻や欠勤が増えるのも、うつ病のサインのひとつです。特に、今まで遅刻や欠勤をしたことが少なかったなら、気をつけて見るべき行動の変化と言えます。
これは、ボーっとすることが増えたり時間の感覚が狂ったりすることが原因です。
もちろん、遅刻や欠勤をしようと思ってしているわけではなく、いつの間にか時間が過ぎているという感覚ですね。
意外に初期症状が出ていることに気づけない場合も多いため、今一度自身の出勤履歴を確認してみてはいかがでしょうか。
行動④離席が増える
うつ病のある人は他人との接触を避けるようになり、それに伴って離席も増えます。
大勢の社員が同じフロアで仕事をしている空間がいたたまれず、休憩時間ではなくても席を離れるのです。
また、注意力や集中力が低下しているため、仕事に打ち込めず、頻繁にリフレッシュするために席を離れる場合もあります。
席を離れている時間が増えたと感じる場合は、気に留めておきましょう。
行動⑤机上が散らかりはじめる

机の上が散らかり始めたら、それはうつ病のサインです。注意力が散漫になっているため、整理整頓ができなくなってしまいます。
たとえば、以下のような状態だと、整理整頓ができていないと言えるでしょう。
- 机の上に資料が山積みになっている
- 探し物がなかなか見つからなかったりする
あなたのデスクはきれいですか?一度、確認してみてください。
行動⑥電話の受け答えが緩慢になり沈黙が増える
他人との会話を避けることの延長線で、うつ病になると電話対応にも変化が出てきます。
気分の落ち込みや注意力の低下によって、受け答えが緩慢になったり沈黙が増えたりするのです。
具体的には「はぁ…」「そうですね…」のような返事が増えたり、「聞こえてますか?」と言われる機会が増えたりすることなどが挙げられます。
このような症状が出ている場合は、うつ病を疑った方がいいでしょう。
行動⑦眠気が強く日中でも朦朧としている
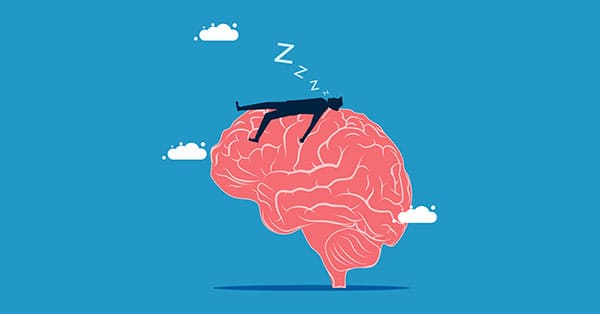
人によっては、うつ病になることによって強い眠気が出るケースがあります。これは、夜によく眠れないことにより、日中でも眠くなるのです。
以下のような行為が思い当たる場合は、うつ病からくる眠気の可能性があります。
- パソコンを操作しながらうたた寝する
- 会議中に居眠りする
夜にある程度寝ても日中に眠くなる場合もあるので、留意しておいてください。
行動⑧自分を責めるような発言が増える
うつ病になると精神が不安定になるため、自分に自信がなくなり、自分を責めるような発言が増える場合があります。
「私なんていなくてもいい」「ほかの人がやればよかったんだ」などの発言が増えてきたら、要注意です。
当事者は自分を責めている認識がない場合もあります。周りに自分の発言が変わってきていないか聞いてみるのもいいでしょう。
行動⑨話し方に抑揚がなくなり極端に声が小さくなる

気持ちが落ち込むのは、うつ病の代表的な症状のひとつです。
そのため、「話し方に抑揚がなく覇気がない」「声が小さくて聞き取れない」などと言われることが増えたら、うつ病の初期症状を疑いましょう。
たいていの場合は、自分でも気づかぬうちにこのような状態になっています。周りの反応を注意深く見てみましょう。
行動⑩イライラして投げやりな態度をとる
精神が不安定になったり気分が落ち込んだりすることによって、イライラしやすくなり、投げやりな態度を取りやすくなります。
具体的には、貧乏ゆすりをしたり舌打ちが増えたりすることなどが挙げられます。人によっては、声を荒らげたり暴力的になったりすることもあるでしょう。
最近イライラしていると感じたら、注意してください。
仕事でうつ病の初期症状が出たときにすべき7つの対応
うつ病の初期症状は無視してはいけません。
この章では、仕事でうつ病の初期症状が出たときにすべき対応を解説します。
対応①勤務先に相談する

まずは、勤務先に相談するのがオススメです。うつ病の初期症状が出ていることや原因と思われることを話してみましょう。
原因が仕事環境によるものであれば、勤務先に相談するとすぐに対処してくれる可能性があります。たとえば、仕事の量や責任、人間関係などです。
勤務先に相談窓口があればそこへ連絡し、なければまず直属の上司に相談してみるのがいいでしょう。
対応②産業医面談を実施する
労働者が希望した場合には、メンタルヘルスの専門家である産業医の面談を受けることが可能です。
産業医とは、労働者の健康管理に関して、専門的な立場から助言や指導を行う医師のことです。
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業所に1人以上、3000人超の事業所では2人以上の産業医を選任しなければならないことが定められています。(参考:厚生労働省「産業医について」)
上記の条件を満たしていれば、あなたが勤めている企業にも産業医がいるはずですので、一度確認してみるといいでしょう。
面談の結果次第では人事考課や給与査定に影響が出るのではないかと心配されるかもしれませんが、産業医は中立的な立場から診断を行いますので、ご安心ください。
もし企業側から説明を求められても、個人情報保護の観点から共有していいかを原則ご本人に確認することになります。
料金等も発生しません。メンタルに不調を感じるなら、産業医面談を実施するのもひとつの手です。
対応③外部の相談窓口に相談する

以下のような理由で、勤務先に相談しづらい人もいるでしょう。
- 何を言われるかわからない
- 信用できる人がいない
そんな場合は、外部の相談窓口を利用するのがオススメです。
たとえば、厚生労働省が委託している「こころの耳」では、仕事に関する相談やこころの健康に関する相談など、さまざまなケース別で相談窓口を紹介しています。
国が設置している機関であれば安心でしょう。勤務先に相談できないときはこちらを利用してみてください。
こころの耳「相談窓口案内」
対応④病院へ行く
相談や産業医面談もできますが、病院へ行き、専門医の判断を仰ぐことも可能です。
うつ病の初期症状を感じたとき、勤務先に相談先がないとき、勤務先との提携の対応が自分に合っていないと思うとき、病院に行かずに症状が悪化したと感じたときなどには、遠慮せずに医療機関の診察を受けましょう。
うつ病になると、思考力と判断力が鈍ります。
ご自身ではまだ大丈夫だと思っていても、専門家の目から見るとすぐに治療・療養した方がいいと判断される場合があります。
診断を受けた段階で投薬や休職を提案されたときには、素直に従った方がいいでしょう。
医師の診断にどうしても納得できなかったり、処方された薬を服用することに抵抗があったりする場合は、セカンドオピニオンを求めて別の病院へ行くのもひとつの手です。
元の先生と違う方針を示された場合には、あなたが安心して治療を進められそうな方に従ってください。
ただし一般論として、セカンドオピニオンでも治療の方針があまり変わらないようなら、多少納得できないところがあっても、元の方針に従うことをオススメします。
また、代替医療や民間療法ではなく「病院」の治療を受けるという点も重要です。
行こうとしているところがきちんとした専門機関かどうかを確認してから診察を受けるようにしましょう。
対応⑤休職を検討する

職場に相談しても状況が改善されなかったり、病院の先生から休職を提案されたときは、休職を検討してみましょう。
心に余裕がないことが原因でうつ病の初期症状が出ていた場合は、一旦休職して仕事から距離を置くことで改善するケースがあります。
休職する際は、家族へ連絡したり経済面が大丈夫かを確認したりしましょう。
うつ病のある人が休職する際の確認事項については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
対応⑥退職を検討する
うつ病の原因が勤務先にあって改善の兆しが見えないとき、または復帰してすぐにうつ病が再発したときは、退職を検討するのもひとつの対策です。
パワハラやセクハラ、残業の常態化など原因の根本が勤務先にある場合は、何度戻ってもうつ病は治りません。
しかし、退職は大きな決断になるため、慎重になりましょう。
うつ病での退職前にすべきことについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
また、うつ病で退職する場合、失業保険を受け取れる可能性があります。
失業保険を受給する方法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
対応⑦転職を検討する

勤務先が原因でうつ病を発症したが働くことは辞めたくない場合は、転職を検討してみましょう。
職場環境が改善したところ、うつ病の初期症状が治まったケースもあります。
うつ病の転職のポイントについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
「うつ病のある人が転職なんてできるの…?」と思われる方もいるかも知れません。そう思った方は、以下のコラムを読んでみてください。うつ病は転職に不利とは限らないことがわかるはずです。
また、40代になってうつ病を発症し、転職を考えている方もいるでしょう。年を重ねてからの転職は不安ですよね。
そんな方は、以下のコラムを読んでみてください。40代での転職のポイントを紹介しています。
うつ病の初期症状が見られたときにできるセルフケア7選
うつ病に限らず、病気のときは適切に医療機関を利用することが大切です。
ただし、「風邪をひかないために、うがい・手洗いをする」ように、うつ病になる前にできるセルフケアもあります。
それでは、うつ病の初期症状を感じはじめたときにできるセルフケアにはどのようなものがあるのでしょうか?
この章では、うつ病の初期症状が見られたときにできるセルフケアを解説します。
セルフケア①生活リズムを整える

うつ病を予防するために最初にしておきたいことは、「生活リズムを整える」です。
睡眠障害が出るようになると、つい二度寝をしたり、夜更かしをしたりして、生活リズムが乱れてしまいます。
日中も眠気を感じることが増えるでしょう。
しかし、それによって生活リズムが崩れると、意識が朦朧とした中で仕事をしなくてはならないため、ストレスが倍増します。
睡眠不足を感じた際は、こまめに昼寝をすることで補いましょう。
休むことは大切ですが、「休日は不規則に過ごす」のではなく、休日であってもできるだけ平日と同じ生活リズムを保つようにしてください。
セルフケア②散歩や軽い運動をする
次にオススメしたいのは、「散歩や軽い運動をする」というものです。
これには科学的な根拠があります。
運動をすることで、不安や恐怖感といったうつ病の初期症状を抑える精神伝達物質セロトニンが分泌されるという研究結果が出ているのです。(参考:「Phys Ed: Why Exercise Makes You Less Anxious」)
セロトニンには、精神を落ちつかせるだけでなく、痛みをやわらげる効果もあります。
特に日光を浴びながら身体を動かせば目も覚めて、生活リズムも整ってくるでしょう。
具体的な運動メニューとしては以下の3つがオススメです。
- 近所を10分だけ歩いて帰ってくる
- 10分程度の縄跳び
- 30回だけスクワットをする
上記を行うことで、血流がよくなり、頭が冴えてくるというメリットも期待できます。
ストレスによる憂鬱感を払いたいという人は、ぜひ散歩や軽い運動を取り入れてみてください。
セルフケア③身近な友達や家族に悩みを話す

セルフケアの3点目は、「身近な友達や家族に悩みを話す」です。
うつ病の初期症状のひとつに、人と話すのが面倒になるというものがありました。
その状態を維持していると、コミュニケーションがますます苦手になり、人と話しづらくなるという悪循環に陥るおそれがあります。
とはいえ、初対面の人といきなり話をするというのは難しいものです。
そこで、仲のいい身近な友達や家族に悩みを打ち明けて相談に乗ってもらうといいでしょう。
信頼できる人に話してみることで、自分の感情や考えを俯瞰的に見られるようになります。
悩みの解決法が具体的に見つかったり、話すだけで気が楽になったり、悩みが大したことではないと気づいたりして、初期症状が緩和される場合があるのです。
また、声を出すことで、身体があたたまると同時に自然と呼吸が深くなってくるので、心を落ちつけられるという効果があります。
ひとりで抱え込まずに、身近な友人や家族にご自身の状態について相談してみてください。
セルフケア④冬季性うつ対策として日光浴をする
「日光浴をする」というのも、セルフケアとして有効な手段です。
近年話題にのぼるうつ病の一種として、「冬季性うつ」と呼ばれるものがあります。
冬季性うつは季節性情動障害(SAD)の一種で、秋から冬にかけて抑うつ状態が続くのが特徴です。
要因としては、体内時計が狂う「概日リズム障害」が挙げられますが、根底にあるのは季節変化に伴う日照時間の減少です。
この冬季性うつ病対策としては、日光浴のような光療法が有効と考えられています。
特に女性は男性の3倍近くかかりやすいと言われていますので、日に当たる時間が少なくなっていないか注意が必要です。(参考:Royal College of Psychiatrists「季節性感情障害(SAD)」)
冬季性うつ対策のためにも、意識的に日光を浴びる時間を増やすようにしましょう。
セルフケア⑤お風呂に浸かる時間を増やす

5点目は、「お風呂に浸かる時間を増やす」というものです。
湯船に浸かって体温を上げることで、不安や恐怖心を解消することができます。
また、血流が良くなり酸素が頭をめぐるようになることで、うつ病の初期症状として見られがちな「ボーっとする」感覚を軽減する効果もあります。
上述した冬季性うつ病対策としても有効なため、体温の下がりがちな冬などは特に湯船に浸かって温まる時間を作るようにしましょう。
セルフケア⑥一日にあったことを紙に書きだす
うつ病の初期症状で悩んでいる人は、その日にあったことをぜひ紙に書きだしてみてください。
こちらでも紹介しましたが、うつ病になる人は、自分が具体的に何にストレスを感じているのかを理解していないことがあります。
ストレス源がわかっていれば対処が可能ですが、それが認識できていないために行き詰まるのです。
一日にあったことを紙に書きだすことで、自分が何にストレスを感じたのかを把握できるようになります。
医療機関からも治療の一環として日記を書くことを勧められることがあり、一日の出来事を紙に書きだすことは、うつ病対策として有効な手段のひとつです。
抑うつ感にお悩みの場合は、その日に起こった出来事や思ったことを紙に書きだしてみるとよいでしょう。
セルフケア⑦ストレス源から離れる

疲れているときは、「ストレス源から離れる」ことも大切です。
うつ病の初期症状を感じている人は、自責感もあいまって「問題と向き合わないと」と気負うことがあります。
しかし、常に自分を追い込んでいると、どうしても心身ともに疲れてくる場面が出てくるものです。
そうした事態を避けるためにも、ストレス源から距離を置くという選択肢を持っておくといいでしょう。
具体的な方法のひとつに、有給休暇を繋げて休養をとることが挙げられます。
まとまった休暇が取れないようであれば、煩わしさを感じる人間関係から少し距離を取ってみるだけでもかまいません。
本当に疲れ切る前に、ストレス源から離れる方法はないかを考えてみましょう。
うつ病の初期症状に関する2つの事例
風邪であれば、初期症状としてのどの痛みや鼻づまりが出てきても、「これくらいなら大丈夫か」と放っておくうちに治ることもあるでしょう。
しかし、うつ病の初期症状と思うときには、無視してはいけません。適切な治療を受ける必要があります。
また、受診することで、「うつ病ではないけれど、別の病気や障害があった」ということに気づける場合もあります。
この章では、うつ病の初期症状に関する2つの事例を紹介します。
事例①初期症状を見過ごしたことで重篤化したケース

事例の1つ目は、初期症状を見過ごしたことでうつ病が重篤化した、Aさんのケースです。
Aさんがうつ病になったのは、オーバーワーク(過労)の結果でした。
初期症状として、書類整理ができなくなったり、電話応答時にうまく言葉が出てこなかったり、という現象があらわれていました。
ですが、「忙しくて疲れているのだろう」「通常の疲労の範囲だろう」と判断して、まとまった休みをとることもなく仕事を続けていたのです。
しかしあるときに、朝起きると身体を動かすことができないほどに疲れ切っていることに気づきました。
少し休暇を取ったのですが、この段階までくると、休みを取った後ですら意欲が枯渇して、掃除洗濯といった日常生活にまで支障をきたすようになっていました。
もはや、トイレや入浴すら面倒になるほどです。
結果として、1年近い休職を余儀なくされました。
仕事などの社会生活に若干の支障をきたす程度の「軽症うつ」の段階で対処しないと、Aさんのように日常生活にも問題が起きて回復までに時間がかかる場合があります。
逆に言うと、うつ病は上記の初期症状が見られた時点で早めに対処することで、回復も早めになります。
事例②うつ病の初期症状ではなく発達障害だったケース
事例の2つ目として紹介したいのが、うつ病の初期症状だと思っていたら実は発達障害だったというBさんのケースです。
ADHD(注意欠如・多動性障害)の症状の代表例として以下のようなものがあります。(参考:田中康雄『大人のAD/HD』)
- 忘れ物やミスが多い
- 時間が守れずに遅刻する
- 整理整頓が苦手で物をなくしやすい
ご覧のとおり、うつ病の初期症状に似たものがありますよね。
Bさんは、ミス、紛失、遅刻などがあまりにも続くためうつ病を疑って病院に行きましたが、その際に受けた診断結果ではじめて自分がADHD(注意欠如・多動性障害)だということに気づいたのです。
その人はご自身の障害を理解した上で仕事の進め方を工夫したり、同僚にADHD(注意欠如・多動性障害)を開示することで配慮を受けたりすることで、問題解決に至りました。
以上のように、うつ病の初期症状だと思っていたら、実は発達障害の性質のひとつだったというケースもあるのです。
自己判断で「自分はうつ病になりかかっている」と決めつけて対応せず、適切に医療機関を頼ったことで「自分に合った対応」が見つかりました。
仕事に関連してうつ病を発症した場合の治療方法3選
この章では、仕事に関連してうつ病を発症した場合の治療方法を紹介します。
仕事が関連しないうつ病でも、共通する部分はあるため、ぜひ参考にしてみてください。(参考:こころの耳「Q4:うつ状態の診断で休職中の社員の治療方針を知りたい:専門家が事例と共に回答~職場のメンタルヘルス対策Q&A~」)
治療方法①休養

休養は基本的な治療法ですが、実は最も重要です。
休養はうつ病の治療に限らず、たいていの体調不良・病気において自然治癒力を最大限に発揮してくれます。
休養の方法としては、主に「完全に仕事をストップして休む方法」と「働きながら休む方法」の2つです。
「完全に仕事をストップして休む方法」では、休職や退職をして、完全に仕事と離れた状態で体と心を休めます。
「働きながら休む方法」では、残業を減らしたり出勤日数・時間を減らしたりすることで、休養する時間を増やしていきます。
あなた自身と職場の状況や医師の判断などを踏まえて、どのように休養するかを検討しましょう。
治療方法②薬物療法
薬物療法は、文字通り、薬を服用してうつ病の改善を目指すものです。
不安症状には抗不安薬、不眠症状には睡眠導入剤といったように、症状ごとに薬を服用します。
薬の服用を不安に思う場合は、担当の医師に伝えてみてください。
なぜその薬が必要なのか、あなたが納得して安心するまで教えてくれるはずです。
治療方法③相談や精神・心理療法

相談や精神・心理療法は、内側の意識から変えていく治療法です。
医師やカウンセラーとの対話を繰り返しながら、ストレスに対しての捉え方や気分が落ち込んだときの考え方などを見直していきます。
これはうつ病のある人だけではなく、生活習慣病のある人が生活習慣の改善を目指すときにも用いられます。
「病は気から」という通り、自分の考えや思いを変えることによって、体や心にも影響があるということですね。
内側の考えから変えることができれば、再発防止にもつながります。
ゆっくり確実に治していきたい場合には、相談や精神・心理療法もひとつの手です。
うつ病のある人が社会復帰するときの3つのポイント
うつ病のある人が社会復帰を考える際、「早く戻らなきゃ」とあせるケースがあります。
しかし、とりあえず戻っても、またうつ病を発症しては意味がありません。
この章では、うつ病のある人が社会復帰するときの3つのポイントを解説します。
ポイント①ストレスの原因が何かを把握する

うつ病になるということは、職場に何らかのストレスがある可能性があります。
うつ病を再発させないために、ストレスの原因が何かを把握しましょう。
厚生労働省の調査によると、仕事のストレスの原因の第1位は「仕事の量」で「仕事の失敗、責任の発生等」「仕事の質」と続いています。(参考:厚生労働省「令和4年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概要」)
何でストレスがかかっているのかを把握できれば、元の勤務先に戻るにしろ、新しい職場へ行くにしろ対策が取れるようになります。
たとえば、仕事の量が主なストレスの原因になっているのであれば、減らしてもらえるように交渉したり、元から仕事量が少ない職場を探したりできますよね。
うつ病を再発させないためにも、ストレスの原因を把握することは重要なのです。
とはいえ、うつ病は仕事とは関係ないストレスで発症することもありますし、明確な原因がわからない場合もあります。
あくまで、ストレスの原因が何かを把握できるとうつ病が悪化しづらくなるということであり、原因がわからないとダメなわけではありません。
社会復帰のポイントのひとつとして知っておきましょう。
ポイント②社会復帰=元の勤務先へ戻ることではない
うつ病からの社会復帰とは、「休職後に元の勤務先へ戻る」だけに限りません。
その内容は様々です(就労以外の観点も含めるなら、大学などに入って学び直すというルートもあります)。
- 退職を経て転職
- 障害者雇用枠への切り替え
- (一時的な)パート・アルバイトとしての勤務
もしかしたらあなたは、「なんとしても元の職場に戻らなくては」とお考えかもしれません。
ですが、そうした考え方にこだわらずに、あなたにとって無理のない働き方を柔軟に模索することが、社会復帰を検討する上では大切になります。
つらくならない範囲で構いませんので、治療を進めながら「あなたにとっての社会復帰をどこに設定するか」を少しずつ考えていきましょう。
社会復帰を考える上では「復帰後のこと」も考えることが重要だということは、心に留めておいてください。
もしアルバイトを考えている場合は、以下のコラムを読んでみてください。
ポイント③社会復帰を急がない

うつ病のある人は、社会復帰をあまり急がないようにしましょう。
うつ病のある人の中には、休職中や無職の状態に後ろめたさを感じて、「早く復職しなければ」と焦る人が少なくありません。
しかし、その焦燥感は自分へのプレッシャーになって、うつ病の改善を妨げる可能性があるのです。
実際にうつ病の再発率は約60%もあるため、社会復帰に関しては慎重に考えるべきと言えます。(参考:こころの耳「職場復帰のガイダンス 働く方へ」)
ただ、経済的な事情から「焦らざるを得ない」という方もいるでしょう。
そのような場合は、うつ病のある人向けに経済的な支援を受けられる制度が複数ありますので、そちらを利用することをオススメします。
うつ病のある人が受けられる経済的な支援については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
うつ病のある人が利用できる支援機関5選
元の職場への復職や転職・再就職にあたって、以下のような不安もあるでしょう。
- うつ病のある自分は復職できるのだろうか…
- うつ病と言ったら雇ってもらえないのではないか…
そんなときは、この章で紹介する支援機関を利用してみてください。
より詳しい支援内容については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
また、再就職を成功させるコツや準備については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援機関①ハローワーク

ハローワーク(公共職業安定所)は、厚生労働省が全国500箇所以上に設置している総合的雇用サービス機関です。
就職や転職を希望する人に向けて、相談や職業の紹介などを行っています。
ハローワークには「障害者関連窓口」が設置されており、うつ病のある人もここでサービスを受けられます。
うつ病の特性をよく理解した専門の担当者がいるので、きめ細やかなカウンセリングが受けられるのです。
「精神障害者保健福祉手帳」を持っている場合は、障害者雇用枠の求人を紹介してもらえます。
まずは相談だけでもいいので、足を運んでみるといいですよ。
厚生労働省「全国ハローワークの所在案内」
支援機関②就労移行支援事業所
就労移行支援とは、「一般企業などへの就職を目指す、病気や障害のある方」向けに、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(通称:障害者総合支援法)」に基づいて行われる福祉サービスのことです。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
実際のサービスは、国の基準を満たした様々な「就労移行支援事業所」が行います。
就労移行支援事業所では、体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができます。
さらには、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
復職に向けて、基本的なビジネススキルを身につけたい人にオススメです。
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、うつ病の初期症状のある人のための就労移行支援事業所です。
- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月
新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。
支援機関③地域障害者職業センター

地域障害者職業センターでは、うつ病を含めて病気や障害のある人に対して、専門的な職業リハビリテーションサービスを提供しています。
ハローワークと連携しており、仕事に関する相談や訓練、復職するためのサポートを受けられます。
各都道府県に最低1箇所はあるため、ご興味があれば、お住まいの地域の施設を調べてみてください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」
支援機関④障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、障害者の身近な地域において、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う公的機関です。
令和5年4月時点で、全国に337箇所設置されています。
就業に関する相談支援や日常生活・地域生活に関する助言など、文字通り就労と生活の支援を受けられる施設です。
ハローワークや地域障害者職業センターなどと連携を取りながら、地域一体となってサポートしてくれますよ。
支援機関⑤転職エージェント

転職エージェントとは、転職の際に仕事を探してくれたり求人元と交渉をしてくれたりなど、いわゆる代理人のような役割を果たしてくれるサービスです。
うつ病をはじめとした病気・障害がある人向けの転職エージェントも存在し、障害者雇用に関する幅広い知識を持った担当者が対応してくれます。
うつ病のことを伝えれば、受け入れ体制が整った企業を紹介してくれたり、先方と相談をしてくれたりします。
実際に就職に向けて動くので、早く復職に向けて動きたい人にオススメです。
まとめ:うつ病は初期症状の段階で対処しましょう

うつ病は、初期症状を自覚しはじめた段階で対処することが大切です。
自分がうつ病になっていることを認めたくないと思う気持ちもあるかもしれませんが、やせ我慢を続けていると無理がたたって起きあがることすらできなくなる場合があるのです。
しかし、初期症状の段階でセルフケアをしたり、医療機関で診察を受けたり、周囲の人に頼ったりすることができれば、あらかじめ対策できるので安心してください。
このコラムが、仕事の場でうつ病の初期症状に悩んでいるあなたの助けになれば幸いです。
仕事の場面で見られる「うつ病の初期症状」にはどのようなものがありますか?
「物忘れやケアレスミスが多くなる」「同僚との会話を避けるようになる」「遅刻や欠勤が増える」「体調不良とは別にトイレ休憩などの離席が増える」などがあります。詳細はこちらをご覧ください。
勤務先で活用できるうつ病対策はありますか?
例として、「産業医面談」「ストレスチェック制度」「メンタルヘルス研修」があります。詳細はこちらをご覧ください。
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
執筆寺田淳平
てらだ・じゅんぺい。
高校2年の春から半年ほど不登校を経験。保健室登校をしながら卒業し、慶應義塾大学に入学。同大学卒業後の就職先(3,500人規模)で人事業務に従事する中、うつ病を発症し約10か月休職。寛解・職場復帰後、勤務を2年継続したのち現職のフリーライターに。
2019年に一般財団法人職業技能振興会の認定資格「企業中間管理職ケアストレスカウンセラー」を取得。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→