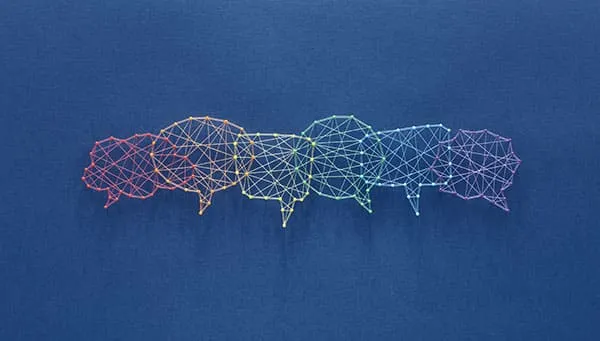うつ病で休職する人の確認事項7選 休職の手続きなどを体験談とあわせて解説

こんにちは、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジの寺田淳平です。
うつ病による休職をお考えのあなたは、以下の点に不安をお持ちではありませんか?
- 休職前に確認しておくべきことがわからない
- うつ病で休職するときの具体的な手続きは?
- うつ病での休職期間の目安はどれくらい?
- 休職中はどう過ごすべきなんだろう?
上記は、実際にうつ病で1年近い休職を経験した私が当時、抱いていた疑問です。
この記事では、うつ病で休職するときの7つの確認事項や休職するときの具体的な手続き、休職中の過ごし方を解説します。
あわせて、休職を経験したわたしの体験談をご紹介します。
3,500人規模の職場で人事を担当していた観点から、人事側のすべき対応や注意点についても解説しますので、休職される方だけでなく、休職予定の部下や同僚を持つ方もぜひ読んでみてください。
目次
うつ病で休職する人の確認事項7選
この章では、うつ病で休職するときの確認事項を、7つに分けてご紹介いたします。
休職に入る前に、前提として心に留めていただきたいことがあります。
それは、「あなた一人の判断で結論を出さずに、できる限り周りの人の意見を聞きながら、慎重に決断する」ということです。
ここで言う周りの人とは、かかりつけ医、ご家族、ご友人、支援者のことです。
私も経験のあることですが、うつ病で精神的に疲れているときは、理性や判断力が鈍っています。
諸々のやり取りを飛ばして休みたくなる気持ちはわかりますが、できる限り周囲の人へ相談する姿勢は持つようにしましょう。
前提:そもそも休職とは?

休職とは、「雇用契約を維持したまま労働を免除、または停止させる措置のこと」です。(参考:大阪府※PDF『33 休職と休業』、友常祐介『正しく知る 会社「うつ」の治し方・接し方』)
休職の認定を受けるには、労務に服せない理由が示された文書の提出など、いくつかの条件を満たす必要があります。
しかし、これらの条件はお勤め先によって異なります。
休職制度は法律ではなく、お勤め先の定める就業規定に則って適用されるからです。
具体的な休職の条件としては、以下の3つがよく見られます。
- 持病や疾患など、私傷病を理由とする本人の申し出がある
- 欠勤が○日以上継続する
- (私傷病の場合)休養を求める医師の診断書がある
上記の要件を満たしている場合、仮に本人が休職を拒否したとしても、お勤め先が休職を命じることもあります。
まずは、お勤め先の休職制度について人事部門に問い合わせるか、ご自身で就業規定を確認してみてください。
確認事項①専門医に相談する

休職前にはまず、「専門医に相談する」ようにしましょう。
特に「うつ病のような症状」があるだけで、実際に診断を受けていなかったり、「自分はうつ病かもしれない」と自己判断で済ませたりしている場合、まずはメンタルクリニックを受診してください。
伝えられる範囲で構いませんので、仕事の状況や精神状態を伝え、通院を続けながら治療に専念しましょう。
また、休職する際は基本的に「医師の診断書」が必要です。
診断書の発行までには、初診から数ヶ月かかる場合もありますので、休職をご検討中の方はなるべく早く受診するようにしてください。
メンタルクリニックへ通うことに抵抗があるという方は、お勤め先の「産業医」に相談するのもひとつの手段です。(参考:厚生労働省『産業医について』)
産業医とは、労働者の健康管理について助言や指導を行う医師のことです。
労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者が在籍する事業所に1人以上、3,000人超の事業所では2人以上の産業医の配置が義務付けられています。
上記の条件を満たしていれば、あなたのお勤め先にも産業医がいるはずです。
「産業医面談の内容次第では、人事考課に影響が出るのではないか」と心配される方もいらっしゃいますが、産業医は中立的な立場から診断を行いますので、ご安心ください。
もし、お勤め先が診断結果を求めても、個人情報保護の観点から、共有してよいかを原則ご本人に確認することになります。
また、産業医面談には料金なども発生しません。
休職をご検討の際は、まずはメンタルクリニックの専門医、産業医などに相談するようにしてください。
確認事項②就労支援機関に相談する

2点目は「就労支援機関に相談する」です。
専門医の診断からうつ病であることが明らかになり、その原因があなたの仕事の進め方や体調管理の方法にある場合、就労支援機関に相談することで、適切なアドバイスや指導を受けられます
また、近年ではうつの症状をきっかけにクリニックを受診したところ、発達障害であることが発覚したというケースも増えてきています。
就労支援機関の中には、発達障害の人を専門にフォローしているところもあります。
お勤め先とあなたの間に入って、業務量や勤務時間といった労務環境の調整をしているところもありますので、活用するとよいでしょう。
障害者総合支援法に基づいて福祉サービスを提供している「就労移行支援事業所」は、日常生活のアドバイスから仕事に役立つスキルの指導まで、最低0円からサービスを受けられますのでオススメです。
ただし、休職の手続きと同様に、就労移行支援を受けるためには「専門医による診断書」が必要になります。
就労移行支援にご興味のある方や、発達障害について詳しく知りたい方は、下記のコラムをご覧ください。
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、うつ病や発達障害などの人のための就労移行支援事業所です。
- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月
新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。
確認事項③就業規程の休職制度を確認する

確認事項の3点目は「就業規程の休職制度を確認する」です。
休職制度はお勤め先の就業規程に定められていますので、まずは規程を確認しましょう。
その際に注目してほしい確認事項が2点あります。
- 休職中の給与支給の有無
- 休職可能な期間
上の2点は、正規か非正規かなどの職位によって、条件が異なる場合があります。
職場によっては、職位次第で給与支給のないところもありますので、特に注意が必要でしょう。
仮に支給があっても、「6か月までは満額、それ以降は50%をカットする」などの制限が設けられている職場も少なくありません。
また、休職可能な期間も、半年間の職場から1年以上に渡る職場まで様々です。
確認する際には、ご自身で規程を検めるだけでなく、人事担当者に詳しく確認を取りましょう。
ちなみに、給与支給がない場合は、健康保険組合から傷病手当金を受け取れる場合があります。
就業規程だけではなく、健康保険組合にも問い合わせてみるとよいでしょう。
確認事項④貯金などの経済面を確認する

4点目は「貯金などの経済面を確認する」です。
うつ病で休職するときに経済的な余裕がないと、それが焦燥感や不安につながって、治療に専念できない場合があるため、必ず確認するようにしましょう。
ここで言う「経済面」とは、前項で述べた給与支給の有無や傷病手当金、毎月かかる治療代などです。
詳細は後で述べますが、人によっては労働災害による給付金も計算に入ってくるでしょう。
また、もし休職中に転職活動をすることになった場合、長期戦になることも見越して、貯蓄を見直すことも大切です。
ただし、「経済面で余裕がないと休職できない」と言っているわけではありません。
当座のお金が足りないのなら、家族・親戚・友人などから借りるなどという手段もありますし、市区町村役所では生活相談も受け付けています。
優先すべきはあなたの心身の状態です。
うつ病は放っておいて回復するものではなく、適切な治療によって回復します。
経済的に十分な余裕が取れなくても、すぐに休職を取った方がよい場合があるということを忘れないようにしましょう。
うつ病の人への経済的な支援については、下記コラムに書いています。よろしければご覧ください。
確認事項⑤家族に連絡・相談する

休職の前には「家族に連絡・相談する」ようにしてください。
実際に休職に入ると、休養のために、日中を家で過ごすことが増えてきます。
当然、ご家族は何があったのかを心配しますし、場合によっては状況を詳しく問われて、あなた自身が疲弊するという事態にもなりかねません。
こうした状況を避けるためにも、休職前は必ずご家族に連絡・相談するようにしましょう。
実家の家族と別居している場合も、念のために伝えておいた方がよいでしょう。
ただし、家族仲が極端に悪いような場合は、医者や他の支援者などに「家族との関係をどうするか」を確認してから方針を決めましょう。
確認事項⑥労災の申請が可能かを考える

うつ病になった明確な原因が職場にある場合は、「労災の申請が可能かを考える」必要があります。(参考:厚生労働省『労働災害が発生したとき』、労働問題弁護士ナビ『うつ病の労災が認められにくい理由と申請手続きの手順・流れを詳しく解説』、厚生労働省『精神障害の労災補償状況』)
労災とは、労働によって生じたケガや病気を指す「労働災害」の略称です。
労災を申請して認定されれば、労災保険による治療費などの補償を受けることができます。
ここで言う「うつ病になった明確な原因」とは、過度な長時間労働や、ハラスメントのことです。
昨今、職場でのハラスメントや長時間の残務がきっかけとなって、うつ病などの精神障害を発症する人が後を絶ちません。
過労死など、精神障害による「労働災害」の民間企業での認定件数は、2017年の506件をピークに依然として横ばい傾向が続いています。(参考:厚生労働省『令和元年版過労死等防止対策白書』)

上述したデータはあくまでも労働災害として「公に」認められたものだけです。
労働によるストレスが原因でうつ病にかかった人の総数は、実際にはこれよりも遥かに多いでしょう。
ただし、一般論として、うつ病などの精神障害による労災認定は、非常に難しいと言われています。
というのも、うつ病の原因を特定することは難しく、「私生活を含む様々な要因が複合的に絡みあって発症するケース」が多いからです。
また、発病前の約6か月間に、業務による極度の心理的負荷が認められるなど、原因が職場にあることを明確化するための条件設定が厳しいというのが現状です。
しかし、認定されるかどうかに関わらず、状況次第では申請すること自体は可能です。
労災の申請が可能かどうかを担当部署に確認してみてもよいでしょう。
確認事項⑦職場との連絡手段や頻度を考える

最後に意外と忘れられがちなのが、「職場との連絡手段を決める」ことです。
うつ病の場合、電話に出たくなかったり、メールをしたくなかったりと、連絡すること自体が大変になります。
そのため、休職に入ってからの連絡手段や頻度を、あらかじめ考えておきましょう。
職場との連絡手段が定まっていれば、休職中に気がかりなことがあっても安心できます。
また、病状を報告するタイミングを決めておけば、職場からの不定期な連絡を受けずに済むでしょう。
通院や診断書の有効期限が切れるタイミングで、受診結果の報告をするのが一般的です。
「あなたが連絡しやすい手段」と「どのくらいの頻度で連絡するか」を考えておいてください。
うつ病で休職するときの具体的な手続き4点

ここからは、うつ病で休職する際の一般的な手続きについて、お話しします。
休職する際の手続きは、主に以下の4つに分かれます。
- 専門医による診断書の発行
- 上司との面談
- 人事担当者との面談
- 休職申請書類の提出
休職する際には「専門医が発行する診断書」が必要ですますので、まずはかかりつけの病院やクリニックに相談してください。
診断書が発行されたら、基本的には所属する部署の上司に面談のアポイントメントを取り、診断書を提示しながら、「うつ病により療養の必要がある」ということを伝えましょう(具体的な相談先は、お勤め先や個人の事情によって異なります)。
このとき、休職者が多い職場は別として、普段は淡々とお仕事を進めていた方や、気丈に振る舞われていた方は、上司から多少驚かれるかもしれません。
上司との面談は精神的にエネルギーが必要なところかと思いますので、ご自身の調子を考慮して、アポイントメントを取るとよいでしょう。
面談の前に数日、休暇を取るなどして、それとなく療養が必要なことを匂わせておくという手段もあります。
いずれにせよ、診断書には相応の効力がありますので、基本的には休職が認められるはずです。
通常であれば、この後に人事担当者との面談が行われます。
このときに上司が同伴するかどうかは、あなたの判断によることが多いです。
特に、うつ病の原因が、明らかなハラスメントなどにある場合は、配慮してもらえるでしょう。
場合によっては、休職に代わる選択肢として、異動の打診が行われたり、労働災害の申請について説明されたりします。
その後、原則的には、職場の書式に則って休職の申請書類を提出し、手続きが完了するはずです。
ただし、担当業務によっては、休職までの間に最低限の引継ぎを頼まれると思いますので、無理のない範囲で遂行してください。
うつ病による休職中の過ごし方:4つのQ&Aから解説
休職中のよくある休職中の過ごし方に関する悩みをQ&A形式で紹介いたします。
ここに挙げるものは、私自身が休職中に感じたことでもあります。
悩みと併せて、対処法やオススメしたい考え方も解説しますので、ぜひご覧ください。(参考:五十嵐良雄『うつ病・躁うつ病で「休職」「復職」した人の気持ちがわかる本』、松﨑博光『新版 マジメすぎて、苦しい人たち:私も、適応障害かもしれない…』)
Q1.休職中は何をすべきですか?

休職中は何をすべきかを考える前に、前提としてお伝えしておきたいことがあります。
それは、あなたの判断で通院や服薬をやめない、ということです。
調子が良くなってくると、「もう病院に行く必要はない」と自分で判断する人がいます。
しかし、回復していたとしても、それは継続的な薬の服用の結果であったり、医師の目から見ればまだ休養が必要であったりという場合が多いのです。
そのため、休職中は通院を続けて、その上で元気が出てきたら、医師と相談の上で「何をすべきか」を考えるようにしましょう。
休職中にしておくとよい行動として、ここでは以下の4つを挙げさせていただきます。
- 生活リズムを整える
- 自分なりのリラックスの仕方を覚える
- どこかへ通う習慣をつける
- 適度に運動する
うつ病で休職した初期は、日中も横になって過ごすことが多いかと思います。
回復してきたら、まずは生活リズムを整えることから始めましょう。
その際には、「どこかへ通う習慣をつける」や「適度に運動する」というのが有効です。
日中に外出して日光を浴びることで、体内時計が整うはずです。
また、瞑想やアロマテラピーをしたり、長めにお風呂に入ったりといった「自分なりのリラックスの仕方を覚える」ことは、うつ病の回復だけでなく、その後の予防にもつながります。
Q2.休職中に旅行してもいいでしょうか?

休職中に、「リフレッシュのために旅行したい」という人は多いです。
特に、うつ病の原因が職場環境との不適応にある「適応障害」の人は、仕事を休み始めたら元気になる場合が多いと言われています。
しかし、元気になったからと言って、すぐに旅行に出ることはオススメできません。
回復したと感じても、疲労が残っている場合があるからです。
旅行へ出たいという方は、まずは主治医に相談をして、診断を仰ぐようにしましょう。
その上で、旅行が療養に有効(回復の邪魔をしない)であれば問題ありません。
とはいえ、旅行へ行ったとしても、同僚の目に触れるSNSなどに写真を載せる行為はしないようにしましょう。
人によっては気分を損ねて、その後の人間関係に影響が出てることもあります。
現職への復職を視野に入れている方は、特に注意してください。
Q3.休職期間の目安は?

厚生労働省の調査によると、うつ病などの精神疾患によって休養した労働者は、職場復帰までに平均「107日(約3.5か月)」かかるという結果が出ています。
しかし、これはあくまでも平均日数です。
うつ病から復帰するまでにかかる時間は、人によって異なります。
もし平均日数を越えたとしても、焦らずに休養に励んでください。
というのも、うつ病などで休職した人が再休職する割合は、「5年で47.1%」と半数近くにものぼるのです。(参考:厚生労働省『平成28年度労災疾病臨床研究事業費補助金研究報告書』)
2度目の休職では、復帰までに「平均157日」かかるなど、1度目のときより時間がかかるため、焦らずに治療を進めることが大切になります。
どうしても気持ちが焦ることもあるかと思いますが、平均日数はあくまで目安として考え、ご自身の復帰については、必ずかかりつけ医の診断に従うようにしてください。
なお、うつからの復職については、下記コラムにまとめてあります。ご参照ください。
Q4.休職中に利用できる支援機関はありますか?

休職中に利用できる支援機関は多数あります。(参考:東京都『東京都発達障害者福祉センター(TOSCA)』、厚生労働省『精神保健福祉センターと保健所』、東京都福祉保健局『よくある相談事例|東京都立精神保健福祉センター』、厚生労働省『サポステ|地域若者サポートステーション』)
前述した「就労移行支援事業所」は、メンタル面のケアだけでなく、復帰までの支援を得ながら、自身のスキルアップも目指せますのでオススメです
就労移行支援事業所の詳細は、下記コラムをご覧ください。
就労移行支援を利用するための条件は、以下の3つになります。
- 原則18歳から65歳未満であること
- 一般企業への就職または仕事での独立を希望していること
- 精神障害、発達障害、身体障害、知的障害や難病を抱えていること
就労移行支援事業所では、診断書の提出が必要になりますが、診断書がなくても支援を受けられる機関はあります。
例えば、発達障害についての相談に特化している「発達障害者支援センター」では、発達障害の診断が下っていない、いわゆる「グレーゾーン」であっても相談が可能です。
また、臨床心理士に相談ができる「精神保健福祉センター」でも、あなたの状態に応じたアドバイスを受けられるでしょう。
その他、15歳~39歳までの「若者」を対象としている「地域若者サポートステーション(通称:サポステ)」でも就労の悩みを受け付けています。
基本的には、都道府県が設置しているものになりますので、どの支援センターに行ったらよいかわからないという方は、一度、お住まいの地域の役所に問い合わせてみるとよいでしょう。
うつ病による休職を経験したわたしの体験談

ここでは実際にうつ病による休職を経験した、私の体験談をお話します。
私の場合、繁忙期を耐え抜いた後の「燃え尽き症候群」がきっかけとなり、うつ病になりました。
繁忙期の末期になって気を緩めた途端に、どっと疲れが出て、ベッドから起き上がれなくなったのです。
それまでも「出勤がつらい」と思うことはあったものの、「これくらいは他の人でもある」と思っていました。
しかし、繁忙期が終わって張り詰めた糸が切れたことで、本格的に抑うつ症状が現れるようになったのです。
ひとまず休みを取って、メンタルクリニックに通ったところ、抑うつの診断が下りました。
とはいえ、すぐに休職の診断書が出るわけではなかったため、数日は休暇を挟みながら出勤を続けました。
この段階で、同僚は私の様子がおかしいことに気づいていたようです。

まもなく診断書が下りたため、上司と面談をしましたが、そのときに「休職を取った方がよいのではないかと思っていた」と言われました。
それからは、人事部の担当者と面談をして、休職に入りました。
休職の初期は、日中もベッドに横たわって、眠っていることが多かったです。
その後は、「生活リズムを整えること」と「体力を維持すること」の2点を念頭に置きつつ、自分のやりたいことをしていました。
回復してきたとはいえ、職場復帰への恐さをなかなか拭うことはできず、私の場合は何度も主治医や上司、人事担当者との面談を重ねて、休職期間が長引きました。
しかし、最終的には現職に留まることを選択しました。
「当時の勤め先が、基本的には、自分の性格に合致していると感じていたこと」「業務内容が合わないだけで、異動の提案もすでに受けていたこと」が、現職に留まった理由です。
その後は、自分に合ったリラックスの仕方や仕事術を実践し、気持ちよく働くことができました。
現在は、当時のうつ病とは全く別の理由で転職し、次のステップへとキャリアを進めています。
うつ病で休職中の部下がいるときの人事の対応4点
この章では視点を変えて、うつ病の休職中の部下をお持ちの方向けに、人事的な対応について解説しておきます。(参考:中村美奈子『復職支援ハンドブック―休職を成長につなげよう』、亀田高志『改訂版 人事担当者のためのメンタルヘルス復職支援』)
休職中の人の中には、自分がまだ職場復帰できる状態にないのに、焦りから「復帰できる」と思っている場合があります。
そのようなときに、部下の調子を適切に判断し、フォローアップができるかどうかで、その後の職場定着が大きく変わってくるのです。
「今後復職したらどのような対応をされるのか」と不安に思っている休職中の方も、併せてお読みいただければ幸いです。
対応①休職者の不安を理解する

まずは「休職者の不安を理解する」ことから始めましょう。
「休職者が何を不安に思っているか」をしっかりヒアリングすることが重要になります。
主に、以下の点を確認してください。
- どの業務がつらかったのか
- 業務量に問題はなかったか
- 人間関係に問題はなかったか
特に、業務内容と業務量については、念入りに聴くようにしましょう。
ただし、休職前であれ、休職中であれ、「いつになったら復職できそうか」という質問をするのは厳禁です。
休職者に焦りを生じさせたり、休んでいることに罪悪感を感じさせたりする可能性があります。
また、休職中に職場の人員が替わっている場合は、そのことを休職者は知らないため、現在の職場の状況を併せて伝えるとよいでしょう。
休職者を理解するとともに、その不安を軽減することに努めましょう。
対応②就業規程をわかりやすく説明する

「就業規程をわかりやすく説明する」というのも大切な対応です。
基本的に就業規程は、どの従業員でも見られるように、社内のネットワークなどで公開されていると思います。
しかし、規程に関わらない部門の人は、就業規定を読み込んでいないことがほとんどです。
上司や人事からの説明を当てにしている場合が多いため、内容をわかりやすく説明する技術が求められます。
休職者へ説明をする際は、人事部門内で当たり前に使っている用語、基本事項を、休職者はほとんど知らないということを想定しましょう。
そして、休職者が内容を理解しているか、説明をしている途中でも、都度確認をしましょう。
休職者の年次によっては、新卒や中途採用の人向けに解説するつもりで接した方がいい場合もあります。
なお、休職した側の意見になりますが、「もし休職可能な期間を過ぎた後は、どうすればよいか」など、規程の説明が丁寧だと、「頑張って復帰しよう」という気持ちになります。
私の場合は、休職したときの年齢がまだ若かったこともあり、上司が経済的な面まで相談に乗ってくれるなど、親身になって接してくれました。
このときに、いい加減に扱われていたら、「この企業は人を使い捨てにするかもしれない」「復職してもフォローがないかもしれない」と、すぐに離職につながっていたかもしれません。
当然、補充要員の採用にかかる手間や研修費用を考えれば、離職は避けるべきかと思います。
誠実さが休職者へ伝わるように、規程の説明はきちんとするようにしましょう。
対応③復職可能な状態かを見極める

これは休職してある程度の期間が経ってからの対応になりますが、「復職可能な状態かを見極める」ことが特に重要です。
面談を行う際には、以下のような質問をしてみましょう。
- 復職に関して医師はどう言っているか
- 生活リズムは安定してきているか
- 日中はどう過ごしているか
- 症状はどの程度緩和されているか
- 支援者やご家族も復帰に前向きか
ただし、日中の過ごし方などを深掘りすることは、プライベートな内容を追及することにもなるため、注意してください。
また、質問をする際には、できるだけ緊張感を和らげるように意識して話しかけてください。
その際には、「人慣れしていない感じが過度に表れていないか」も確認するとよいでしょう。
職場復帰をすると、人とコミュニケーションをする機会が増えます。
そうしたときに、十分なコミュニケーションが取れる程度まで回復していないと、ストレスを抱えて再休職する可能性があります。
面談がコミュニケーション感覚を取りもどすリハビリになることもありますので、無理のない範囲で様々な質問を投げかけて、休職者の様子を伺ってみてください。
対応④異動や短時間勤務を提案する

4番目は「短時間勤務や配置転換を提案する」です。
休職中の人の中には、ご自身の口から短時間勤務や異動の話を切り出せる人もいますが、申し訳なくてうまく希望できないという人もいます。
そのため、職場側から提案するというのもひとつの手段です。
適応障害などは、環境がマッチするだけで格段にパフォーマンスが上がる場合もあります。(参考:厚生労働省「適応障害|病名から知る|こころの病気を知る(リンク失効)」)
もちろん、異動という話になれば、受け入れ先などの調整が必要になります。
しかし、短時間勤務や異動は、離職を防ぐ意味でも効果的ですので、職場側からの提案も考慮に入れるとよいでしょう。
まとめ:確認事項をチェックして休職に専念しましょう

うつ病で休職する際の確認事項から、手続き、人事の対応までを詳しく解説してきましたが、役に立ちそうな情報はありましたか?
大切なのは、あなたひとりの自己判断で決めるのではなく、周囲の人や専門家を適切に頼ることです。
うつ病だと人と接するのもつらいかもしれませんが、ここで人に頼ることを覚えると、その後の回復状況も変わってくるかと思います。
ぜひ一人で抱え込まずに、周囲の人に相談してみてください。
このコラムがうつ病による休職で悩んでいる方の助けになれば幸いです。
うつ病で休職する前後に、確認しておくべきことはありますか?
一般論として、次の7つをオススメします。「専門医に相談する」「就労支援機関に相談する」「就業規程の休職制度を確認する」「貯金などの経済面を確認する」「家族に連絡・相談する」「労災の申請が可能かを考える」「職場との連絡手段や頻度を考える」詳細はこちらをご覧ください。
うつ病での休職中には、何をするべきですか?
一般論として、次の4つをオススメします。「生活リズムを整える」「自分なりのリラックスの仕方を覚える」「どこかへ通う習慣をつける」「適度に運動する」。詳細はこちらをご覧ください。
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
執筆寺田淳平
てらだ・じゅんぺい。
高校2年の春から半年ほど不登校を経験。保健室登校をしながら卒業し、慶應義塾大学に入学。同大学卒業後の就職先(3,500人規模)で人事業務に従事する中、うつ病を発症し約10か月休職。寛解・職場復帰後、勤務を2年継続したのち現職のフリーライターに。
2019年に一般財団法人職業技能振興会の認定資格「企業中間管理職ケアストレスカウンセラー」を取得。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→