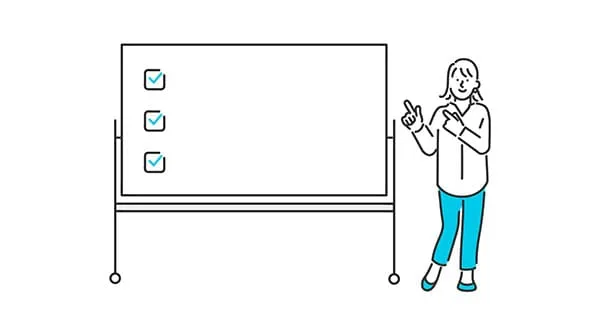うつ病で退職する人が失業保険を受給する方法 受給までの流れやその他の経済的支援制度を解説
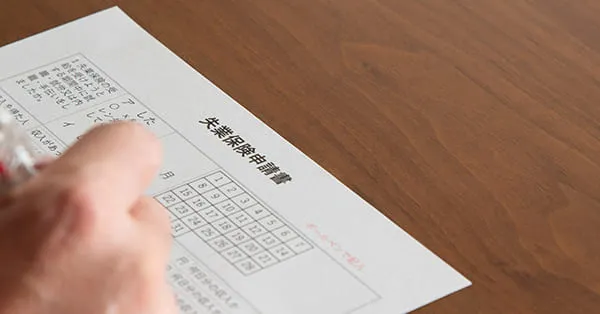
うつ病に関連して退職するときにまず不安になるのが、生活費や治療費などのお金のことでしょう。
この記事では、うつ病で退職する人が生活費や治療費などの支えとなる「失業保険」の概要や受給する方法、受給金額や条件、申請から受給までの流れ、失業保険対象者の種類、うつ病で退職するときの流れ、うつ病の人が利用できるその他の経済的支援制度、「傷病手当金」や「障害年金」との違いについて詳しく解説します。
経済的支援を利用することは、決して恥ずかしいことではありません。
支援を利用しつつ、しっかり休養・治療することが、うつ病からの回復(またはその後の再就職など)には欠かせません。
この記事を参考に失業保険などの支援制度について知っていただけると幸いです。
目次
はじめに:うつ病で退職する人への支援は失業保険以外にもたくさんあります
前提として、うつ病を理由に退職した人も、失業保険(失業手当)などの支援制度を利用できます。
この記事を「失業保険も含めて、『うつ病の失職者』をサポートする仕組みはたくさんある」という安心材料にしてください。
その上で、「実際のあなた」がどのようなサポートを利用できるのかは、医師に尋ねたり、サポート団体などを利用したりすることで、具体的に見えてくると思います。
もちろん失業保険の仕組みは、複雑な部分もあります。後で紹介するように、退職の理由やうつ病の状態などによって受給期間を延長できたり、「今すぐには」受給ができなかったりすることもあります。
また、各種制度は随時改定・改正が行われます(この記事でも、「うつ病と失業保険の全て」をお伝えできるわけではありません)。
「実際のあなた」と照らし合わせて、検討してみてください。
失業保険の詳細や受給方法について知りたい人は、こちらの章からご覧ください。
失業保険以外の経済的支援制度やサポート団体については、以下のコラムも併せてお読みください。
うつ病で退職する人が失業保険を受給する方法
失業保険は、「体調的には今すぐに働ける状態にあり、求職活動もしているけれど、失業状態の人」が利用できます。
そして、うつ病がある人が「今すぐ働けるかどうか」は、個別の状況によって(医師の判断によって)異なります。
前提:うつ病は、失業保険の対象とならないことがある
うつ病で今すぐ働けない人は、「病気やケガですぐに働けない人」に当てはまり、失業保険を受給できない可能性があります。
「うつ病がありつつ、失業保険を受給したい人」は、自分がすぐに仕事ができる状態かどうか、医師に相談して考えておく必要があります。(状態によっては、うつ病があっても働くことが可能です)
ただし、今すぐ働けない人でも、後述する「期限延長」をしたり「就職困難者」に認定されたりした場合は、失業保険を利用できることがあります。
失業保険は働ける状態になれば改めて申請できます。また、うつ病の人への金銭的なサポートは失業保険以外にもあります。
「失業保険を受給できなさそう」だからといって、不安にならないようにしましょう。
失業保険の詳細や受給方法について知りたい人は、こちらの章からご覧ください。
今すぐ働ける場合

「今すぐ働ける人」は、ハローワークで手続きを行い、求職活動を行うことで、失業保険を受給できます。
また、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」と認められた場合は、2か月間の給付制限期間なしに受給できます。
失業保険の詳細や受給方法について知りたい人は、こちらの章からご覧ください。
今すぐ働けない場合
改めて、うつ病で今すぐ働けない人は、失業保険を受給できない可能性があります。
「今すぐ働けない人」は、以下のような方法を考えましょう。
- 失業保険以外の経済的支援制度を検討する
- 失業保険の「受給期限」の延長手続きを行う
- 「就職困難者」の認定を検討する
失業保険以外の支援制度については、こちらの章から詳しくご紹介します。
また、「今すぐ働ける場合」でも、うつ病や失業に関連して受給できるお金や利用できるサービスがあるなら併用をオススメします。
うつ病で退職するときの流れ
うつ病で退職するときの一般的な流れを説明します。
より詳細な、うつ病が関係する退職の前後に行った方がよいことは、下記コラムをご覧ください。
まだ退職(を決意)していないなら、参考としてご覧ください。
先にお伝えしますと、うつ病のときには、判断力などが衰えています。退職についてあなた一人で決断するのではなく、主治医、上司、人事部、サポート団体などによく相談しながら準備をしましょう。
①病院での診断受診

まだうつ病の診断が出ていない段階であれば、病院に行って診察を受けましょう。
インターネットなどにはうつ病の自己診断チェックシートなどもありますが、「ある人が、本当にうつ病かどうか」診断できるのは医師だけです。
実際にうつ病だったときには、各種支援の手続きなどのために、うつ病の診断書が必要な場合もあります。
うつ病と似た病気に、適応障害などがあります。病気によって治療法も異なりますので、「病気かもしれない」と思ったときには、病院で適切な治療を受けることが大切です。
②有給取得や傷病手当金の受給を検討
退職を決意する前に、有給休暇で療養するか、休職して傷病手当金を受け取ることはできないか(=退職せずに、お金を受け取りながら休養できる可能性はないか)を考えましょう。
「病気休暇」という、病気療養のための休暇を取得できる職場もあります。お勤め先の制度を確認することをオススメします。
③退職意向の会社への表明(退職届の提出)

主治医・人事部・上司などにも相談しつつ、退職を決意したら、退職届を作成・提出しましょう。
退職届は、お勤め先にフォーマットがあればそれを利用したり、ネットで見つけた一般的な様式を利用したりしましょう。
退職理由は、「一身上の理由」で問題ありません。(うつ病と関連づける必要はありません)
ただし前述のように、特定受給資格者や特定理由離職者に該当すると思われる場合は、退職届もそのように作成しましょう。
退職届の提出時期としては、「退職日の2週間前から1か月前まで」と就業規則で決められているケースが多いようです。実際のあなたの職場がどうなのかは、事前に確認しておきましょう。
退職届を提出しても、「代わりの社員がいない」「業務の引き継ぎに時間がかかる」などでなかなか退職を許可されない(引き止められる)ケースもないわけではありません。
うつ病の症状がある状態で、あなた一人で引き止め交渉を行うのは大変な場合もあるでしょう。医師、うつ病の人をサポートする団体、法テラス、労働基準監督署などへの相談もオススメします。
④退職後の保険切り替えと離職票の準備
退職後には「健康保険」と「年金」の切り替えなどが必要です。
(1)健康保険
正規雇用の人が退職すると、それまでの健康保険が使えなくなるので、以下の3つのうちのどれかの手続きが必要です。
手続きは、お住まいの市区町村の健康保険担当窓口で行います。
- 国民健康保険に切り替える
- 家族の健康保険の扶養者になる
- 社会保険の任意継続を申請する
(2)年金
正規雇用の人は、厚生年金から国民年金に切り替えましょう。
手続きは、お住まいの市区町村役所の国民年金担当窓口で行うことができます。
(3)離職票
職場に、離職票の発行を依頼しましょう(退職前の依頼も可能です)。失業保険の給付を受ける際に必要な書類です。
⑤ハローワークでの失業保険手続き

失業保険は、お住まいの地域を管轄するハローワークに行って手続きをすることで、受給可能になります。退職後は、できるだけ早くハローワークに行って、諸々の手続きを行いましょう。ハローワークの全国一覧はこちらです。(管轄は、インターネットでの「○○市 ハローワーク」などの検索でも見つかります。
また、傷病手当金や障害年金など他の支援制度を利用したい場合は、それぞれの窓口に行って必要な手続きをしましょう。
⑥医師の指示に基づく治療と休養
すべての手続きが終わったら、医師の指示に従って治療・休養に専念しましょう。今は苦しいかもしれませんが、体調が回復してきたら、再就職に向けても動き出せるようになります。
改めて、失業保険とは?:受給金額や条件を解説
この章では、「失業保険(失業手当)」について概要から受給期間や条件まで詳しくご紹介します。
厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」
①失業保険の概要

失業保険(正式名称:雇用保険)とは、「雇用保険加入者で、失業・退職した人」が、安定した生活を送りながら一日でも早く再就職するための支援として給付される公的な支援金です。
雇用保険に加入していても、失業・退職したら「すぐに」受給できるとは限りません。また、人によって受給開始日や受給可能期間が異なります。
公務員や自営業の場合は「雇用保険」に加入していないので、失業・退職・廃業しても失業保険の対象とはなりません。ただし、公務員には失業保険に相当するサポートがありますし、職種に関係のないうつ病のサポートももちろんあります(ご興味のある公務員の人は「公務員 失業保険相当」などとネット検索してみてください。その他、うつ病のサポート制度については、下記コラムをご覧ください)。
②失業保険の受給金額

失業保険で受給できる金額(基本手当)は、ハローワークに提出する離職票に基づいて、以下のように計算します。
(離職前6か月の給与の総支給額の合計÷180)×給付率
給与の総支給額とは、保険料等が控除される前の金額で、残業代や賞与は除きます。
給付率とは「およそ50~80%」で、賃金の低かった人ほど高い率となっています(60歳~64歳については、45~80%です)。
平均して月額15万円程度の給与だった場合、支給額は月額11万円程度
平均して月額20万円程度の給与だった場合、支給額は月額13.5万円程度
上限額について、失業保険で受給できる金額は、年齢によって上限額があります。下記は、令和4年8月1日現在の、1日あたりの上限額です。
- 30歳未満:6,835円
- 30歳以上45歳未満:7,595円
- 45歳以上60歳未満:8,355円
- 60歳以上65歳未満:7,177円
なお、65歳以上の人が失業した場合には、「失業保険の基本手当」ではなく「高年齢求職者給付金」が支給されます。年金と併用して受給することも可能です。
③失業保険の受給条件

失業保険は、基本的に「離職状態にあり、今すぐ働く意思があるが、仕事を見つけられない人」が受給できます。
例えば、以下のような人が対象です。
- 積極的に就職しようとする意思があること
- いつでも就職できる健康状態や環境などであること
- 積極的に仕事を探しているにも関わらず、現在職業に就いていないこと
ですので逆に、例えば次のような場合は、受給することができません。
- 妊娠・出産・育児・病気・ケガなどのために、すぐに就職できない人
- 就職するつもりがない人
- 家事に専念している、学業に専念している、会社などの役員に就任しているなどの人
- 自営業の人
④失業保険の相談先
失業保険の相談先は、ハローワークです。
⑤雇用保険の加入状況の確認方法

ご自分が雇用保険に加入しているかどうかは、一般的には「給与明細に雇用保険の名目で控除があれば、加入している」と判断できます。逆に、控除がなければ加入していません。
ごく一部ではありますが、例外的に「雇用保険名目の控除があるけれど、実際には加入していない」という、いわゆる「ブラック企業」がないわけではありません。気になる人は、ハローワークにご確認ください。ハローワークには、「雇用保険の被保険者資格取得の届出が適正になされているか否かの確認を労働者自らが照会できる仕組み」があります。
⑥失業保険の受給期間
失業保険を受給できる期間は、「離職した翌日から1年間」です。
ただし、申請したらすぐに受給できるわけではなく、また、1年間ずっと受給できるわけではありません。「受給できる日数(給付日数)」は、勤続年数などによって変わります。
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者(後述)の所定給付日数は、120日です。退職後にすぐに申し込み、申請が認定されれば、1年間の受給期間のうちの120日間分受給できます。
申請が大幅に遅れた場合、「本当ならば120日間受給できたはずなのに、申請が遅れた結果、受給開始から50日目に『退職からの1年』が経過するので、50日分しか受給できない」などの事態もありえます。
受給開始までに数か月(給付制限期間)を要することもあります。受給を考えている人は、早めにハローワークに行きましょう。
失業保険の申請から受給までの流れ

失業保険は、次のような流れで申請・受給します。
(参考:ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」)
- 離職票を用意する(※1)
- ハローワークで申請手続きをする
- 7日間(待期期間)と2か月(給付制限期間)の経過を待つ (※2)
- ハローワークの給付説明会に行く
- ハローワークで、決められた回数の求職活動をする(※3)
- 失業の認定を受ける(※4)
- 口座に給付金が振り込まれる
(※1)旧勤務先に、離職票を発行してもらいます。勤務先によっては、発行に時間がかかることもあるので早めに準備しましょう。
(※2)7日間の待機期間中は、アルバイトも禁止されています。
(※3)失業保険は「働く意思があること」が前提になっているので、決められた回数、「ハローワークでの」求職活動をする必要があります。転職サイトなどでの求職活動がメインの場合は、実際にはハローワークでは「形だけ」の求職活動になることも珍しくないようです。
(※4)現実として失業状態が続いている場合でも、継続して受給するためには、失業の認定を原則として4週間に一度受ける必要があります
失業保険対象者の種類
失業保険の対象者は、退職の状況によって、「①自己都合退職者」「②特定理由離職者」「③特定受給資格者」3つの種類に分けられます。
「うつ病の人の退職」は、基本的には①に該当します。
個別の状況やハローワークの判断によっては②③となることがあるようです。
種類①自己都合退職者
自己都合退職者とは、病気や転職などの自己都合の理由で退職した人です。
退職時に「一身上の理由」と書くとこちらに分類されます。
種類②・特定理由離職者
特定理由離職者とは、自分の意思に反する正当な理由(健康上の理由、出産育児、介護、家庭の都合など)があって退職する場合はこちらに当てはまります。
定年後、休養してから働きたい人もこちらに含まれます。
種類③特定受給資格者
特定受給資格者とは、いわゆる「会社都合退職」です。
企業の倒産や解雇など、勤め先の都合によって離職を余儀なくされた人が当てはまります。
長時間労働やパワハラが原因でうつ病になって退職を余儀なくされた人は、このケースに認定されることがあります。
自己都合退職者・特定理由離職者・特定受給資格者の違い
各退職の分類によって、失業手当の受給などは次のように変わります。
失業手当を受給できるのは、ハローワークに行った日から7日間の手続き期間後、さらに2か月の給付制限期間が過ぎてからです。制限期間は、以前は3か月でしたが、2022年10月以降の退職者から2か月に変更になりました。
自己都合退職者だけでなく、自分に責任があって辞める場合(過失が原因で退職など)の場合も、2か月の給付制限期間が設けられます。
失業手当は、7日間の手続期間後に受給できます。待機期間の2か月がありません。とはいえ、実際には、「7日が過ぎたらすぐに受給」ではないようです。「求職の実績を積む」などの期間が少し必要なようで、申請・認定からおおむね1か月後くらいから受給可能だと考えておきましょう。
特定受給資格者と「一部」の特定理由離職者は、給付日数が多くなる可能性がある
失業手当の受給可能期間も、次のように異なります。
自己都合退職
90〜150日
特定受給資格者・「一部の」特定理由離職者
90〜330日(年齢によって異なります)
つまり、特定受給資格者・特定理由離職者は、失業手当金をより長い期間受給できるということです。
ただし、「特定理由離職者」には、「一部の」という条件がつきます。(「会社に契約更新を拒まれた人」に限られます)。退職の理由がうつ病に限られる場合は、自己都合退職者と同じ期間になります
制度改正による変更などの可能性を考慮して、このページでは詳細は省略します。ご興味がある人は、ハローワークのウェブサイト「基本手当の所定給付日数」をご覧ください。
「特別理由離職者」は受給期限を延長できる
失業保険を申請・受給できる期限は、「失業・退職から1年間の間」です。(受給可能期間は、1年間丸ごとではなく、90〜360日間です)
「特別理由離職者」は、申請期限を最長3年間延長することができます=最長で4年(1年+3年)になります。
これはどういうことかというと、「最初は治療に専念して、4年以内に働ける状態になったら、ハローワークに失業保険を申し込むことができる」ということです。
受給期限延長にはハローワークへの手続きが必要ですので、気になる人は確認してみましょう。手続きは、窓口に行かなくても「郵送」や「代理人」で申し込むこともできます。
うつ病の程度によって、「就職困難者」に認定されることもある
うつ病の程度が重く、将来的にも就労に障害がありそうな人は、「就職困難者」に認定されることがあります。
「就職困難者」は、失業保険について以下のように優遇されることがあります。
- 2か月の受給制限期間がない
- 受給日数が長くなる(区分は、年齢と被保険者であった期間によって、150日、300日、360日)
「就職困難者」に認定されるためには、障害者手帳を持っていることが条件です。また、あくまで「困難者」なので、全く求職できない人、する意志のない人は対象にはなりません。
長時間労働やパワハラでうつ病になり会社を辞める場合

前述のとおり、ブラックな長時間労働やパワハラなどが原因でうつ病になって離職する場合は、「会社都合の退職となる」=「特定受給資格者に認定される」場合があります。
特定受給資格者となると、失業保険の受給開始時期が早くなる、受給日数が多くなるなどの優遇を受けることができます。
「該当する」と思うようであれば、退職前にパワハラがあることを勤務先に伝え、会社都合の退職にする必要があります。
ただし、そういう訴えをしづらかったり、訴えても真面目に受け止められなかったり、早く辞めたくて自己都合で辞めたり、というケースはよくある話でしょう。そのような場合でも、後からハローワークに相談して、退職理由を会社都合に変更できる可能性があります。
その上で、勤務先が長時間労働やパワハラを認めず、裁判などで争わなくてはならないケースもあります。必要に応じて、事前に弁護士などにも相談しましょう。労災認定を受けた場合は、労災保険や慰謝料を受け取れる可能性もあります。
うつ病がありつつ、(元)勤務先と(法的に)争うことは、大変だと思います。「実際のあなた」が「実際にどうするか」は、体調を見つつ、サポート団体などとも話し合いつつ、検討していきましょう。
(特定受給資格者に今すぐにはなれなくても、失業保険以外の手当を受給したり、勤め先への訴えは体調がよくなってから行ったりすることは可能です)
うつ病の人が利用できる失業保険以外の経済的支援制度9選

この章では、うつ病の人が利用できる、失業保険以外の経済的支援制度を9つ紹介します(状況によって、「必ず利用できる」とは限りません)。
うつ病で退職した人が受けられる経済的支援(お金を受給できる支援と、各種支払いが減免できる支援)は、失業保険(失業手当)だけではありません。
支援制度は他にもたくさんありますので、ご安心ください。
経済的支援を受けることは、恥ずかしいことではありません。支援を受けつつ、経済的に安心してうつ病の治療・休養に専念することで、仕事復帰・仕事探しも含めて「次の一歩」にも進みやすくなります。
支援制度①傷病手当金
傷病手当金とは、病気やケガのために仕事を休む場合に「健康保険」の被保険者とその家族を保障するための制度です(国民健康保険の加入者は対象外です)。
傷病手当金を受給する条件は「病気やケガによって労働不能であること」です(医師の診断書が必要です)。
つまり、傷病手当金は「退職前に受給するお金」ということです。ただし一定の条件を満たせば、退職後も継続して受給できます。
傷病手当金の窓口は、「全国健康保険協会、各健康保険組合、各共済組合」になります。
ご興味がある場合は、ご自身の加入している健康保険に問い合わせてみましょう。
傷病手当金の詳細は、下記コラムをご確認ください。
なお、傷病手当金と失業保険は、同時期の併用ができません。詳細はこちらの章で解説します。
支援制度②障害年金
障害年金とは、ケガや病気などによって障害を負い日常生活や仕事に支障が出た場合に、年金加入者が受給できる年金です。
年金という名前ではありますが、高齢者だけではなく、20歳以上の人なら受給できます。また、病気やケガが治るまでは、生涯にわたって受給可能です。
障害年金の詳細は、下記コラムをご覧ください(年金未加入時期がある人のための特別障害者給付金制度についても解説しています) 。
傷病手当金と障害年金は、同時期の併用ができます。詳細はこちらの章で解説します。
支援制度③生活保護

生活保護とは、生活に困窮している人に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、「健康で文化的な最低限度の生活の保障」「自立の助長」を目的とした支援制度です。(参考:厚生労働省「生活保護制度」)
「生活に必要な最低限度のお金を持つことが困難な人がお金を受給できる制度」と言えます。
生活保護で受給できるお金には生活扶助(食費・被服費・光熱費など)や住宅扶助(アパートなどの家賃)、医療扶助(医療サービスの費用など)などがあります。
また、受給金以外にも、国民年金保険料や住民税、NHK放送受信料などの税金・公共料金の支払いが減免されることがあります。
「うつ病と生活保護」の詳細は、下記コラムをご覧ください。
支援制度④障害者手帳
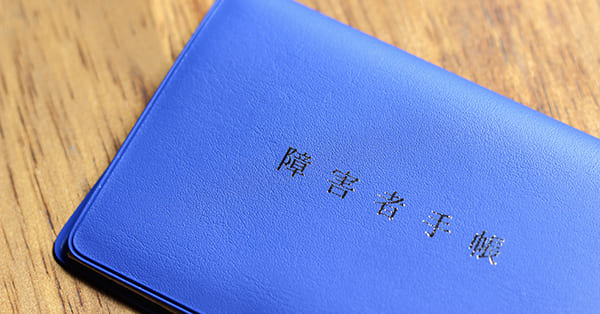
障害者手帳とは、障害のある人が、その障害の内容や程度に応じて交付される手帳の総称です。
障害者手帳には、以下の3種類があります(参考:厚生労働省「障害者手帳について」)。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
種類によって制度の根拠となる法律等は異なりますが、障害者手帳をお持ちの方はいずれも「障害者総合支援法」の対象となり、様々な支援や福祉サービスを受けることができます。
障害者手帳の詳細は、下記コラムをご覧ください。
支援制度⑤特別障害者手当
特別障害者手当とは、「精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給する」制度のことです。(参考:厚生労働省「特別障害者手当について」)
利用できる場合、2023年4月現在では、月額2万7980円を受給できます。
申請先は、お住まいの市区町村役所です。
支援制度⑥自立支援医療制度
自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療に関する医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。うつ病もその支援の対象となります。(参考:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」)
自立支援医療は、下記の3種類に分けられます。
- 精神通院医療(精神疾患の治療など)
- 更生医療(身体障害に関わる治療など)
- 育成医療(身体障害がある子どもに関わる治療など)
自立支援医療制度は指定の医療機関・薬局のみで利用可能ですが、通常3割負担の医療費が1割負担まで軽減されます。
負担額には上限が設定されており、原則上限以上の負担は免除されます。また、費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない場合や所得の程度に応じて、更に軽減措置が行われます。
支援制度⑦労災保険(労働が原因の疾病の場合)

労災保険とは、仕事中や通勤中にケガや疾病といった「労働災害」が発生した場合に、その補償を得られる制度です。(参考:厚生労働省「労働災害が発生したとき」、労働問題弁護士ナビ「うつ病の労災が認められにくい理由と申請手続きの手順・流れを詳しく解説」、厚生労働省「精神障害の労災補償状況」)
ただし、一般論として、うつ病などの精神障害による労災認定は非常に難しいと言われています。
なぜなら、うつ病などの精神障害は原因の特定が難しく、「私生活を含む様々な要因が複合的に絡みあって発症するケース」が多いからです。
また、発病前の約6か月間に仕事による極度の心理的負荷が認められるなど、原因が仕事や職場にあることを明確化するための条件設定が厳しいという問題もあります。
労災保険の対象と認定される可能性もあるため、気になる人は労働基準監督署やお勤め先の人事部などに相談してみましょう。
支援制度⑧生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援制度とは、仕事や住居の確保に困窮している人に対して、生活状況に応じた支援を提供する制度です。(参考:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」、東京都福祉保健局「生活困窮者自立支援制度について」)
生活困窮者自立支援制度は、こちらでも解説した生活保護の受給に至る前に、対象者の自立を促進することを目的に制定された制度です。
就労などの自立に関する相談支援や自立に向けた支援計画の作成などを実施する「自立相談支援事業」、就職活動をすることなどを条件に一定期間の家賃相当額を支給する「住居確保給付金の支給」などの支援を行います。
その支援内容は多岐に渡り、またその内容は自治体によっても異なります。
支援制度⑨生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度とは、低所得者や障害者などの生活を経済的に支えつつ、その在宅福祉や社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。銀行などと比べて、低い金利でお金を借りることができます。(参考:全国社会福祉協議会「生活福祉資金」、厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧」、政府広報オンライン「生活にお困りで一時的に資金が必要な方へ「生活福祉資金貸付制度」があります。| 暮らしに役立つ情報」)
対象となるのは、「低所得者世帯」「障害者世帯」「高齢者世帯」であり、うつ病を含む障害者の場合は障害者手帳などの交付が前提となります。
生活福祉資金貸付制度は大きく分けて下記に分類されます。
- 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
- 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
- 教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
- 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
この制度は、あくまで「貸付」です。返済の義務があるという点は注意しましょう。
その他の支援制度
「実際のあなた」が利用できるサービスは、サポート団体などに相談しましょう。
(退職した)うつ病の人をサポートする制度は、失業保険も含めてたくさんあります。
ですが、うつ病の症状があるときには、制度を調べたり申請したりすることは難しいかもしれません。
「実際のあなた」がどの制度を利用できるかについては、ご家族・主治医・サポート団体などの協力も得ながら、役所、ハローワーク、年金事務所、健康保険組合などに確認することをオススメします。
サポート団体には、次のようなものがあります。
- 精神保健福祉センター
- 就労移行支援事業所
- 地域障害者職業センター
- 障害者就業・生活支援センター
- 復職支援(リワーク・プログラム)
- その他の支援団体
上記以外の支援制度などについては、下記コラムを参考にしてみてください。
適職を見つけたいうつや発達障害のあなたへ
- 初任給
- 38万円
のケースも
- 就職まで
- 4ヶ月
※1
- 就職率
- 83%
※2
※1:他社就労移行支援事業所では通常1年半(自社調べ)
※2:他社就労移行支援事業所では約52%(自社調べ)
ご相談・資料請求は無料です!
お好みの方法でご連絡ください
失業保険と傷病手当金は併用できない

こちらの章で、傷病手当金について解説しました。
傷病手当金は「働けない状態の場合に受給するお金」、失業保険は「働ける状態の場合に受給するお金」です。
よって、傷病手当金と失業保険は、同時期の併用ができません。
ただし、時期をズラして両方を受給することは可能です。
具体的に気になる場合は、次のような流れができそうか、健康保険やハローワークに確認してみましょう。
- 在職中に、傷病手当金を受給して治療
- 退職して、働けないうちは傷病手当金の受給を継続
- 働ける状態になったら、失業手当を申請・受給
失業保険と障害年金は併用できる

こちらの章で、障害年金について解説しました。
障害年金は、求職しながらでも働きながらでも受給できます。
年金という名前ではありますが、高齢者だけではなく、20歳以上の人なら受給できます。また、病気やケガが治るまでは、生涯にわたって受給可能です。
よって、「働く意思があり、働ける状態である場合」は、障害年金と失業保険を同時に受給できます。
まとめ:利用できる経済的支援はたくさんあります

うつ病の人も、条件に当てはまれば失業保険を受給できます。また、失業保険以外にもうつ病の人の利用できる経済的支援はたくさんあります。
経済的支援の利用は、恥ずかしいことでは決してありません。支援を利用して、治療・休養に専念することが何よりも大切です。
「実際のあなた」が利用できる支援については、医師・役所・サポート団体などと話しつつ、具体的に探していくことをオススメします。
この記事が、うつ病に関連して退職した・退職を検討している人の参考になったなら幸いです。
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
執筆内田青子
うちだ・あおこ。1982年生まれ。上智大学文学部卒。
大学卒業後、百貨店勤務などいくつかの仕事を経た後、2018年から発達障害・不登校・中退経験者などのための個別指導塾・キズキ共育塾で講師として国語(現代文・古文・漢文)と小論文を指導し、主任講師となる。
並行して、聖徳大学通信教育部心理学科を卒業。現在、公認心理師の資格取得を目指して、発達障害や不登校支援についてさらに勉強中。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→