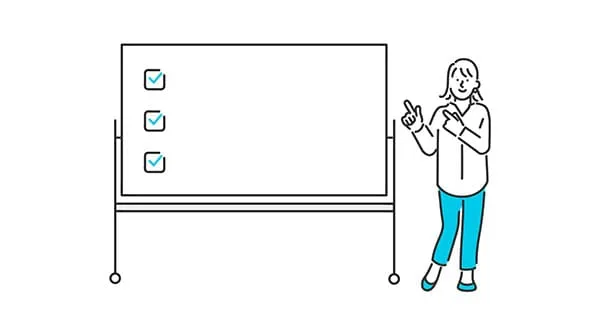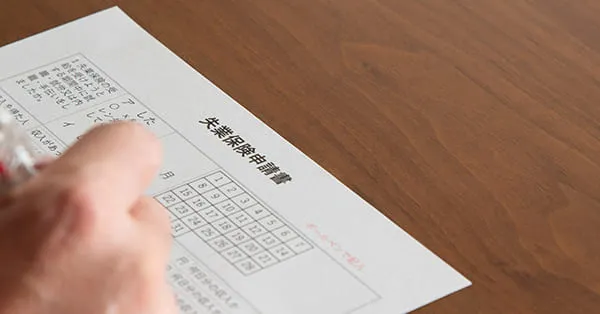うつ病で働けない人が受けられる経済的支援制度12選 支援機関や社会復帰するコツを解説

こんにちは、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジの寺田淳平です。
うつ病で働けないと感じているあなたは、以下のような悩みを抱えていませんか?
- 働けない期間のお金の問題はどうしよう
- うつ病で働けないときに受けられる支援は?
- うつ病で働けないときはどんなところを頼ればいいの?
そこで今回は、うつ病で働けない人が受けられる経済的支援や、頼れる支援機関を徹底解説します。
実際にうつ病から復職に至った私の経験を交えながら、社会復帰のコツも併せて解説します。うつ病が原因で働けない状態に悩んでいる人は、ぜひ読んでみてください。
目次
うつ病で働けない人が受けられる経済的支援制度12選
この章では、うつ病で働けない人が受けられる経済的支援制度を紹介します。
前提:支援制度については、支援機関に相談しましょう
うつ病で働けない人が直面する現実的な問題として、「生活費や治療費をどう工面すればいいのか」という悩みがあると思います。
うつ病で働けない人が受けられる経済的支援(お金を受給できる支援と、各種支払いが減免できる支援)は、たくさんあります。ご安心ください。
ただし、状況によって、「必ず利用できる」とは限りません。また、「支援の対象にあてはまるか」「どの程度の支援を受けられるか」は、個々人の状況によって異なります。
そのため、「実際のあなた」が支援を受ける際には、支援機関に相談することが大切です。
経済的支援を受けることは、恥ずかしいことではありません。支援を受けつつ、経済的に安心してうつ病の治療・休養に専念することで、仕事復帰・仕事探しも含めて「次の一歩」にも進みやすくなります。
その点を心に留めながら、以下を参考に支援を受けるかどうかを検討してみてください。
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、うつ病や発達障害などの人のための就労移行支援事業所です。
- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月
新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。
支援制度①傷病手当金

傷病手当金とは、病気やケガのために仕事を休む場合に「健康保険」の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です(国民健康保険の加入者は対象外です)。(参考:全国健康保険協会「傷病手当金」、全国健康保険協会「傷病手当金について」)
傷病手当金は、「退職前に受給するお金」です。ただし一定の条件を満たせば、退職後も継続して受給できます。
傷病手当金の受給対象は、「病気やケガによって労働不能であり、十分な給与が支給されない人」です(医師の診断書が必要です)。
傷病手当金の窓口は、「全国健康保険協会、各健康保険組合、各共済組合」です。
全国健康保険協会の例では、以下のすべての条件を満たしている必要があります。
- 業務外の病気やケガで療養中であること
- 療養のための労務不能であること
- 4日以上仕事を休んでいること
- 給与の支払いがないこと
これらの項目には、たとえば、「給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給される」などの補足が付いています。
そのため、対象となる協会・組合に問い合わせたりウェブサイトを参照したりして、しっかりと条件を確認することが大切です。
また、傷病手当金の受け取りのためには、基本的にうつ病などの病気であることを証明する「診断書」などの提出が必要になります。
具体的な金額は対象者の標準報酬月額などによって変わるため、より詳しい額を知りたいという方は、人事部門に一定期間の給与額等を確認した上で該当窓口に相談してみてください。
ご興味がある場合は、ご自身の加入している健康保険に問い合わせてみましょう。
「うつ病と傷病手当金」の詳細は、下記コラムをご確認ください。
支援制度②自立支援医療制度
自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療に関する医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。うつ病もその支援の対象となります。(参考:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」、東京都福祉保健局「自立支援医療(更生医療)」)
自立支援医療は、下記の3種類に分けられます。
- 精神通院医療(精神疾患の治療など)
- 更生医療(身体障害に関わる治療など)
- 育成医療(身体障害がある子どもに関わる治療など)
特定の精神疾患がある人以外に、身体障害者手帳を持つ人なども対象になります。
通常、医療保険による医療費の自己負担額は「3割」ですが、自立支援医療制度を利用すれば、原則「1割」まで軽減することができます(指定の医療機関・薬局のみで利用可能)。
つまり、通院や薬の処方のための費用負担が、「通常の3分の1に抑えられる」ということです。
ただし、世帯の総所得額によっては、自己負担上限額が定められていたり対象外となったりする場合があります。
負担額には上限が設定されており、原則上限以上の負担は免除されます。また、費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない場合や所得の程度に応じて、更に軽減措置が行われます。
助成制度の具体的な内容・条件・名称は、いずれも自治体によって異なるため、利用される方はお住いの自治体窓口や病院にて、必ずご確認ください。
また、市区町村に設置されている「障害者生活支援センター」などの支援機関にて、前もって相談するのもオススメです(全国の一覧はこちら)。
支援制度③労災保険(労働が原因の疾病の場合)

労災保険とは、仕事中や通勤中にケガや疾病といった「労働災害」が発生した場合に、その補償を得られる制度です。(参考:厚生労働省「労働災害が発生したとき」、労働問題弁護士ナビ「うつ病の労災が認められにくい理由と申請手続きの手順・流れを詳しく解説」、厚生労働省「精神障害の労災補償状況」)
お勤め先に経緯を説明した上で、労働災害に相当する条件を満たした場合には、所定書式を記載して労働基準監督署へ提出することになります。
ただし、一般論として、うつ病などの精神障害による労災認定は非常に難しいと言われています。
なぜなら、うつ病などの精神障害は原因の特定が難しく、「私生活を含む様々な要因が複合的に絡みあって発症するケース」が多いからです。
また、発病前の約6か月間に仕事による極度の心理的負荷が認められるなど、原因が仕事や職場にあることを明確化するための条件設定が厳しいという問題もあります。
しかし、認定されるかどうかに関わらず、そのときの状況次第では申請することは可能です。
労災保険の対象と認定される可能性もあるため、気になる人は労働基準監督署やお勤め先の人事部など、労災保険の管轄部署に一度相談してみるとよいでしょう。
支援制度④失業保険(失業手当、雇用保険給付)

失業手当とは、うつ病に限らず、失職した人が就職するまでの一定期間、受給できる給付金のことです。
原則的には、「退職までの一定期間、雇用保険に加入していたこと」と「求職活動を行っていること」が条件になります。
ここで言う「求職活動」とは、企業への面接訪問などに限らず、窓口相談や職業訓練も含まれますので、現状「うつ病で働けない」という方でも条件を満たすことは充分可能です。
具体的な受給期間(90日~360日)や金額(在職中の給与の約50~80%)は、その人の状況によって異なりますが、うつ病などの疾病によって求職活動条件を満たせない場合には、受給期間を延長することも可能です。
また、これまで述べてきた失業手当は「基本手当」と呼ばれるものになりますが、「病気やケガによって15日間以上、引き続いて求職活動ができない状態」の場合は、「傷病手当」という別の給付金を受給することができます。
なお、雇用保険上の「傷病手当」は、先述した健康保険制度の「傷病手当金」とは異なることに加えて、「両方を同時に受給できない」点には注意してください。
窓口は、各自治体に設置されているハローワークになりますので、気になる人は条件などを問い合わせてみてください。(参考:ハローワークインターネットサービス『雇用保険手続きのご案内』)
「うつ病と失業保険」の詳細は、下記コラムをご覧ください。
支援制度⑤障害者手帳
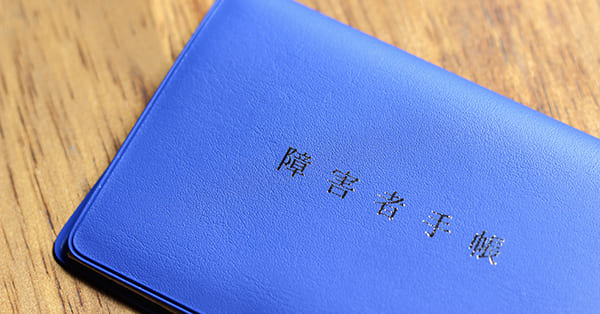
障害者手帳とは、障害のある人が、その障害の内容や程度に応じて交付される手帳の総称です。
障害者手帳には、以下の3種類があります(参考:厚生労働省「障害者手帳について」)。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
種類によって制度の根拠となる法律等は異なりますが、障害者手帳をお持ちの方はいずれも「障害者総合支援法」の対象となり、様々な支援や福祉サービスを受けることができます。
障害者手帳の詳細は、下記コラムをご覧ください。
支援制度⑥障害年金

障害年金とは、病気やケガなどによって障害を負い、日常生活や仕事に支障が出た場合に、年金加入者が受給できる年金です。(参考:日本年金機構「障害年金」)
年金という名前ではありますが、高齢者だけではなく、20歳以上の人なら受給できます。
また、病気やケガが治るまでは、生涯にわたって受給可能です。
障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること。
以下の①もしくは②を満たしていること。
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上納められている。
- 初診日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納期間がないこと。
なお、20歳前に初診日がある場合は保険料納付要件は問われません。
申請した障害年金の種類に対応する、以下の障害等級などの条件を満たしていること。
- 障害基礎年金:1級、2級
- 障害厚生年金、障害共済年金:1級、2級、3級、障害手当金
なお、初診日に加入していた年金の種類やあなたの置かれている状況によって、「障害年金の申請が受理されるかどうか」「金額がどの程度になるか」は変わってきます。
中には、例外の取り扱いもありますので、詳細は各自治体に設置されている障害年金相談センターやNPO法人 障害年金支援相談ネットワークなどに問い合わせて確認してみてください。(参考:NPO法人 障害年金支援相談ネットワーク『うつ病と障害年金』)
障害年金の詳細は、下記コラムをご覧ください(年金未加入時期がある人のための特別障害者給付金制度についても解説しています)。
支援制度⑦特別障害者手当
特別障害者手当とは、「精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給する」制度のことです。(参考:厚生労働省「特別障害者手当について」)
利用できる場合、2023年4月現在では、月額2万7980円を受給できます。
申請先は、お住まいの市区町村役所です。
支援制度⑧特別障害給付金制度
特別障害給付金制度とは、国民年金に任意加入していなかったことで、障害基礎年金などの受給要件を満たせず障害年金を受給できない障害のある人に対する福祉的措置として創設された制度のことです。(参考:日本年金機構「特別障害給付金制度」)
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」に基づく給付であり、障害基礎年金や障害厚生年金とは異なる制度です。
障害基礎年金1級相当に該当する人は月額5万3650円(2023年時点)、障害基礎年金2級相当に該当する人は4万2920円(2023年時点)が、支給されます。
支援制度⑨心身障害者医療費助成制度

心身障害者医療費助成制度とは、重度心身障害者の福祉の増進を図る目的で、各自治体が医療費の一部または全部を助成する制度のことです。「マル障」と呼ばれることもあります。(参考:東京都福祉局「心身障害者医療費助成制度(マル障)」、渋谷区ポータル「医療費の助成 | 障がい者の医療」)
一般的に、各種医療保険の自己負担から一部負担金を差し引いた金額または全額が助成されます。
自治体によって助成の内容や受給条件などのルールが異なります。
気になる方は各自治体の窓口にご相談ください。
支援制度⑩生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援制度では、うつ病に限らず、仕事や住まいの確保に困窮している方に向けて、各々の生活状況に応じた支援を提供しています。(参考:厚生労働省「制度の紹介」、東京都福祉保健局「生活困窮者自立支援制度について」)
この支援制度は、次項で解説する「生活保護」の受給に至る前に、対象者の自立を促進することを目的に制定されたものです。
経済、就労、住居確保といった幅広い分野について相談することができ、要件を満たす人には家賃相当額の支給といった経済的な支援も行っています。
また、自立相談支援機関が作成した支援プランに沿って、一定期間、支援員が生活を立て直すためのサポートをしている場合もあります。
生活困窮者自立支援制度の支援内容は多岐に渡り、またその内容は自治体によっても異なります。
こちらの支援について気になる場合は、自治体の窓口になっている担当課に相談してみましょう。
支援制度⑪生活保護

生活保護とは、生活に困窮している人に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、「健康で文化的な最低限度の生活の保障」「自立の助長」を目的とした支援制度のことです。(参考:厚生労働省「生活保護制度」)
「生活に必要な最低限度のお金を持つことが困難な人がお金を受給できる制度」と言えます。
生活保護で受給できるお金には生活扶助(食費・被服費・光熱費など)や住宅扶助(アパートなどの家賃)、医療扶助(医療サービスの費用など)などがあります。
- 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)
- アパート等の家賃
- 義務教育を受けるために必要な学用品費
- 医療サービスの費用
- 出産費用
- 就労に必要な技能の修得等にかかる費用
- 葬祭費用
また、受給金以外にも、国民年金保険料や住民税、NHK放送受信料などの税金・公共料金の支払いが減免されることがあります。
生活保護制度の申請窓口は、お住まいの市区町村を所管する福祉事務所になりますが、まずは、自治体の生活保護課に相談するようにしましょう。
ただし、生活保護は一般には審査が厳しく、年齢や条件によっては申請が却下される可能性があることは心に留めておいてください。
「うつ病と生活保護」の詳細は、下記コラムをご覧ください。
支援制度⑫生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度とは、低所得者や障害者などの生活を経済的に支えつつ、その在宅福祉や社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。銀行などと比べて、低い金利でお金を借りることができます。(参考:全国社会福祉協議会「生活福祉資金」、厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧」、政府広報オンライン「生活にお困りで一時的に資金が必要な方へ「生活福祉資金貸付制度」があります。| 暮らしに役立つ情報」)
対象となるのは、「低所得者世帯」「障害者世帯」「高齢者世帯」であり、うつ病を含む障害者の場合は障害者手帳などの交付が前提となります。
生活福祉資金貸付制度は大きく分けて下記に分類されます。
- 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
- 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
- 教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
- 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
この制度は、あくまで「貸付」です。返済の義務があるという点は注意しましょう。
うつ病で働けない人が頼れる支援機関4選
最後に、うつ病で働けない人が頼れる支援機関を紹介します。
この章では、無料で相談を受け付けている公的機関のみを紹介しますが、民間にも支援機関はありますので、興味のある方は調べてみるとよいでしょう。
もし、どの支援機関が自分にふさわしいかが分からないという場合は、居住地の自治体の「障害福祉課」が基本の窓口になりますので、そちらに相談することをオススメします。
また、ここで挙げる支援機関の中には、うつ病で働けない人向けの職場復帰を念頭に置いた「リワークプログラム」や職業訓練を実施しているところもあります。ただし、体調と相談の上、無理はしないことが大切です。
あくまでも、体調を第一に考えた上で、あなたにとって適切な支援を受けるということを忘れないようにしてください。
支援機関①就労移行支援事業所

就労移行支援事業所では、一般企業への就職を目指す病気や障害のある人向けに、障害者総合支援法に基づいて行われる障害福祉サービスを提供しています。
就労移行支援事業の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。
- 原則18歳から65歳未満であること
- 一般企業への就職または仕事での独立を希望していること
- 精神障害、発達障害、身体障害、知的障害や難病を抱えていること
障害者手帳は必須ではなく、うつ病の人でも専門医による診断書があればサービスを受けることができます。
具体的な支援内容は事業所によって異なりますが、仕事相談からメンタル面の相談、自己管理の方法といったサポートを行っています。
うつ病による休職のあとで転職を視野に入れているという方には、専門スキルの講習や面接指導、インターン先・就職先の紹介までと、幅広い支援を受けられるため、特にオススメです。
相談は無料ですので、興味を抱いた事業所にお問い合わせしてみるとよいでしょう。(参考:厚生労働省『就労移行支援事業』)
就労移行支援事業所の詳細は、下記コラムをご覧ください。
支援機関②精神保健福祉センター

精神保健福祉センターとは、うつ病を含む精神疾患がある人のサポートを目的に、精神保健福祉法によって各都道府県に設置された支援機関です。
心の問題や病気で困っているご本人だけでなく、ご家族や関係者の方からも精神衛生に関する相談を受け付けています。
精神保健福祉センターは、他の支援機関と比較して精神疾患に特化している点が特長といえるでしょう。
匿名でも相談を受け付けていますので、まずは電話にて問い合わせてみてください。(参考:東京都福祉保健局『精神保健福祉センターとは』)
精神保健福祉センターの全国の一覧はこちらに掲載されています。
支援機関③地域障害者職業センター

地域障害者職業センターでは、うつ病に限らず、障害を抱える一人ひとりのニーズに応じて、職業評価、職業指導、職業訓練などの専門的な職業リハビリテーションサービスを提供しています。
うつ病の症状そのものよりも、次のような、「働けない」ことから来る悩みが特に大きいという方にオススメです。
- 「仕事に苦手意識が付いた」
- 「働きたくても働けない」
- 「働くことに抵抗感がある」
運営は、「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」が行っており、全国47都道府県に設置されています(全国の一覧はこちらです)。
また、当事者だけでなく、事業主に対しても雇用管理に関する相談・援助を実施しています。(参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構『地域障害者職業センター』)
支援機関④障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターでは、就業及びそれに伴う日常生活上の支援が必要な障害のある人に対し、センター窓口での相談や職場・家庭訪問などを実施しています。
こちらは仕事に限らず、生活面での支障も大きいと感じている方にオススメです。
厚生労働省の資料によると、2019年5月時点で334センターが設置されており、当事者の身近な地域において就業面と生活面を一体に捉えた相談と支援を行っています。
障害者就業・生活支援センターの特徴は、就労だけでなく、金銭管理などの経済面や住居のことまで多岐にわたって相談できる点にあります。
興味のある方は、お近くの事業所にご相談ください。(全国の一覧はこちらです)
(参考:厚生労働省『障害者就業・生活支援センター』)
うつ病で働けない人が社会復帰するコツ8点
ここからは、うつ病で働けない人が社会復帰するためのコツを解説していきます。
前提として大切なのは、必ず定期的に病院を受診して、かかりつけ医の指示を仰ぐことです。
あなたが「そろそろ働けるかもしれない」と感じるときであっても、医師は「慎重に様子を見た方がよい」と判断する場合もあります。
また、薬を服用している方は、自己判断で断薬することは絶対にやめましょう。
上記に留意した上で、以下のコツを実践していくようにしてください。
コツ①復帰を焦らずに休養する

まず、「復帰を焦らずに休養する」ことを意識しましょう。
うつ病の人の中には、経済的な不安などから「働けないけど働かなくては」と焦る方もいると思います。
また、先述したように、人から「うつ病は甘えだ」と言われたり、ご自身でも「もっと頑張れるのではないか」と考え込んだりすることがあるでしょう。
しかし、そうした気持ちや思いがプレッシャーになり、自分を追い込んでいる可能性があります。
その焦りやプレッシャーによって、治療が長引くことにもなりかねませんので、復帰を焦らずに「まずは休養することが大切」という意識を保つようにしてください。
コツ②定期的にカウンセリングを受ける

コツの2点目は「定期的にカウンセリングを受ける」です。
うつ病を治療中の人の中には、医師による診察と薬の処方のみで、臨床心理士などによるカウンセリングを受けていない方がいるかと思います。
そういう方は、専門のカウンセラーによる定期的なカウンセリングを受けるのも有効です。
カウンセラーは、医師の診察では拾いきれなかった日常の細かな心配ごとやストレス、社会復帰への不安などを聞き取ります。
もし、認知や思考に偏りがある場合には、それとなく本人が自覚して修正できるようにアドバイスを得られます。
また、カウンセラーによる経過観察を続けることで、症状に何らかの変化が現れたとしても、いち早くその変化に気づくことができます。
そのため、よりあなたの状況に合った示唆や助言を得られるようになるでしょう。
コツ③支援機関に通所・相談する

うつ病による意欲低下よりは、仕事から長く離れていたことで「働くのが恐い」「仕事に抵抗がある」といった気持ちゆえに「働けない」と思っている人もいるでしょう。
そういった方には、「支援機関に通所・相談する」ことをオススメします。
うつ病の診断が下っている人に対して、障害福祉サービスを提供している機関は、公民を問わずたくさんあります。(具体的な支援機関は次の章で紹介します)
中には、後述する就労移行支援事業所などのように、単にうつ病の症状に関する相談だけでなく仕事で活かせる自己管理の方法や、実践的な仕事術、専門的なスキルの講習など、社会復帰に向けた実際的な支援を提供している機関もあります。
サービスの内容にもよりますが、基本的には「無料」でサービスを受けられるところばかりですので、医師やカウンセラーだけでなく、そうした支援機関に頼るのもよいでしょう。
コツ④生活習慣を整える

4点目は「生活習慣を整える」です。
就寝と起床の時間は、できるだけ一定になるように心掛けましょう。
睡眠リズムの乱れは、生活リズムの乱れに直結するだけでなく、あなたが日頃感じるストレスにも大きく影響します。
特に、睡眠不足が続くと、日中も頭が朦朧としたり意欲が湧かなかったりしやすいので、気をつけてください。
また、薬物療法を受けている方などは、アルコールやカフェインの摂取にも注意が必要です。
これらの嗜好品は、薬効に悪影響を及ぼす可能性があるだけでなく頭痛や不安の原因にもなります。
依存性もありますので、ストレス解消につながるように思えても控えるのが賢明でしょう。
コツ⑤適度に運動をする

「適度に運動をする」というのも、うつ病でお悩みの方には有効です。
意欲が低下していたりだるかったりすると、身体を動かすのも大変に感じられるかもしれせんが、できる範囲で簡単な運動を始めましょう。
特に、日中に陽を浴びながら散歩や軽いジョギングをすると、生活リズムを整えることにもつながるためオススメです。
もちろん、室内でストレッチをしたりスクワットをしたりするのもよいでしょう。
体力が付くだけでなく、ストレスの発散にもなりますし、身体を動かすことで意欲が湧いてくることもありますのでぜひ試してみてください。
コツ⑥ストレス対処法を身につける

6点目は「ストレス対処法を身につける」です。
人は仕事に限らず、日常生活においてもさまざまなストレスにさらされています。
そのストレスの中には、その日の天候や気温など環境によるストレスも少なからずあります。
そうしたストレスを溜め込まずに上手に発散する方法を身につけておくことが、心の健康を保つために大切です。
うつ病で「働けない」という人は、こうしたストレスを緩和するための方法を身につけるようにしましょう。
ストレス対処法は、人によってさまざまです。
散歩やウィンドウショッピングのように外出することが気晴らしになる人もいれば、家の中で読書をしたり映画を観たりすることがストレス発散になる人もいます。
体力的に無理のない範囲で興味が持てることを試し「何をすると気持ちが楽になるか」をご自身で探ってみてください。
ストレス対処法が身につけば仕事(それにより生じるストレス)への抵抗が薄れるため、働くことへのハードルが徐々に下がるでしょう。
コツ⑦雇用枠の変更を検討する

「雇用枠の変更を検討する」ことで、就労に伴う困難を減らせる可能性があります。
具体的には、これまで「一般枠」での就労をしていてうつ病の症状が重い人の場合、精神障害者保健福祉手帳を取得して「障害者枠」での就労を検討するという方法があります。
「障害者枠」とは、障害に応じて業務内容や業務量の配慮を受けられる障害のある人を対象とした雇用枠です。
原則的には、障害を証明するために障害者手帳を所持していることが条件になります。
「障害者枠」では障害への配慮がある分、一般枠よりも比較的働きやすくなると考えられますが、その分だけ、給与や待遇、キャリアといった点が制限される可能性があります。
したがって、「仕事に何を求めるのか」「なにを重視して就労したいか」といった点をよく考慮し、どの雇用枠が向いているかを総合的に判断することが大切です。
もし、判断に迷うようであれば、後述する就労移行支援事業所のような支援機関に相談することで、アドバイザーから有益な意見をもらえます。専門家を頼るようにしましょう。
コツ⑧勤務形態や業態を見直す

最後のコツは「勤務形態や業態を見直す」です。
正規雇用やフルタイムでの就業にこだわらず、アルバイトやパート勤務といった、非正規での雇用に切り替えるのも、一つの方法です。
人によっては、朝9時から夜17時までの勤務といった「固定時間制」がストレスになっていたため、就労時間を柔軟に変えられる「フレックス制」や「裁量労働制」を取り入れている勤め先に移ったら、楽に働けるようになったという人もいます。(ただし、フレックス制には「コアタイム」といって、たいていは必ず働かなくてはならない時間帯を設定することが求められます)
あるいは、「自由業(フリーランス)」に転業したことで、「うつ病で働けないと思っていたけれど働けることに気づいた」という人もいるでしょう。
このように、勤務形態や業態にはさまざまな種類があり、人によって「向き・不向き」があります。
ぜひ、いろいろな働き方を検討し、必要であれば専門家の意見も取り入れながら、これまでの勤務形態・業態を見直してみてください。
改めて、うつ病とは?
改めて、うつ病の概要について説明します。既にご存知かも知れませんが、これまでに紹介した内容の理解も深まると思いますので、ぜひご覧ください。
うつ病とは、気分の落ち込みや憂うつ感、意欲の低下が一定期間、持続する精神障害の一種です。
うつ病は、所属している環境や仕事のストレスが引き金になることもありますが、明確な原因が見当たらないまま発症することも多いため、原因による分類・定義は難しいと言われています。
一般的には女性、若年者に患者が多いとされていますが、日本では中高年でも頻度が高いです。
厚生労働省が実施している患者調査によれば、うつ病を含む気分障害の日本での患者数は2002年には71.1万人、2005年には92.4万人、2008年には104.1万人と、著しく増加しています。
また、ICD-10(世界保健機関の分類)診断によると、「うつ病の12ヶ月有病率は2.2%」、「生涯有病率は7.5%」であり、「過去12ヶ月間にうつ病を経験した人は約50人に1人」、「生涯にうつ病を経験した人は約15人に1人」と、決して珍しい病気ではないのです。
(参考:厚生労働省「うつ病|疾患の詳細(リンク失効)」)
①うつ病の症状

うつ病の症状は、精神症状と身体症状に大きく分けられます。
- 憂うつ感が続く
- 気分が重い
- 不安である
- 集中できない
- 興味が湧かない
- 罪悪感がある
- 食欲がない
- 身体がだるい
- 疲れやすい
- 動悸がする
- 頭痛、肩こり
- 胃の不快感
ただし、上記の症状は、うつ病でない人であってもショックな出来事などが起こった際などに一時的に感じるものです。
また、症状の原因が身体疾患にあるというケースもあります。
症状の程度や持続期間など、様々な基準によって「うつ病かどうか」は診断されるため、症状があるからといって自己判断せず、必ず専門医を受診するようにしましょう。
②うつ病の治療法

うつ病の治療法には、大きく分けて、「薬物療法」と「精神療法」の2つがあります。
その名の通り、症状の改善が期待できる「抗うつ薬」を服用する療法です。
医師やカウンセラーと会話をしながら、自身の考え方の癖や認知(思考)の歪みを修正していく「認知行動療法」などがメインとなります。
薬物療法と精神療法の比率は、疾患の内容や程度によって変わります。
気分が高揚する「躁うつ症状」を伴う場合には、うつ病ではなく「双極性障害」の可能性があるため、躁とうつの波を小さくする「気分安定薬」を使用することもあります。
また、身体疾患や、その治療のための薬剤が、うつ病の原因になっているケースもあるため、可能性がある場合には、身体疾患の治療や薬剤の中止あるいは変更を考慮することもあります。
③うつ病で働けないのは「甘え」?

「うつ病で働けないのは甘え」だという意見は、インターネット上に限らず、たびたび耳にするものです。
実際、私がうつ病で休職をしたときにも、親類や知人の一部から「働けないのではなく、怠けているだけではないのか」というような言葉を投げかけられたことがありました。
しかし、「うつ病は甘え」という意見をあなたが真に受ける必要はありません。
まず、一般的に「甘えとは何か(どういう状態が甘えか)」の判断基準が人によって異なる上に、「甘えかどうか」という目に見えない心理状態について何かを断言できる知見を備えている人は少ないからです。
また、私の見た限り、「うつ病は甘え」という考えを持つ人の多くはうつ病への理解が少なく、そもそも「うつ病を病気の一種ではない」と思い込んでいる傾向があります。
しかし、だとしたら何のために専門医は時間をかけてカウンセリングをし、心理検査を行って「うつ病」という診断を下すのでしょうか。
それは、心が休養のサインを出しているにも関わらず、「うつ病は甘えだからまだまだ働ける」と考える人にストップをかけるためでもあるのです。
専門家からうつ病という診断が下りている以上は、「働けないのは甘えているだけではないのか」という考えに惑わされず、まず「休養を取ること」を優先するようにしてください。(参考:キズキビジネスカレッジ『うつは甘え?勘違いされやすいうつの症状と種類を徹底解説します』)
うつ病で働けない理由5点
うつ病で「働けない」という人には具体的にどういった事情があるのでしょうか?
この章では、うつ病への理解を深めるためにも「よくある働けない理由を5点」、紹介します。(参考:大野裕『うつ病の人の気持ちがわかる本』)
理由①医師に休養を求められている

最初に考えられるのは、「医師に休養を求められている」からです。
うつ病になると、食欲減退や意欲低下などにより、行動をするためのエネルギーが減りやすくなります。
そのため、医師から「休職した方がよい」などの休養を勧められることがあります。
診断書に「加療を要する」といった文言で、休養の必要性を明示される場合も多いでしょう。
中には、本人が「まだ働ける」と感じていても、医師の方で「この状態では働けない」「働かない方がよい」と判断するケースもあります。
理由②意欲がわかない

2つ目は「意欲がわかない」というものです。
うつ病でない人は、たとえ気が進まないことやストレスを感じることでも、必要であれば実行することができます。
しかし、うつ病になると意欲が減退しやすいので「何もする気がわかない」「何もできない」と無気力になることが多々あります。
結果として「働けない」と感じる人が多いようです。
理由③体が重くて動けない

うつ病で働けないよくある理由として、そもそも「体が重くて動けない」というものが挙げられます。
うつ病を経験した人でないと理解しづらい面はありますが、単に行動意欲が湧かないだけでなく、「体が重くてベッドから起き上がれない」と感じることも少なくありません。
また、「体が鉛のように重い」と感じる人も多いです。これは専門用語で「鉛様麻痺」という言葉があるくらいに、うつ病の症状として認知されているものです。
当然、動くこともつらいので、「働けない」と考えるようになります。
理由④薬の副作用で集中できない

「薬の副作用で集中できない」ことで「働けない」というケースもあります。
治療薬の中には、体質によって眠気を催すものや鎮静作用で多少ぼうっとするものがあります。
そうした薬の副作用で集中できないことから、働くのがつらかったり、「働けない」と感じたりする人がいるようです。
ただし、医師と相談の上で治療薬を少しずつ変えていくことで、薬の副作用についての悩みは解決する可能性があります。
理由⑤頑張るとすぐに疲れる

最後は「頑張るとすぐに疲れる」という理由です。
うつ病の症状に「易疲労性(通常より疲れやすい体質であること)」があります。運動などをして体力的に疲れているわけではないのに、「なぜか疲れる」のです。
また、なかなか疲れが抜けないことで、治療を進めながら仕事をしている人の中には、出勤する時点で疲れを感じる人もいるでしょう。
こうした疲労感の積み重ねが、「これ以上働けない」といった実感につながるようです。
まとめ:うつ病で働けない人が受けられる支援はたくさんあります

うつ病で働けない人が受けられる経済的支援から社会復帰のコツ、頼れる支援機関までを紹介してきました。
役立ちそうな情報がありましたか?
大切なのは、「うつ病で働けない」という悩みを一人で抱え込まずに周囲の専門家を頼ることです。
これまで述べてきた通り、うつ病で働けない人が頼れる支援制度、支援機関はたくさんあります。
焦らず、そういった制度や支援センターを利用し専門家の意見を取り入れていくことで、少しずつあなたの心身の調子を取り戻していけるはずです。
まずはお気軽にご相談・お問い合わせをしてみてください。
うつ病で働けない自分が利用できる経済的支援を知りたいです。
代表的な例として、次の6点が挙げられます。「傷病手当金」「自立支援医療制度」「障害年金」「失業手当(雇用保険給付)」「労災保険(労働が原因の疾病の場合)」「生活保護」。詳細はこちらをご覧ください。
うつ病で働けない自分が社会復帰するためのコツを知りたいです。
一般論として、次の8点が考えられます。「復帰を焦らずに休養する」「定期的にカウンセリングを受ける」「支援機関に通所・相談する」「生活習慣を整える」「適度に運動をする」「ストレス対処法を身につける」「雇用枠の変更を検討する」「勤務形態や業態を見直す」。詳細はこちらをご覧ください。
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
執筆寺田淳平
てらだ・じゅんぺい。
高校2年の春から半年ほど不登校を経験。保健室登校をしながら卒業し、慶應義塾大学に入学。同大学卒業後の就職先(3,500人規模)で人事業務に従事する中、うつ病を発症し約10か月休職。寛解・職場復帰後、勤務を2年継続したのち現職のフリーライターに。
2019年に一般財団法人職業技能振興会の認定資格「企業中間管理職ケアストレスカウンセラー」を取得。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→