就労定着支援とは? 利用料金や条件、対象者を簡単に解説

あなたは、就労定着支援の利用を検討しているものの、どのようなものか分からず、お困りではないでしょうか。
就労定着支援では、「就職しても、すぐにやめてしまう」などの問題を解決するうえで役立つ支援を受けられます。
就労定着支援をうまく活用するためには、自分に合った支援事業所を見極めることが大切です。
この記事では、就労定着支援とはどのようなものか、支援内容、メリット、手続きの流れ、選ぶときのポイントについて解説します。
自分に合った就労定着支援事業所をどう選べばよいかお困りの方はぜひ参考にしてください。
目次
就労定着支援とは?
就労定着支援の定義について簡単にまとめると、「病気や障害のある人が、就職後、退職せずに長く働けるように支援するサービス」となります。
支援を行う事業所が、「就職後の悩みや不安がある本人」と「就職先」の間を調整し、問題解決をサポートします(参考:e-GOV 法令検索「平成十七年法律第百二十三号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」 )
「病気や障害のある人の雇用は徐々に増えてきてはいるものの、定着率は高くはないこと」を背景に、改正障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスとして2018年4月から始まりました。
就労定着支援とジョブコーチとの違い

就労定着支援と似ている仕組みに、ジョブコーチ(職場適応援助者)があります。
ジョブコーチとは、病気や障害のある人の職場適応に問題がある際に、障害特性を踏まえた支援を行い、職場適応を図る人のことです。(参考:厚生労働省「職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業について」 )
就労定着支援とジョブコーチは大まかな目的は似ていますが、別々の制度のため、対象者や期間、利用料金に違いがあります。
ジョブコーチは、利用できる期間が1〜8か月と短いものの、無料で利用できることが特徴です。
就労定着支援と就労移行支援との違い
就労移行支援(事業所)とは、「病気や障害があり、一般企業への就職などを目指す人」の就職をサポートする仕組みのことです。
直接的に就職に関係するサポートのほか、生活改善などのサポートも行います。
就労移行支援は就職できるまでをサポートしますが、就労定着支援では就職した後のことをサポートします。
就労移行支援事業所が就労定着支援事業所を兼ねているケースがあり、そのまま同じ事業所に支援を依頼することもあります。
就労移行支援について詳しく知りたい方は下記コラムをご覧ください。
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、うつ病や発達障害などの人のための就労移行支援事業所です。
- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月
新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。
就労定着支援と就労継続支援(A型、B型)との違い

就労継続支援(事業所。A型、B型)とは、「病気や障害があり、現時点で一般企業への就職が難しい人」に向けて、事務業務や軽作業などの実業務の機会の提供や必要な能力の向上を行う職業訓練サービスを提供する支援(機関)です。
就労継続支援A型事業所(A型作業所)は比較的一般就労に近い仕事を、就労継続支援B型事業所(B型作業所)は比較的簡単な軽作業などを取り扱っています。
作業の対価として、給料や工賃が支払われることが就労継続支援の特徴です。
就労継続支援(A型、B型)について詳しく知りたい方は下記コラムをご覧ください。
就労定着支援を利用する条件
就労定着支援を利用するためには、条件があります。以下、解説します。(参考:厚生労働省「就労定着支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」)
就労定着支援の対象者

就労定着支援を利用できるのは、以下のサービスを利用して就職した、病気や障害のある人です。
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
それぞれの支援内容については後ほど解説します。
就労定着支援の利用期間
就労定着支援は最長で3年利用できます。1年ごとに、利用期間が更新されます。
3年経過後は支援事業者の方針によって異なり、任意で継続支援を受けられるケース、障害者就業・生活支援センターに引き継がれるケースに分かれます。
3年後にどのような支援が受けられるのかについては、支援を受けている(受けようとしている)就労定着支援事業所に相談してみることがおすすめです。
障害者就業・生活支援センターとは、障害のある人や障害のある人の雇用をする企業に対して相談、支援を行う施設です。(参考:厚生労働省OSAKA 大阪労働局「障害者就業・生活支援センターのご案内」)
就労定着支援の利用料金

就労定着支援の利用料金は、厚生労働省が定めており、事業所による違いはありません。
その上で、サービス利用者の前年の収入状況などによって異なります。大まかな費用感は以下のようなイメージです。
- 住民税が非課税の場合:自己負担なし(無料で利用可能)
- 前年の年収204万円以上の場合:自己負担あり(例:月額3500円など)
なお、この利用料金は1割が自己負担で、9割が市区町村が負担することになっています。
料金体系は、就労移行支援や就労継続支援と同じです。
前年度に収入がなかったり、納税額が一定以下だったりした場合などは、料金の発生が就労定着支援の利用後2年目からとなることも多いです(その前年に就職して、給料の受け取りを開始しているため)。
料金体系や、実際に必要な費用を確認したい人は、お住まいの地域の市区町村役所の、障害福祉の担当窓口に問い合わせてみてください。
なお、費用の支払いが発生するのは利用者である本人のみで、就業先の企業に対しては、費用がかかりません。
就業先の企業に費用面で負担がかかるわけではない点は安心して利用できます。
就労定着支援を利用できる場所
就労定着支援を行うのは、以下の事業所のうち、就労定着支援事業所として指定を受けている事業所です。
- 就労定着支援事業所
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所(A型、B型)
- 生活介護事業所
- 自立訓練事業所
- 障害者就業・生活支援センター
それぞれどのような事業所なのかはこちらの章で解説します。
補足①:事業所の変更は可能

ある事業所で就労定着支援を受けている途中で、別の事業所に変更することは可能です。変更によるペナルティや変更回数制限などもありません。
ただし、変更する際には、障害者福祉サービス受給者証を発行している市区町村役所へ報告する必要があります。
「ここの就労定着支援は自分に合っていない」と感じたら、別の事業所を探してみるのがおすすめです。
補足②:就労移行支援を受けた事業所以外でも就労定着支援は受けられる
就職までに就労移行支援事業所・就労継続支援事業所を利用していた場合、就労定着支援までサポートできる事業所もあります。
しかし、必ずしも一緒である必要はなく、別の就労定着支援事業所を利用しても問題ありません。
「就職するまでのサポートは自分に合っていたけど、就職してからのサポートは合っていないな…」と感じた場合は、事業所の変更を検討してみましょう。
補足③:就労定着支援の利用中に転職しても支援を受けられる

就労定着支援の利用中に転職しても、条件を満たしていれば転職後に再び就労定着支援を受けられます。具体的な条件は以下の通りです。
- 就労定着支援の利用中の転職が1回目であること
- 退職から転職までに離職期間がある場合、それが1か月以内であること
- 就労定着支援を利用できる最長期間を過ぎていないこと
以上の条件をすべて満たしていれば、転職後も就労定着支援が利用できます。
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、うつ病や発達障害などの人のための就労移行支援事業所です。
- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月
新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。
就労定着支援の主な取り組み
就労定着支援では、具体的にどのような支援が受けられるか気になる人もいるでしょう。
ここでは、就労定着支援で主に行われる取り組みについて解説します。
取り組み①利用者と面談

事業所は、利用者と面談を行い、利用者の就労状況にどのような課題があるのかを確認します。必要に応じて、解決策の提案などまで行うこともあるでしょう。
この面談は月1回以上行うことが法律で定められています。面談は、対面で行うこともあれば、zoomなどのオンラインツールを使うこともあります。
取り組み②関係機関との連絡・調整
事業所は、利用者が抱える課題解決のために、利用者本人だけではなく、関係機関との連絡や調整も行います。
医療機関などと連携し、相互に協力しながら、利用者が継続して就労できるようにサポートします。
取り組み③利用者への支援
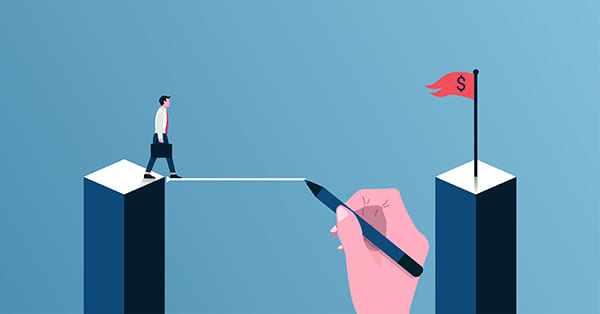
事業所は、利用者に向けた直接的な支援も行います。課題解決に向けた指導やアドバイスなどが主な手法です。
利用者本人だけではなく、就職先や家族に対してのヒアリングやサポートも支援に含まれます。
就労定着支援を利用するまでの流れ
就労定着支援を利用する際、利用までどのような流れで進むのか気になる人も多いでしょう。ここでは、就労定着支援を利用するまでの流れを解説します。
細かい部分や具体的な部分は、事業所によって異なる可能性があります。参考としてご覧ください。
流れ①就労定着支援事務所を探す

お住まいの地域に、就労定着支援事業所があるか探してみましょう。
事業所を探す際には、事業所ごとの公式WEBサイトを確認するか、自治体の障害福祉窓口などに相談することがおすすめです。
なお、就労移行支援や就労継続支援を利用している場合は、その事業所で就労定着支援が受けられないか確認してみましょう。
また、障害福祉サービスを利用せずに就職して、就労定着支援を受けたい人は、障害者就業・生活支援センターを利用できます。
流れ②事前見学
気になる事業所を見つけたら、就労定着支援について、どのような支援を行っているのか、確認・見学をしましょう。
ほとんどの事業所では無料で、相談・見学・体験ができます。気になる事業所があるなら、試しに利用してみることがおすすめです。
流れ③申請

就労定着支援の利用申請は、対象の事業所ではなく、お住まいの市区町村の窓口で行います。
「その事業所で、現在就労移行支援などを利用している」という場合でも同様です。
流れ④認定調査・受給者証発行
事前に調査員によって生活状況の聞き取り調査などが行われます。
また、受給者証を発行するためには、専門医による診断書が必要になることがほとんどです。
条件に該当する場合には、サービスを利用するための受給者証が発行されます。
受給者証を受け取ったら、診断書と受給者証を持って就労定着支援事業所にて契約手続きを行いましょう。
流れ⑤サービスの利用

就労開始から6か月目までは、就労定着支援計画をベースに職場訪問や面談を行い、就労定着支援の具体的な支援内容を検討・決定します。
就労定着支援の本格的な支援は、就労開始から7か月目から利用できます。
サービス利用開始後は、就業中の課題を感じた際には、就労定着支援員に相談して必要な支援を受けましょう。
場合によっては、企業の担当者や医療機関との連携を行うこともあります。
流れ⑥継続的な状況確認
就労定着支援サービスの利用期間は1年ごとに更新されます。
基本的には、最長で3年の支援が受けられます。3年後も支援を受けられるかどうかは、事業所ごとに異なります。
引き続き支援を受ける場合は、その就労定着支援事業所で継続するか、障害者就業・生活支援センターなどに引き継がれるか、いずれかの方法が取られることが一般的です。
就労定着支援を利用するメリット3点
就労定着支援を利用することのメリットを解説します。
メリット①悩みや課題を相談できる

職場の人たちは、就職者本人にどのような課題があるのか、実態を理解できないこともありえます。また、就職者本人も、自身の特徴の伝え方など、わからないこともあるはずです。
そのようなことについて、就労定着支援事業所であれば理解できることが多いです。また、就職先に直接相談しにくいことでも、就労定着支援員であれば相談しやすいでしょう。
特にクローズ就労の人も、職場にバレないよう相談支援を受けられます。
一人で抱え込まなくていいということは、安心感にもつながるはずです。
自分一人で抱え込まず、困り事を解決するためにどうしたら良いか一緒に考えることができる点は、メリットと言えるでしょう。
メリット②生活についての相談もできる
就労定着支援では、仕事に関する悩みだけでなく、生活上の悩みも相談できます。
病気や障害のある人の中には、体調管理やお金の管理に苦手な人もおり、プライベートの問題が仕事に影響することも少なくありません。
そのような悩みも就労定着支援員に相談できます。
メリット③就職先への要望をスムーズに伝えられる

職場への要望などについて、自分の言葉ではうまく伝えられないことでも、就労定着支援事業所が仲介することで、スムーズに伝えられます。
就労定着支援事業所は、どのような問題が起きているのか、就職者と職場の両方の視点で把握し、客観的に双方の状況を把握したうえで、課題に対処できます。
就労定着支援を利用する際の注意点

こちらでも解説しましたが、就労定着支援は、基本的には最長で3年しか利用できない点に注意が必要です。
3年目以降は、支援を行わない事業所もあります。
そうした事業所を利用していた場合、3年以降のサポートは、障害者就業・生活支援センターなど地域の支援機関に引き継ぎが行われます。
しかし、担当者が変わることで、新しい関係性を構築する負担がかかります。
障害内容の理解度に違いがある可能性もあり、同じサポートが受けられるとは限らないことは、あらかじめ意識しておきましょう。
就労定着支援事業所を選ぶときのポイント4選
就労定着支援事業所は、事業所ごとに特色が異なります。自分にあったものを選ぶことが大切です。ここでは、就労定着支援事業所を選ぶポイントについて解説します。
ポイント①自治体や専門機関に支援内容を相談する

1つ目のポイントは「自治体や専門機関に支援内容を相談する」ことです。
就労定着支援の内容(定期面談や個別支援計画の作成など)は、事業所ごとに、重視ポイント、方針、雰囲気、具体的なアドバイスなどに個性があります。
あくまで例として、「お勤め先との環境調整や、仕事の進め方に関する助言・指導に重点を置いている事業所」もあれば、「体調管理やメンタル面のサポートといった、生活面の支援を重視している事業所」もあるでしょう。
そうした支援の違いなどを知るためにも、自治体や専門機関などの詳しい人に相談することをオススメします。
具体的には障害者生活・就業センターや地域障害者職業センターなどで、無料相談が可能です。
就労定着支援に関する情報収集も兼ねて、そうした自治体や専門機関に在籍する人の意見を取り入れることも、あなたに合った事業所を選ぶポイントになります。
ポイント②あなたの病気や障害の対応状況はどうか
「あなたの病気や障害の対応状況はどうか」も選び方のポイントです。
就労定着支援を実施している事業所には、通常、支援に関わる実務経験や資格を有する「サービス管理責任者」が在籍しています。
その上で、社会福祉士や臨床心理士などの専門員が所属している事業所もあります。
精神障害のある人であれば精神保健福祉士、身体障害の場合であれば介護福祉士など、専門職の在籍があるかどうかを確認するのも、大切なポイントの一つです。
こうした専門員が所属していると、あなたの病気や障害の実情に即した支援を受けられる可能性が高くなります。
とはいえ、「有資格者がいなければ、あなたに向いていない」ということではありません。有資格者がいなくても、基本的には各病気や障害に対応することが可能なはずです。
「資格の有無」にこだわらず、「あなたの病気や障害への対応状況や実績はどうか」を確認してみましょう。
ポイント③雰囲気や支援員との相性が合っているかどうか

3点目は、「雰囲気や支援員の性格があなたに合っているかどうか」です。
カウンセリングや通院と同様に、事業所の雰囲気や支援員との相性はあります。
事業所との定期面談や通所を無理なく続けるには、実際の様子を体験し、あなたの性格と事業所の雰囲気、または支援員の性格が合っているかという点は、確認しましょう。
また、事業所の雰囲気を掴むために、事業所に通っている人が、どんな様子で過ごしているかを、確認することもおすすめです。
ぜひそうした機会を活かして、あなたの性格とマッチした支援員が多くいそうな事業所を探してみてください。
ポイント④あなたの働き方や職種の定着実績の状況はどうか
最後のポイントは、「あなたの働き方や職種の定着実績の状況はどうか」です。
例えば、「一般枠で、プログラマー」という働き方をしている人の場合、同じような働き方・職種の定着実績が豊富な事業所に通うことで、より適切なサポートを受けやすいでしょう。
逆に「障害者雇用枠に強いけれど、一般枠の実績があまりない事業所」や「軽作業職の実績は豊富だけれど、専門的な職業に詳しくない事業所」などでは、適切なサポートが受けられない可能性があります。
問い合わせの際に、自分の職種での就労定着支援実績があるかを確認しましょう。
ただし、「実績がなければ、適切なサポートは絶対に受けられない」というわけではありません。
全体的な雰囲気や方針によっては、あなた向きのサポートを受けられる可能性はもちろんあります。
就労定着支援を実施している団体6選
就労定着支援を実施している団体は、「以下の6団体のうち、就労定着支援の指定を受けている団体」です。それぞれ、解説します。
団体①就労定着支援事業所

就労定着支援事業所は、就労定着支援を行う事業所です。
ただし現状では、「就労定着支援だけを専門で行っている」というよりも、「就労移行支援事業所が、就労定着支援事業所を兼ねている」というケースが多いようです。
事業所を探す際には、探し方としては、自治体の障害福祉担当の窓口や、インターネット検索の他に、専門のウェブサイト(例:公益財団法人東京都福祉保健財団が運営する「福ナビ」)もあります。
団体②就労移行支援事業所
就労移行支援事業所とは、一般企業への就職を目指す、病気や障害のある人たち向けに、生活面から仕事面に至るまで、包括的な障害福祉サービスを提供している支援機関です。
相談は無料ですので、支援内容に興味を抱いた事業所に一度、詳細をお問い合わせいただくとよいでしょう。
就職支援から就職後の定着まで同じ事業所にサポートして欲しい場合に特におすすめできます。
就職前からサポートを受けていれば、支援者があなたの性格や特性を理解しているため、スムーズな定着支援が受けられるでしょう。
就労移行支援事業所の詳細は、下記コラムをご覧ください。
団体③就労継続支援事業所(A型、B型)

就労継続支援事業所(A型、B型)では、現時点で一般企業への就職に関して困難を抱える障害のある人に、事務業務や軽作業などの実業務の機会の提供や必要な能力の向上を行う職業訓練サービスを提供しています。
就労継続支援事業所(A型、B型)について詳しく知りたい方は下記コラムをそれぞれご覧ください。
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、うつ病や発達障害などの人のための就労移行支援事業所です。
- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月
新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。
団体④生活介護事業所
生活介護事業所とは、入浴・排せつ・食事などの介護や援助が必要な障害のある人を対象に、必要な介護や日常生活面の助言・相談を行っている支援施設です。
創作的活動・生産活動の機会の提供や、身体機能・生活能力の向上のために必要な支援なども実施しています。
団体⑤自立訓練事業所

自立訓練事業所は主に、「機能訓練」を目的とする事業所と、「生活訓練」を目的とする事業所に分かれます。
機能訓練については、事業所に通う通所型や、事業所に滞在して行う宿泊型、支援者がお宅を訪問する訪問型などがあります。
理学療法・作業療法・リハビリテーションといった機能訓練を施したり、生活面での相談・助言を行ったりしています。
生活訓練についても、機能訓練と同様に通所型、宿泊型、訪問型があります。
入浴・排せつ・食事といった自立した日常生活を営むために必要な訓練や、生活面での相談・助言を行います。
団体⑥障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、障害のある人の就業面と生活面に関する相談・支援を行う支援機関です。「なかぽつ」や「なかぽつセンター」と呼ばれることがあります。
厚生労働省や都道府県から事業を委託された、各地域で活動している社会福祉法人やNPO法人が運営しています。
まとめ:自分に合った就労定着支援事業所を探してみてください
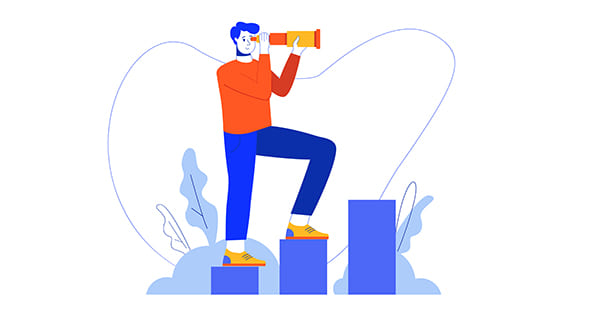
この記事では、就労定着支援とはどのようなものか、支援内容、メリット、手続きの流れ、選ぶときのポイントについて解説しました。
就労定着支援は、就業してからの課題を解決するための支援が受けられ、長く会社に働き続けたい場合におすすめできる選択肢の1つです。
ただし、就労定着支援事業所によって支援内容や強みが異なるため、自分に合った事業所かどうか、慎重に見極める必要があります。この記事を参考に、自分に合った就労定着支援事業所を探してみてください。
就労定着支援の利用料金はいくらですか?
就労定着支援の利用料金は、厚生労働省が定めており、事業所による違いはありません。
詳細はこちらをご覧ください。
就労定着支援を利用するまでの流れを教えてください。
一般論として、次のような項目が挙げられます。
詳細はこちらをご覧ください。
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
執筆寺田淳平
てらだ・じゅんぺい。
高校2年の春から半年ほど不登校を経験。保健室登校をしながら卒業し、慶應義塾大学に入学。同大学卒業後の就職先(3,500人規模)で人事業務に従事する中、うつ病を発症し約10か月休職。寛解・職場復帰後、勤務を2年継続したのち現職のフリーライターに。
2019年に一般財団法人職業技能振興会の認定資格「企業中間管理職ケアストレスカウンセラー」を取得。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→




