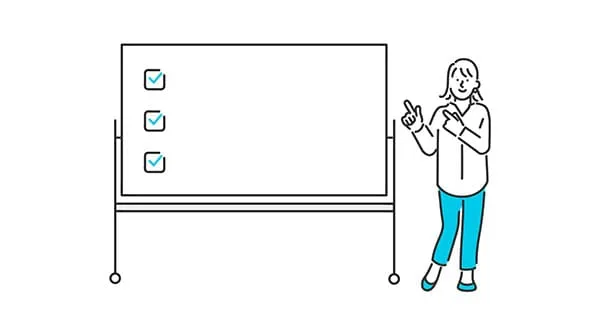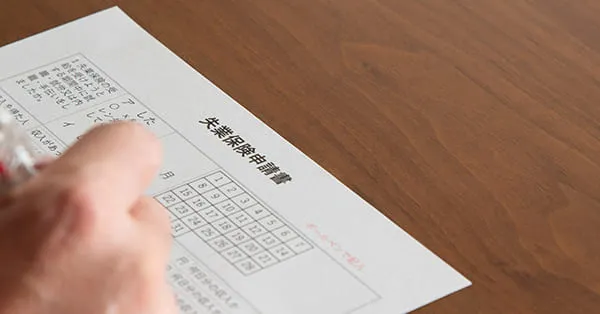てんかんのある人に向いてる仕事 就労できない仕事や仕事する上での注意点を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
てんかんのあるあなたは、以下のことでお悩みではありませんか?
- てんかんがあるために就職や転職ができないのではないか
- てんかんがあると、仕事に就いても続かないかもしれない
- 職場で「てんかんだから仕事ができない」と思われてしまう…
発作や偏見への不安は当然のこと。しかし、服薬や健康管理によって、てんかんと上手につきあい、自分に合った働き方を選ぶことは十分可能です。
このコラムでは、てんかんのある人に向いてる仕事や向いてない仕事、就労できない仕事、仕事を探すときのポイント、仕事をする上での注意点、利用できる支援制度、支援機関を解説します。
あわせて、てんかんのある人を雇用する事業者が意識しておくべきポイントを解説します。
てんかんのあるあなたにあった仕事選びの参考になれば幸いです。
目次
てんかんとは?

この章では、てんかんの概要と分類、発作の種類と症状、治療法について解説します。(参考:厚生労働省「てんかん対策」、公益社団法人日本てんかん協会「てんかんについて」、児玉クリニック「てんかん発作の原因」))
てんかんの概要
てんかんとは、意識を失ったりけいれんが生じたりする「てんかん発作」と呼ばれる症状が繰り返される病気のことです。
てんかん発作とは、脳にある神経細胞が異常な電気活動をすることで引き起こされる発作のことです。
てんかん発作の主な症状は、以下のとおりです。
- 体の一部が固くなる(運動神経)
- 手足がしびれたり耳鳴りがしたりする(感覚神経)
- 動悸や吐き気を生じる(自律神経)
- 意識を失う
- 言葉が出にくくなる(高次脳機能)
てんかんのある人は1000人に5〜8人(日本全体で60万〜100万人)と言われており、乳幼児から高齢者のいずれの年齢層でも発症します。
てんかんの種類と原因
てんかんは、以下の2種類に分けられます。
- 部分てんかん(局在関連てんかん):大脳の片側の一部が興奮するてんかん
- 全般てんかん:両側の大脳半球の広範囲に興奮が起きるてんかん
さらに、てんかん発作を引き起こす原因によって、以下の2種類に大きく分けられます。
- 特発性てんかん:明らかな脳の病変が認められない場合のてんかん
- 症候性てんかん:明らかな病変が認められる場合のてんかん
てんかん発作の種類と症状

てんかん発作には複数の種類があり、異常な電気活動を起こしている脳の部位に対応した様々な症状が出現します。
代表的なものとして、以下のような症状があります。
- 単純部分発作:顔がピクピク、幻聴や変なにおいを感じるなどの症状が起こる意識が保たれる発作。
- 複雑部分発作:意識を失う、全身けいれんは起こらない発作。
- 強直間代発作(きょうちょくかんたいほっさ):全身が硬直したあと、ガクガクと激しく体が震える発作。
- 強直発作(きょうちょくほっさ):グーっと力が入る症状のみの発作。
- 欠神発作(けっしんほっさ):数秒〜数十秒の間意識を失う発作。
- ミオクロニー発作:両手または両足が一瞬だけピクッと動く発作。
てんかん発作は、ほとんどの場合数秒〜数分間で終わりますが、ときには数時間以上続くてんかん重積状態も起こります。
例えば「全般性強直間代発作」では多くの場合、意識がなくなり、全身が硬くなった後(強直相)、全身をガクガクとさせます(間代相)。症状が軽い場合には、一方の腕や顔の一部だけが数秒間だけ固くなるだけの人もいます。
また、突然反応がなくなり数秒間だけ宙をみつめるのが発作の症状の人では、転倒したりけいれんしたりすることもなく、他者からは気づかれないかもしれません。
てんかんの治療法

てんかんは、抗てんかん薬による治療が一般的です。
抗てんかん薬は「てんかん」の原因を取り除くことはできませんが、てんかん発作を起こりにくくします。
抗てんかん薬には様々な種類があります。発作の種類や年齢や性別、副作用などのその他の状況により、使用する抗てんかん薬は異なります。
抗てんかん薬を内服することで、大部分の方は発作が抑制され、さらに一部の方では数年後には薬をやめることができるようになります。
抗てんかん薬を内服しても発作が充分に抑えられない場合には、脳外科手術により発作が抑制されることもあり、食事療法や迷走神経刺激術といった他の治療により発作が軽減する方もいます。
てんかんのある人に向いてる仕事

「てんかんがあると仕事はできない」と考える人がいますが、決してそんなことはありません。
結論から言いますと、「てんかんだから向いてる仕事」というものはありません。てんかんのない人と同じように、自分の適性や希望に合った職業を選ぶことが可能です。
違う言い方をすると、「てんかんだから〇〇業界に進むべき」「てんかんだから〇〇の仕事しかできない」と狭い視野で考えなくてもいいということです。
確かに、こちらで解説しますが、航空機パイロットなど法律上てんかんのある人が就労できない仕事は存在します。しかし、多くの職業ではそのような制限はありません。(参考:東和薬品株式会社「てんかんと就労」)
自身のてんかんの症状について理解を深めることは大切ですが、てんかんであることにこだわりすぎず、幅広い視野を持って仕事を探すことができます。
そして、「てんかんに注意しつつ、あなたに向いた仕事を探す」ためには、就労移行支援事業所など、てんかんのある人の就労をサポートする支援機関を積極的に利用することをオススメします。
てんかんのある人に向いてない仕事

こちらで、てんかんがあるからと言って特定の仕事が向いてるとは限らないとお伝えしましたが、オススメできない仕事も一部あります。
この章では、てんかんのある人にオススメできない仕事を紹介します。
てんかん発作以外の、何らかの「障害」「特性」「病気」が併存する場合はなおさらです。
ご自身の発作の性質と仕事の特性をよく考えて、無理のない仕事を選びましょう。
仕事①自動車の運転を伴う仕事
てんかんのある人も、一般的には「運転に支障するおそれのある発作が2年間ない人」は運転免許を取得可能です。
ですが、運転手・ドライバーや自動車による営業職など、体調に関わらずいつ運転するかわからない仕事や、常に運転が必要となる職種は、避けた方がいいかもしれません。
仕事②高所作業や危険を伴う機械操作のある仕事
オススメできない仕事の2つ目は、「高所作業や危険を伴う機械操作のある仕事」です。
転倒や意識消失を伴う発作がある場合、けがや事故に繋がりかねないためオススメしません。
仕事③交替勤務、夜間を含むシフト勤務がある仕事
交替勤務、夜間を含むシフト勤務がある仕事もオススメしません。
睡眠不足が発作の誘因となる場合には避けた方が無難でしょう。
てんかんのある人が就労できない仕事
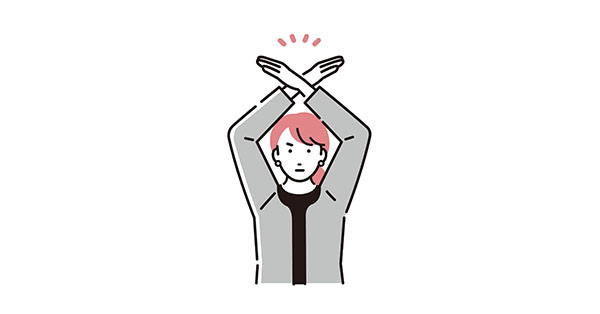
この章では、てんかんのある人が就労できない仕事を解説します。
「一般的に、よく見かける職種」とは異なるものもありますが、参考としてご覧ください。
てんかんのある人は、以下の職業に就くことができません。(参考:障害保健福祉研究情報システム「障害者に係る欠格条項(63制度)一覧」)
- 自動車の運転免許が必要な仕事航空機に乗り組んでその運航を行う航空従事者
- 船員
- 銃砲又は刀剣類の所持が必要な仕事狩猟免許が必要な仕事
- その他、精神障害に関する欠格条項がある仕事
こちらでも解説しましたが、運転免許の取得自体に、てんかんに関する条件があります。
また、鉄砲・刀剣の所持自体にも、てんかんに関する条件があるため、銃砲又は刀剣類の所持が必要な仕事は就労できません。狩猟免許も、てんかんに関する条件があるため同様です。
ただし、例外が存在する場合もあります。例えば、船員については、てんかんのある人のうち、「船内において治療の見込みがなく、かつ、船内労働に適さないと認められる者」以外はなることができます。
希望の職種に関する制限と例外の有無や該当可能性については、支援者とともに調べてみることをオススメします。
加えて、法律は変わるものです。例えば、かつてはてんかんのある人が取得できなかった美容師免許・理容師免許は、法律の改正によって、取得可能になりました。
「現在就けない職業には、将来的にも絶対に就けないわけではない」ということも、覚えておくと役立つかもしれません。
てんかんのある人が仕事を探すときのポイント3点
この章では、てんかんのある人が仕事を探すときのポイントを3つを解説します。(参考:てんかん情報センター「就労と医療」)
就労について、あなた一人で対策を考える必要はありません。
医師や、就労移行支援事業所などの支援機関と話をすることで、「あなたに適した対策」が見つかります。
ポイント①「てんかんだから」と就労をあきらめない

「てんかんだから」といって、就労をあきらめないようにしましょう。
たしかに、てんかんの「管理」や一般的な日常生活が可能で、就労できる能力がありながらも、実際に就労先を見つけることに困難を伴う場合はあります。
てんかんに配慮した雇用体制が整っていない企業があることも事実です。
しかし、てんかんへの理解は広まりつつあり、例えば美容師など、以前はてんかんのある人が就くことができなかった仕事にも就けるようになってきています。
また、てんかんのある人の就労をサポートするサービスも増えています。
そして、てんかんがありながら仕事に就き、社会で活躍している方も多くいます。
てんかんがありながらの就労が困難な場合もあることは事実ですが、あきらめないで仕事を探す気持ちを持つようにしましょう。
ポイント②就労を急がない
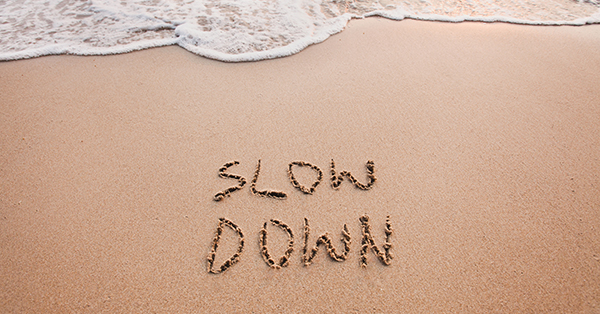
こちらの内容をくつがえすわけではありませんが、「就労をあきらめないこと」は意識しつつも、就労を急がない、あせらないようにしましょう。
「仕事をしたい」という気持ちはよくわかります。
ですが、就労のためには、「ある程度の、落ち着いた体調や日常生活」などが必要です。
また、これまでに就労経験がない方なら、就職活動の前に「ある程度のビジネスマナーやビジネススキル」を身につけた方がうまくいく場合もあります。
就きたい仕事によっては、専門的な技能や資格を身につける必要もあるでしょう。
自分の状態でどのような仕事ができるのかわからなければ、職業適性検査を受けたり、発作の状態についてよく主治医と話をしてじっくりと考えたりする時間も大切です。
あせらずに、「今、自分が就職できるか」「転職活動をしても大丈夫か」「今、自分に必要なことは何か」などを考えてください。
相談の結果、残念ながら、「今すぐの就職・転職」が困難なこともあるでしょう。
そのような方も、悲観的にならずに、現在の状態で可能な社会参加の方法を考えましょう。例えば、ボランティアやサークル活動など、「人とのつながり」は「心の安定」につながります。
また、拘束時間の長い正規雇用を目指すのが難しい体調でも、アルバイトやパート、契約社員などの勤務時間の少ない非正規雇用なら体調と両立できるかもしれません。
非正規雇用を通じて「働くことに慣れること」「社会とのつながりを持つこと」は、検討してもよいのではないでしょうか。
そうして治療も並行するうちに、体調も落ち着き、改めて「正規雇用を目指すべきか」なども考えられるようになるでしょう。
金銭面での不安がある方は、障害年金などの制度を利用することも考えましょう。
ポイント③てんかんのことを就職先に言うべきかどうかを考える
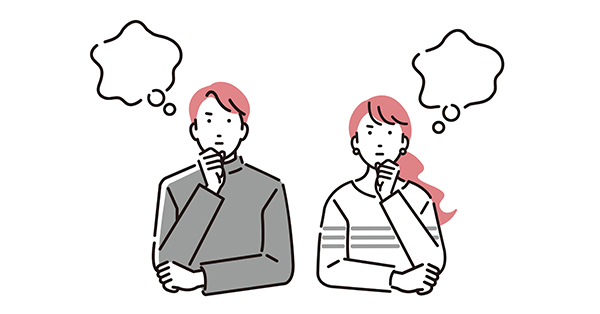
繰り返しになりますが、てんかんのある人が仕事をするにあたっては、周囲の理解が大きな力になると同時に、偏見がないわけではないこともまた事実です。
就職先や、就職活動中の相手先に、ご自身のてんかんのことを伝えるかどうかを検討しましょう。
基本的には、「てんかんのことを伝えなくてはいけない」という決まりはありません。
もちろん、こちらで解説したてんかんのある人が就労できない仕事や取得できない資格について、「てんかんではない」などと虚偽の申請をすることは、しないようにしましょう。
発作の頻度が少なく、生活や仕事をする上で発作がそれほど障害とならなければ、職場にはてんかんのことを伝えないのも一つの方法です。
自分の病気について言わずに就職することを、一般に「クローズ就労」と言い、伝えてから就職することを「オープン就労」と言います。
ただしクローズ就労の場合でも、「てんかん発作は、仕事中には必ず起きない」という保証はありません。発作が起きたときの説明は用意しておくようにしましょう。
一方、発作が頻繁にみられたり、発作による受傷の危険性があったりする方は、オープン就労の方がいいでしょう。
周囲の理解が深まれば、事故などを防げます。また、心理的にも安心して働けるようになります。就職活動の段階でどのように説明するかを、よく考えましょう。
なお、オープン就労を行う場合には、「障害者雇用」での就職も選択肢に入ります。
障害者雇用とは、障害のある労働者が、障害の特徴や内容に合わせて働きやすくするため、安心して働くための雇用枠のことです。
オープン就労やクローズ就労、障害者雇用の詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
てんかんのある人が仕事をする上での3つの注意点

この章では、てんかんのある人がスムーズに仕事をするための注意点を解説します。(参考:東和薬品株式会社「てんかんと就労」)
てんかんのある人が仕事をする際には、以下のような不安を感じるケースが多いようです。
- 「てんかんがあるから仕事ができない」とみなされるのではないか
- てんかん発作などで職場に迷惑がかかるのではないか
- てんかんを理由にクビになったり、仕事が続かなかったりするのではないか
仕事上の不安やストレスは、てんかんにも良い影響を及ぼしません。
これらの不安を少しでも解消できるよう、以下の注意点に気をつけましょう。
注意点①自身のてんかんの症状を理解する
てんかんの症状や発作の出方は一人ひとり異なります。
自分のてんかんのタイプや、発作が出やすい状況を理解し、必要に応じて他人に伝えられるよう整理しておきましょう。
特に、発作の出方や発作時の対応、緊急搬送が必要な場合の有無は大事です。
自分のこととはいえ、不明点があるのは当然のこと。分からないことは受診のタイミングで主治医に確認しておくと安心です。
注意点②心身のコンディションを整える
不規則な生活や心身の疲れは発作の原因につながります。忙しくても生活リズムを乱さないようにしてください。
また、睡眠不足を避けることやお酒の飲み過ぎに注意すること、ストレスをためないことなどを心がけましょう。
発作がコントロールできていれば、適度な運動をしても大丈夫です。
注意点③自分に合った働き方を探す
てんかんがあっても、症状とうまく付き合いながら働いている人はたくさんいます。
就労にあたっては、通院や服薬が継続できること、過労にならない程度の業務量であることを念頭に、自分に合った働き方を探していきましょう。
てんかんのある人が利用できる支援制度8選

てんかんのある人が医療費などをすべて負担するのは大変なことです。また、休職・退職するときや、仕事探しを当面断念せざるを得ないこともあるでしょう。
この章では、国や自治体による支援制度を紹介します。賢く利用することで、経済的な負担を減らすことが可能です。
何度も繰り返すとおり、お勤め先、医師、サポート団体、お住まいの自治体などとも話しつつ、次のような制度の利用を考えましょう。
なお、てんかんのために休職・退職した場合、「国民年金保険料納付免除の申請」や「退職による健康保険の切り替え」の手続きを行わなければ、不利益をこうむることがあります。それぞれ確認しましょう。(参考:独立行政法人静岡てんかん・神経医療センター「病気で仕事を休んだり、退職するとき、利用できる制度はありますか?」)_
支援制度①自立支援医療制度
自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療に関する医療費の自己負担額を軽減する公費負担の支援制度のことです。てんかんもその支援の対象です。(参考:厚生労働省「自立支援医療について」、厚生労働省「自立支援医療制度の概要」、東京都福祉保健局「自立支援医療(更生医療)」)
通常、医療保険による医療費の自己負担額は3割です。自立支援医療制度を利用すれば、原則1割まで軽減することができます。この制度は、指定の医療機関・薬局のみで利用可能です。
さらに、自己負担額には上限が設定されています。1割負担であっても、月額の上限以上となる金額は、原則として負担を免除されます。ただし、世帯の総所得額によっては、自己負担額が変動したり、対象外になったりする場合があります。
また、費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない場合や所得の程度に応じて、さらに軽減措置が行われます。
自立支援医療は、下記の3種類に分けられます。
- 精神通院医療:精神疾患の治療など
- 更生医療:身体障害に関わる治療など
- 育成医療:身体障害がある子どもに関わる治療など
特定の精神疾患がある人以外に、身体障害者手帳を持つ人なども対象です。
具体的な支援内容や条件、名称は、自治体によって異なります。
気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。
支援制度②高額療養費制度
高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費について、自己負担限度額を超えた分の払い戻しを受けられる制度のことです。(参考:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」、てんかん情報センター「てんかんのための医療費の補助制度を教えてください」)
入院の場合は「限度額認定証」の申請をすることで、自己負担限度額までの支払いとなります。
支援制度③心身障害者医療費助成制度
心身障害者医療費助成制度とは、精神または身体に重度な障害のある人の福祉の増進を図る目的で、各自治体が医療費の一部または全部を助成する支援制度のことです。「マル障」とも呼ばれています。(参考:東京都福祉局「心身障害者医療費助成制度(マル障)」、渋谷区ポータル「医療費の助成 | 障がい者の医療」)
一般的に、各種医療保険の自己負担から一部負担金を差し引いた金額または全額が助成されます。
自治体によって支援内容や受給条件などのルールが異なります。
気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。
支援制度④傷病手当金

傷病手当金とは、てんかんを含む病気やケガ、障害のために仕事を休む場合に「健康保険」の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた支援制度のことです。国民健康保険の加入者は対象外です。(参考:全国健康保険協会「傷病手当金」、全国健康保険協会「傷病手当金について」)
傷病手当金は、退職前の在職中に受給するお金です。ただし、一定の条件を満たせば、退職後も継続して受給できます。
傷病手当金の受給対象は、病気やケガ、障害によって就労不能であり、十分な給与が支給されない人です。そのため、医師の診断書が必要です。
傷病手当金の窓口は、全国健康保険協会や各健康保険組合、各共済組合です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の例では、以下のすべての条件を満たしている必要があります。
- 業務外の病気やケガ、障害で療養中であること
- 療養のため労務不能であること
- 4日以上仕事を休んでいること
- 給与の支払いがないこと
各条件には、さらに「給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給される」などの補足が付いています。
そのため、対象となる協会・組合に問い合わせたりウェブサイトを参照したりして、しっかりと条件を確認することが大切です。
また、傷病手当金の受け取りのためには、基本的にてんかんなどの病気であることを証明する診断書の提出が必要になります。
具体的な支給額は、対象者の標準報酬月額などによって異なります。
さらに詳しい支給額を知りたいという方は、まずは職場の人事部に一定期間の給与額などを確認した上で、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。
気になる方は、ご自身の加入している健康保険に問い合わせてみましょう。
傷病手当金については、以下のコラムで解説しています。うつ病のある人に向けた内容にはなりますが、参考になるかと思います。ぜひご覧ください。
支援制度⑤失業保険(失業手当、雇用保険給付)
失業保険(失業手当、雇用保険給付)とは、失職した人が就職するまでの一定期間に給付金を支給する支援制度のことです。
原則、以下の2点が条件です。
- 退職までの一定期間、雇用保険に加入していたこと
- 求職活動を行っていること
ここで言う求職活動とは、企業への面接訪問などに限らず、窓口相談や職業訓練も含まれています。それらの活動ができる場合、「就職活動をして労働する」ことができない人でも条件を満たすことは充分可能です。
具体的な受給期間(90日~360日)や金額(在職中の給与の約50~80%)は、その人の状況によって異なります。また、てんかんなどの病気によって求職活動条件を満たせない場合には、受給期間を延長することも可能です。
また、これまで述べてきた失業保険は「基本手当」と呼ばれるものになります。
病気やケガ、障害によって15日間以上、引き続いて求職活動ができない場合や働けない場合は、「傷病手当」という別の給付金を受給することができます。
なお、雇用保険上の傷病手当は、こちらで解説した傷病手当金とは異なることに加えて、両方を同時に受給できない点には注意してください。また、公務員は対象ではないため、注意してください。
申請は、お住まい自治体に設置されているハローワークで行なえます。(参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」)
気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。
失業保険については、以下のコラムで解説しています。うつ病のある人に向けた内容にはなりますが、参考になるかと思います。ぜひご覧ください。
支援制度⑥障害年金
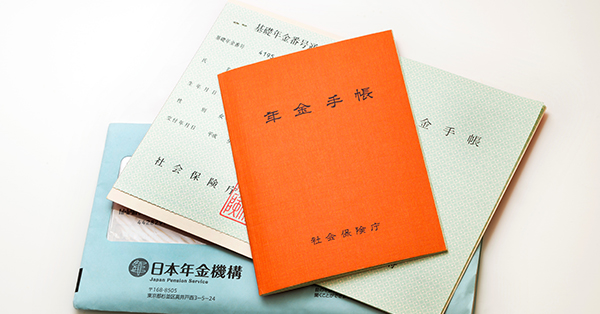
障害年金とは、病気やケガ、障害によって仕事や生活に影響が出た場合に年金加入者が年金を受給できる支援制度のことです。(参考:日本年金機構「障害年金」)
「事故で足を失った」「生まれつき四肢が不自由」「知的障害がある」などのケースだけでなく、発達障害・精神疾患・生活習慣病なども受給の対象になります。
一般的な年金は高齢者にならなければ受け取れませんが、障害年金は現役世代でも受給できることが特徴です。
障害年金は、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。障害厚生年金に関しては、補足的に障害手当金という制度もあります。
気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。
障害年金については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援制度⑦特別障害者手当
特別障害者手当とは、精神または身体に著しく重度な障害があり、日常生活において常に特別な介護を必要とする在宅生活をしている人に対して、必要となる精神的、物質的な負担の軽減を目的に手当を支給する支援制度のことです。(参考:厚生労働省「特別障害者手当について」)
利用できる場合、2023年4月現在では、月額2万7980円を受給できます。
ただし所得制限があり、受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母など)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
申請は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口で行えます。
気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。
支援制度⑧生活保護
生活保護とは、生活に困窮している人や病気やケガ、障害などで就労できない人に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活の保障と自立の助長を目的とした支援制度のことです。(参考:厚生労働省「生活保護制度」)
生活に必要な最低限度のお金を持つことが困難な人がお金を受給できる制度とも言えます。
生活保護で受給できるお金には生活扶助(食費・被服費・光熱費など)や住宅扶助(アパートなどの家賃)、医療扶助(医療サービスの費用など)などがあります。
- 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費など)
- アパートなどの家賃
- 義務教育を受けるために必要な学用品費
- 医療サービスの費用
- 出産費用
- 就労に必要な技能の修得などにかかる費用
- 葬祭費用
また、受給金以外にも、国民年金保険料や住民税、NHK放送受信料などの税金・公共料金の支払いが減免されることがあります。
申請は、お住まいの自治体を所管する福祉事務所で行なえますが、まずは、お住まいの自治体の生活保護を担当する部署・窓口に相談してみてください。
ただし、生活保護は「最後のセーフティネット」とも呼ばれるように、本当に支援が必要な人だけを対象とする支援です。一般的に審査が厳しく、生活保護以外の支援を提案されたり、申請が却下されたりする可能性があるということは、心に留めておいてください。
生活保護については、以下のコラムで解説しています。うつ病のある人に向けた内容にはなりますが、参考になるかと思います。ぜひご覧ください。
てんかんのある人が利用できる支援機関8選

てんかんのある人がてんかんの相談をする際や仕事を探す際には、支援機関を利用することをオススメします。
この章では、てんかんのある人が利用できる支援機関を紹介します。
てんかんに限らず、病気や障害のある人の就労には、様々な助成制度や支援パートナーのような援助があります。
また、紹介する相談先と話をして、自分に向いたところを利用しましょう。(参考:厚生労働省「てんかん対策」)
支援機関①てんかん診療拠点病院
1つ目の支援機関は、てんかん診療拠点病院です。
てんかん診療支援コーディネーターが配置されており、てんかんをもつ方やご家族への支援を行っています。
支援機関②保健所
保健、医療、福祉に関する相談、未治療、医療中断の方の受診など幅広い相談を行っています。
電話、面談による相談があり、保健師、医師、精神保健福祉士などの専門職が対応します。また、相談者の要望によって、保健師が家庭を訪問して相談を行うこともできます。
面談や訪問を希望される場合は事前に電話で予約されることをオススメします。
多くの場合は相談者の居住地の担当保健師が対応します。自分の担当地域の保健師と会っておくと、その後の相談もスムーズに進みます。
支援機関③精神保健福祉センター
精神保健福祉センターは、各都道府県・政令指定都市ごとに1ヵ所ずつあります。(参考:厚生労働省「てんかん対策」)
自治体によっては、「こころの健康センター」などと呼ばれている場合もあります。
精神保健福祉センターでは、精神保健福祉全般にわたる相談を電話や面接にて行っています。規模によって異なりますが、医師や看護師、保健師、精神保健福祉士、臨床心理技術者、作業療法士などの専門職が配置されています。
このほかデイケア、家族会の運営などの事業も行っていますが、精神保健福祉センターによってその内容が異なります。各精神保健福祉センターのWebサイトなどで確認してみてください。
支援機関④就労移行支援事業所

就労移行支援とは、一般企業などへの就職を目指す、てんかんなどの病気や障害のある方向けに、「障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」に基づいて行われる福祉サービスのことです。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
実際のサービスは、国の基準を満たした様々な民間の「就労移行支援事業所」が行います。
就労移行支援事業所では、体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができます。
さらには、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労移行支援事業所は各地にあります。私たち、キズキビジネスカレッジ(KBC)もその一つです。それぞれ特徴が異なるため、気になるところがあれば問い合わせてみてください。
就労移行支援事業所については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、てんかんのある人のための就労移行支援事業所です。
- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月
新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。
支援機関⑤ハローワーク(公共職業安定所)
ハローワーク(公共職業安定所)とは、仕事を探している人に対して、就労に関連するサポートを行っている支援機関のことです。(参考:東京労働局「東京ハローワーク」、厚生労働省「こころの健康サポートガイド」、厚生労働省「ハローワークにおける障害者の就労支援」)
主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示などを行っており、具体的な支援内容は事業所によって異なりますが、一般的には以下のような幅広いサポートを行います。
- 仕事で活かせる知識・技能の習得
- 仕事や私生活で活かせるメンタル面のサポート
- 「どのような仕事や働き方が向いてるのか」のアドバイス
- 転職先候補の業務や雰囲気を体験できる「職場体験実習(インターン)」の紹介
- 履歴書・経歴書・エントリーシートの作成支援
- 面接対策
- 転職後の職場定着支援
ハローワークでは「難病患者就職サポーター」が配置されていることがあります。
「難病患者就職サポーター」は、難病相談支援センターと連携しながら、就職を希望する難病の方に対して、症状の特性を踏まえたきめ細かな就労支援や、在職中に難病を発症した方の雇用継続などの総合的な支援を行っています。「海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん」など対象となるてんかんもあります。(参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「難病の方の就労を支援しています」)
ハローワークで求職登録を行うと、障害の特性や希望職種に応じた職業相談を受けられます。てんかんがあることや障害のある人向けの求人を探していることを伝えると、てんかんのある人に向いてると思われる求人情報を紹介してもらえます。
ほかにも、「てんかんがある状態でどのように就職活動をすればよいのか?」「面接や履歴書にはてんかんの経験をどのように記載すればよいのか?」など、てんかんのある人の就職活動や履歴書の書き方、面接でのてんかんの伝え方など、細かい疑問も解決できます。
また、ハローワークには、住まいや生活に関する総合相談を行う窓口もあります。経済面や生活面などについても幅広く相談できるため、心配がある場合は相談してみましょう。
支援機関⑥地域障害者職業センター

地域障害者職業センターとは、病気や障害のある人に対して、職業評価や職業指導、職業準備訓練、職場適応援助などの専門的な職業リハビリテーションを提供する支援機関のことです。(参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センターによる支援」、厚生労働省「地域障害者職業センターの概要」)
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しており、障害者雇用促進法に基づいて、全国47都道府県に設置されています。
ハローワークや医療・福祉機関と連携しているため、仕事に関する相談や訓練、復職するためのサポートを行っています。
病気や障害に悩む当事者だけでなく、障害のある人を雇用する事業所に対して、雇用管理に関する相談・援助も行っています。
仕事を両立したい人や就労状況について相談したい人におすすめです。
支援機関⑦障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターとは、雇用や保健、福祉、教育に関する関係機関と連携し、障害のある人の雇用の促進・安定を目的とした一体的な支援を行っている支援機関のことです。(参考:厚生労働省「障害者雇用促進法制の整備について」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」)
障害のある人の就職活動の支援や求人の紹介、職場定着のためのサポートなどを行います。
就労面だけでなく、金銭管理などの経済面や生活面のことまで、日常および地域生活に関する支援も行っています。
生活習慣や金銭管理、健康管理などについても幅広く相談できるため、生活面のサポートも受けたい人におすすめです。
2023年4月1日時点で、全国に337箇所設置されています。
支援機関⑧精神障害者社会適応訓練事業
精神障害者社会適応訓練事業とは、障害のある人が、支援機関のサポートを受けながら、自治体が認めた事業所などでの就労訓練や社会経験を通じて自立を図ることを目的とした事業のことです。(参考:大阪府「大阪府精神障がい者社会生活適応訓練事業」)
自治体によって制度の詳細や申込み方法は異なります。
お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口に相談してみてください。
てんかんのある人を雇用する事業者が意識しておくべきポイント2点

この章では、てんかんのある人を雇用する事業者に向けて、雇用する際の注意点について解説します。
ポイント①てんかんのある人を雇用する際の配慮
てんかんのある人を雇用する事業者は、人によっててんかんの症状は様々であることを知っておく必要があります。
症状によっては、合理的配慮が必要のない人もいます。
相手の病状・症状をよく聞いて、次のようなことへの考慮を心がけるようにしましょう。(参考:独立行政法人国立病院機構 静岡てんかん・神経医療センター「てんかんのある人に就労の機会を!」)
- 症状・病状は、合理的配慮が必要な程度か
- 必要な場合、具体的にどのような配慮が必要か
- 症状・病状に鑑みて、どのような仕事を任せるべきで任せるべきではないか
- 発作が起こった場合の対処法はあるか
- 通常のシフト内で、通院や治療のための休日を確保可能か
- 職場への理解を促すかどうか
- 本人の許可を得て、職場でてんかんのことを周知するかどうか
ポイント②てんかんのある人が仕事中にてんかん発作を起こした場合の対応

てんかん発作は、突然起きるものです。仕事中にてんかん発作が起こる可能性も十分にあります。
てんかん発作のある人は、不安や緊張を感じながら生活しているのです。
日本てんかん協会によれば、発作が起きたときに大切なのは以下の3点です。(参考:公益社団法人日本てんかん協会「発作の介助と観察」)
- 気を落ち着かせ、冷静になる
- 騒ぎ立てない
- 多くの場合、すぐに救急車を呼ぶ必要はない
大きなけいれん発作が起きた場合は、安全を確保するために次のことを行ってください。
- 火、水、高い場所、機械のそばなど、危険な物・場所の近くから遠ざける
- 頭の下にクッションを入れるなど、けがをしないように気を配る
- 衣服の襟元をゆるめ、ベルトをはずす
- 眼鏡、ヘアピンなどけがをする可能性のあるものをはずす
加えて、以下のようなときは、医師による処置が必要です。救急車で近くの病院を受診してください。
- けいれんのあるなしに関わらず、意識の曇る発作が短い間隔で繰り返す
- 発作と発作の間で意識が回復していない状態のまま繰り返す
- 1回のけいれん発作が5分以上続き止まらない
まとめ:必要なサポートを受けることが大切です

てんかんがあっても、自分に合った仕事で長く働き続けることは十分可能です。
そのためには受診や治療を継続し、必要なサポートを受けることが大切です。
てんかんで働けない期間があっても気に病む必要はありません。「将来のための大切な準備期間」ととらえ、支援制度を賢く利用しながら体調を整えていきましょう。
このコラムが、あなたが症状や体調と向き合いながら、自分らしく働くためのお役に立てたら幸いです。
てんかんとは、どんな病気なんですか?
てんかんとは、意識を失ったりけいれんが生じたりする「てんかん発作」と呼ばれる症状が繰り返される病気のことです。
てんかん発作とは、脳にある神経細胞が異常な電気活動をすることで引き起こされる発作のことです。
詳細については、こちらで解説しています。
てんかんに向いてる仕事を教えてください。
「てんかんだから向いてる仕事」というものはありません。
てんかんのない人と同じように、自分の適性や希望に合った職業を選ぶことが可能です。
詳細については、こちらで解説しています。
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
執筆寺田淳平
てらだ・じゅんぺい。
高校2年の春から半年ほど不登校を経験。保健室登校をしながら卒業し、慶應義塾大学に入学。同大学卒業後の就職先(3,500人規模)で人事業務に従事する中、うつ病を発症し約10か月休職。寛解・職場復帰後、勤務を2年継続したのち現職のフリーライターに。
2019年に一般財団法人職業技能振興会の認定資格「企業中間管理職ケアストレスカウンセラー」を取得。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→