発達障害グレーゾーンとは? 仕事術や仕事探しのコツ、子どもに対する支援をADHD/ASD/LDの傾向別に解説

近年、「発達障害グレーゾーン」という言葉を聞く機会が増えているかと思います。
あなたは下記のようなことで悩んでいませんか?
- 発達障害のグレーゾーンという言葉を聞くけど、どういうことを指すの?
- 子どもの様子が気になっているが、発達障害かどうかわからない
- 発達障害グレーゾーンかもしれないが、どんな仕事が向いているのか
この記事では、発達のグレーゾーンの人々の症状から、困りごとに対する支援と向いている仕事まで詳しく解説していきます。
目次
発達障害グレーゾーンとは

そもそも発達障害とは、生まれつきの脳機能の発達に偏りなどが生じることで、日常生活や社会生活に影響が出ている障害・状態です。
発達障害がある人は、コミュニケーションや対人関係をつくるのが苦手です。また、その行動や態度は「自分勝手」とか「変わった人」「困った人」と誤解され、敬遠されることも少なくありません。
その原因は、親のしつけや教育の問題ではなく、脳機能の障害によるものです。
世間的に簡単なこととされていること事でも、発達障害のある人には不得手であることが多く、それにより生きづらさを感じている方も少なくありません。
発達障害には大きく分けて3つの種類があり、それぞれ症状の違いがあります(詳しくはこちらの章で解説します)。
加えて、複数の発達障害が併存するケースもあります。(参考:政府広報オンライン「発達障害って、なんだろう? | 暮らしに役立つ情報」)
①発達障害のグレーゾーンの概要
発達障害の「グレーゾーン」とは、発達障害と同じ特性や傾向がいくつか認められるものの、診断基準を全て満たすほどではないため発達障害と診断されるには至らない状態を指します。
つまり、医学的に正式な診断名称ではありません。
「発達障害であると確定診断をつけることができない状態」を、発達障害の「グレーゾーン」と表現しています。
また、「DSM-5の改訂とグレーゾーンの子ども達の支援」(鍛治谷,2015)によると、「保育または教育の場で不適応な行動が見られているものの、診断がついていなかったり未受診だったりする―気になる行動がみられるのに診断がみられない子どもの一群を指す―と言われています。(参考:鍛治谷静「DSM‐5 の改訂とグレーゾーンの子ども達の支援/四條畷学園短期大学紀要 48」)
※DSM-5(「精神疾患の診断・統計マニュアル」):正式名称は、「Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders」。米国精神医学会が発行しており、精神疾患の基本的な定義を記したものです。
②発達障害グレーゾーン=「症状が軽い」ではない

発達障害グレーゾーンとは症状が軽いから「グレーゾーン」というわけではありません。複数ある診断基準を満たしていない場合を指します。
つまり、発達障害の診断を受けた人と同等もしくはそれ以上に特性が強く出る人もいます。
診断に必要な基準を90%満たしていたとしても発達障害グレーゾーン、30%しか満たしていなかったとしても発達障害グレーゾーンとなります。
そのため、本人が日常生活や社会生活上の困難・生きづらさがある点を認識することで診断されることもあります。
さらに、発達障害の特性のあらわれ方は、個々人によって「ムラ」があります。また、同じ人であっても環境や年齢などにより変化します。
③発達障害であると「診断がつかない」場合

「受診するタイミング」や「今は発達障害の診断基準を満たしているが、幼少期の記憶が曖昧でそういった症状があったか不明である場合」によって、発達障害の診断がつかない可能性があります。
自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害(ASD)の診断名にある「スペクトラム」とは、「連続体」という訳であり、それは、症状が全く表れない健常な状態から重度な状態までは連続している、という考え方です。
診断名による線引きではなく、症状の重さでその人の困りごとを捉えることを意味しています。そのため、特性による症状や困りごとを抱えている場合は、自身の特性に合わせた工夫を行ったり、周囲に対し適切な支援を求めていったりすることも大切です。
④発達障害グレーゾーンは障害者手帳を取得できない

発達障害に関連した障害者手帳の発行には医師による確定診断が必要です。そのため、発達障害グレーゾーンの人は取得することができません。
「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類の手帳の総称です。障害の種類によって、日常生活や仕事における困難や支援を必要とする人に対して発行される手帳です。障害者手帳を取得することで、医療費の負担減や税金の控除、割引等のサービスなどが受けられるといったメリットがあります。
詳しくは下記のコラムをご覧ください。
障害者手帳の3種類のうち、発達障害の場合は「精神障害者保健福祉手帳」。発達障害と知的障害が見られる場合は「療育手帳」の申請対象となる可能性があります。
確定診断が出ていない発達障害グレーゾーンの場合は取得対象外とされています。
⑤発達障害に関して正確な診断を受ける方法

発達障害の正確な診断にあたっては、数字やデータなどで可能な限り客観的な証拠に基づくことが重要です。
検査はさまざまなものがありますが、一例として、QEEG検査と知能検査(WAIS‐Ⅳ、WISC‐Ⅳ)をご紹介します。
脳が活動すると脳内に微弱な電気が流れます。その電気活動を電極でとらえ、波形として記録するのが脳波検査(electroencephalography:EEG)です。QEEG検査(Quantitative EGG)とは、脳波を可視化する検査です。脳波検査で得られたデータをデータベースと比較することで、統計的な脳の特性を調べることができます。
欧米では、ADHDや自閉スペクトラム症などの発達障害、うつ病・不安障害・不眠症・耳鳴りなど、さまざまな精神疾患のバイオマーカーとしての研究が近年増加しています。(参考:品川メンタルクリニック「QEEG検査(定量的脳波検査)|品川メンタルクリニック」)
WAIS‐ⅣやWISC‐Vでは、総合的なIQを測ったうえで、多角的に知的能力を測ることができます。
WAIS‐Ⅳ
WAIS-IV知能検査は、ウェクスラー成人知能検査WAISの最新日本版です。
16歳0カ月〜90歳11カ月の青年および成人の知能を測定するための個別式の包括的な臨床検査であり、特定の認知領域の知的機能を表す4つの合成得点(言語理解指標:VCI、覚推理指標:PRI、ワーキングメモリー指標:WMI、処理速度指標:PSI)と全般的な知能を表す合成得点(FSIQ)を算出します。(参考:日本文化科学社「WAIS™-IV知能検査」)
WISC-V
WISC-V知能検査は、ウェクスラー児童用知能検査WISCの最新日本版です。
5歳0カ月〜16歳11カ月の子どもの知能を測定する個別式の包括的な臨床検査であり、特定の認知領域の知的機能を表す5つの主要指標得点(言語理解指標:VCI、視空間指標:VSI、流動性推理指標:FRI、ワーキングメモリー指標:WMI、処理速度指標:PSI)と全般的な知能を表す合成得点:FSIQ、子どもの認知能力やWISC-Vの成績について付加的な情報を提供する5つの補助指標得点(量的推理指標:QRI、聴覚ワーキングメモリー指標:AWMI、非言語性能力指標:NVI、一般知的能力指標:GAI、認知熟達度指標:CPI)を算出します。(参考:日本文化科学社「WISC™-V知能検査」)
もちろん、知能検査のみで診断することはありませんが、このスコアを参考にして発達障害の可能性を診断することもあります。
改めて、発達障害とは
そもそも発達障害とは、「脳の機能の発達に偏りや遅れが生じることで、日常生活や社会生活に影響が出ている状態」のことです。(参考:厚生労働省「発達障害|病名から知る|こころの病気を知る」、宮尾益知「ASD(アスペルガー症候群)、ADHS、LD 職場の発達障害」)
発達障害には主に3つの種類があります。
①ADHD(注意欠陥・多動性障害)
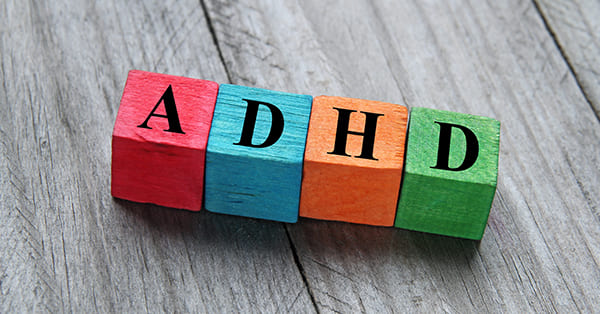
ADHDとは、「注意欠如・多動性障害(Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)」を意味する発達障害の一種です。
「不注意」「多動・衝動性」といった特性があります。
その他にもよく挙がる特性の現れ方として、「マルチタスクやスケジュール管理が苦手」といったものがあります。
- 注意散漫で学習や仕事でのケアレスミスが多い
- 直接話しかけられても、話を聞いているように見えない
- 指示を最後までやり遂げず、仕事を終えられない
- 課題や仕事を計画的に進めることが困難である
- 他人の会話をさえぎったり、割り込んだりする
- 順番を待つのが苦手である
②ASD(自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)

ASDとは、「自閉スペクトラム症、自閉症スペクトラム障害(Autism Spectrum Disorder)」を意味する発達障害の1種です。
「社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的な欠陥」「行動、興味、または活動の限定された反復的な様式」といった特性があります。
他に、感覚過敏(光や音や刺激への敏感さが目立つ)、発達性協調運動障害(不器用さが目立つ)などの特性がある人もいます。
- 場の状況や上下関係に無頓着
- 質問の意図や発言の狙いがわからない
- 比喩や冗談を理解できない
- 自分だけのルールに固執する
- 予定が急変するとパニックになる
- 興味関心の範囲が狭く、こだわりが強い
③LD(学習障害/限局性学習症)

LDとは、「限局性学習症/限局性学習障害(Specific Learning Disorder)」を意味する発達障害の一種です。
読むこと、書くこと、計算することなど、特定の学習のみに困難が生じるといった特性があります。
LDは、知的障害とは全く異なるものです。LDのみがある人は、知的発達の遅れはありません。ただし、LDと知的障害の両方があることもあります。
- 単語や言葉の聞き誤りが多い
- 筋道立てて話すことが苦手
- 文字を発音できない
- 誤った文字を書く
- 数字の位取りが理解できない
- 応用問題、証明問題、図形問題が苦手
発達障害グレーゾーンに関連する困りごとへの対処法
発達障害グレーゾーンの人々は、生きづらさを感じたまま生活することもあります。
以下では、私生活と仕事それぞれの場面別の困りごとから、発達障害グレーゾーンの特性に対処するための方法をご紹介します。
私生活での困りごと①雑談についていけない

他人の話を静かに聞くことができず、さえぎってしまうこともあります。また、話を聞きながら自分の意見を述べるといった2つのことを同時にはできないため、雑談の途中で話を振られてもとっさに対応できないことがあります。
私生活での困りごと②相手に不快感を与えてしまうことがある
例えば、話をしているうちに納得するまで質問を重ねたり、相手の本音に気づかず発言をしてしまったりすることで、相手に不快感を与えてしまうことがあります。
仕事での困りごと①仕事の全体のイメージをつかみづらい
段取りや仕事の過程について想像しづらく、仕事の内容を点と点でうまく結びつけることができない場合があります。その結果、仕事の全体的なイメージをつかむことができないことがあります。
仕事での困りごと②指示を理解しづらい
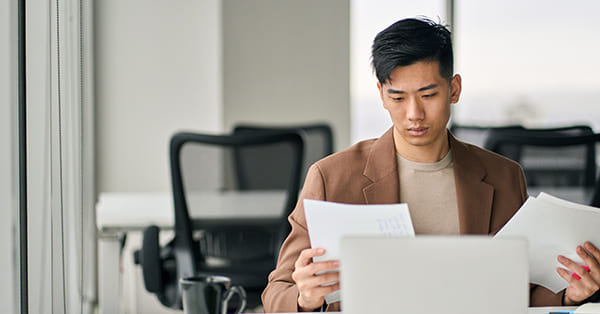
例えば、報告書などを簡潔にまとめるといった漠然とした指示がなされた場合、どの内容をどれくらい簡潔にまとめればよいか理解することが難しいと感じる方もいます。グレーゾーンの方に、仕事の指示を行う場合は、その内容をどれくらい簡潔にまとめればよいかといったところまで、具体的に説明を行う必要があります。
仕事での困りごと③ミスが多い
何度も確認を行ったり、スケジュール管理が難しかったりすると、期限ぎりぎりになってしまい、最後に焦ってミスをしてしまうこともあります。そして、失敗をすることで余計にパニックになり、悪循環に陥ってしまうこともあります。
補足:二次障害について
二次障害とは、発達障害の傾向や特性が原因で、周囲とのコミュニケーションが上手く取れないことで生きづらさを感じてしまうことを指します。
その生きづらさから、うつ病や不安障害、不眠症などの精神疾患を発症してしまうこともあります。
発達障害グレーゾーンの方の場合、発達障害の診断を受けていないことで「変わった人」という印象を持たれて避けられてしまったりすることもあるため、より生きづらさを感じやすい傾向にあります。
このような二次障害の症状が出ている場合、放っておくと深刻化して治療が長期化したり、入院治療が必要になったりすることもあります。悪化する前に治療を受けるようにしましょう。
発達障害グレーゾーンの人にオススメの仕事術8選:傾向別に紹介
発達障害グレーゾーンの人にオススメの仕事術を、傾向別に紹介します。
①ADHD傾向の発達障害グレーゾーンの人の仕事術3選

ミスや忘れ物といった不注意性や、考えるよりも先に行動してしまう点に特徴のあるADHD傾向の強い人には、以下の3つの仕事術をオススメします。
- 整理整頓する時間を取っておく
- リスト化を徹底する
- ダブルチェックをお願いする
ADHDの性質として、「整理整頓が苦手で、気がつくとすぐに机の上が散らかってしまう」傾向があります。
これは、発達障害グレーゾーンの人も同様です。
この傾向は重要書類の紛失やミスに繋がるため、「あらかじめ整理整頓する時間を設けておく」といった仕事術が有効でしょう。
また、作業をするときは、リスト化を徹底しましょう。思考を整理した上で、筋道を立てて仕事ができるようになります。
③の「ダブルチェックをお願いする」というのは、「努力をしても発生する見落としやミスを何としても防ぎたい」という場面で、効果を発揮します。
ダブルチェックは、発達障害の人だけでなく、定型発達者(非発達障害者)も普段から取り入れることが多いため、自然に頼めるのではないでしょうか。
②ASD傾向の発達障害グレーゾーンの人の仕事術3選

あいまいな説明や口頭での指示を受けるのが苦手なASD傾向の強い人には、以下の3つの仕事術がオススメです。
- 具体的な計画や指示を仰ぐ
- 文字や絵図を用いた説明を求める
- 日誌をつける
ASD傾向のある人は、ニュアンスや加減を理解するのが困難なため、抽象的な指示を出されると混乱しやすい場合があります。
そのため、「適宜」や「適当に」といった指示を受けることがないように、できる限り具体的な指示をもらえるように働きかけましょう。
さらに、ASDの人の中には、耳から受ける指示よりも、文字や絵図といった視覚的な指示の方が頭に入りやすいという人がいます。
このような場合も、説明の方法を理解しやすいものに変えてもらうよう、周囲に働きかけるとよいでしょう。
③の「日誌をつける」は、「自身の体調や疲労を顧みず、過度に集中する」といったASDの傾向への対処法です。
自分の状態をしっかりと把握するために、定期的に日誌をつけて確認する習慣をつけましょう。
③LD傾向の発達障害グレーゾーンの人の仕事術2選

「聞く・話す・書く・読む・計算する・推論する」といった学習能力に困難を抱えるLD傾向の人は、以下の点を意識して仕事をしてみましょう。
- 症状に合わせて情報を理解するための手段を変える
- 電子機器を利用する(ICレコーダーなど)
①はASD傾向の人の仕事術に似ていますが、口頭での説明よりメールや印刷物の方がわかりやすいという場合には、情報を理解するための手段を変えるだけで、仕事がスムーズに進むようになります。
また、症状をカバーするために、電子機器を利用するのもオススメです。
「文章を理解することを困難に感じる」「会議の場で議論を聞き取ることができない」という症状をお持ちの場合は、ICレコーダーなどを使って、音声記録を取るとよいでしょう。
また、計算能力に困難を感じるLDの発達障害グレーゾーンであれば、小型の電卓を常に携帯するなど、工夫次第で症状をカバーすることは可能です。
あなたのLDの症状にあわせて、情報理解の手段を変えてみてください。
発達障害グレーゾーンの人の仕事探しのコツ3選
ここでは、発達障害グレーゾーンの人のために、仕事探しのコツを3つご紹介いたします。(参考:木津谷岳「これからの発達障害者『雇用』」、ダイヤモンド・オンライン「発達障害の人に向く職業、向かない職業は何か」
これまでに述べてきた通り、特性理解と周囲を頼るという原則は同じです。仕事探しの際には、それに加えて「支援機関を頼る」ことをオススメします。
発達障害グレーゾーンの人は、診断書が下りない結果、あらゆるサポートを受けられずに、「一人で何とかしなくては」と抱え込む傾向があります。
しかし、診断書がなくても、相談可能な機関はありますのでご安心ください。
コツ①苦手なことを紙に書き出してみる

仕事探しを始めるときには、まず「苦手なことを紙に書き出してみる」ことが大切です。
発達障害の傾向がある人は、就職活動において、症状が前面に出てこないような仕事を選ぶ必要があります。
仕事選びにあたっては、以下のような例が挙げられます。
- ADHDグレーゾーンの人であれば、細かな事務作業やお金の取り扱いが主となる仕事を避けるようにする。
- ASDグレーゾーンの人であれば、臨機応変な対応を求められる接客業などを避けるようにする。
とはいえ、「何が苦手なのかわからない」という人もいるかもしれません。その場合は、付き合いの長い友人やご家族に質問してみましょう。
また、就職した後で、症状が現れやすい業務・向いていない仕事を任されることもあるかもしれません。
そのときは、仕事の手順や工程の中で、どの部分が特に苦手なのかを細かく分けて考えましょう。
苦手なことを紙に書き出すことで、それをカバーしたり回避したりする方法を見つけやすくなります。
コツ②特性を活かせる仕事を選ぶ

2番目のコツは「特性を活かせる仕事を選ぶ」ということです。
1番目のコツでは、「苦手なものを避ける」という方法をピックアップしましたが、「あなたの特性を活かす」という視点も大切です。
例えば、以下のような考え方で仕事選びをすることができます。
- ADHDの傾向が強く、正確さを求められる作業に不安はあるが、動き回ったり、コミュニケーションを取ったりすることは得意なため、接客業や営業が性に合っている
- LDの傾向が強く、一つの感覚に集中することが困難ではあるが、全体像を把握したり、総合的に物事を捉えたりすることが得意なため、デザイナーやインテリアコーディネーターが合っている
上記のように、発達障害グレーゾーンの人は、症状による困難を見出すのと同時に、得意なことや、「こだわり」を活かせる仕事がないかを考えてみるとよいでしょう。
コツ③支援機関を利用する

最後のコツは「支援機関を利用する」です。
相談機関については1章にも記載していますが、その他仕事に関係した相談ができる公共のサービス機関として以下が挙げられます。
発達障害グレーゾーンの人の悩みとして、公的機関の支援が受けられないことが挙げられます。しかし、診断書がなくても相談を受けられる機関は存在します。
一人で悩みを抱え込むのではなく、その解決に向けて積極的に支援機関を利用しましょう。
発達障害グレーゾーンの人の仕事上の困難

発達障害グレーゾーンの人が直面する仕事上の困難について解説します。
発達障害グレーゾーンの人が直面する困難として一番に考えられるのは、「特性があること」を医学的・客観的に説明しづらいことです。
発達障害グレーゾーンの人は診断書が下りないため、障害者手帳を取得できません。
それゆえ、仕事や日常生活に影響する症状があるにも関わらず、障害者枠での採用を利用できません。また、勤め先にグレーゾーンの特性による配慮を求めづらかったりするのです。
そうした状態での労働では、特性ゆえの失敗やミスを努力不足と誤解されやすくなります。
例えば、ADHDの特性が見られるグレーゾーンの人が、書類整理や事務仕事でミスを頻発したときに、「あの人は能力が低い」といった評価をされるケースが考えられます。
こうした仕事上の困難を和らげるために、同僚とのコミュニケーションを通して、あなたの苦手なことを理解してもらう働きかけをすることが必要です。
その際は、「医師からは『発達障害という明確な診断は下せないが、グレーゾーンではある』と言われた」などと、伝えられるとよいかもしれません。
関連して、障害があることを職場に明かすオープン就労と、明かさないクローズ就労の違いなどに興味のある方は、下記コラムをご覧ください。
発達障害グレーゾーンに悩む同僚をお持ちの方へ

「職場で発達障害グレーゾーンに悩む人がいる」という同僚の方へ向けて、少しお話をします。
発達障害グレーゾーンに悩む人とのコミュニケーションにおいては、「苦手をある種の個性として受けとめる周囲の姿勢」が必要になります。
多くの発達障害グレーゾーンの人は、苦手を受け入れようという姿勢があれば十分に働けます。
発達障害グレーゾーンと思われる人を同僚にお持ちの方は、「無理なくその人の苦手をフォローする仕組み」を作れないか考えてみてください。
あなたの働きかけと周囲の姿勢の両輪が揃うことで、発達障害グレーゾーンの人でも無理なく仕事を回せるようになるはずです。
発達障害グレーゾーンの子どもの特徴と支援
発達障害グレーゾーンの子どもには状況を見ながら、支援を行うかどうか判断をしていく必要があります。さらに、環境の変化などにより症状が悪化する場合もあれば、落ち着いて目立たなくなるケースも少なくありません。
発達障がいの基準に満たない場合であっても、少しでも疑いがあれば必要に応じた支援を受けることは可能ですので、気になることがある場合、まずは相談機関へ問い合わせてみましょう。
先述したように、発達障害グレーゾーン特有の症状や特徴はありませんが、ADHDやASD、LDといった発達障害、学習障害の症状や特徴の一部が見られることがあります。
発達障害グレーゾーンの子どもの年齢別の特徴
発達障害グレーゾーンの子どもの年齢別の特徴を一部紹介します。
- 食事中に気になることができると立ち上がったり何度も動き回ったりする
- 自分勝手な行動をとったり、状況を読むことができなかったりする
- 特定の順番で活動することや道順や物の配置にこだわる
- 周りの子と同じように活動ができない
- 学校のルールやマナー、決まり事が守れない
- 授業中、落ち着きがなくうろうろする
- 忘れ物が多い
- 間違いが目立つ
- 読み書きに時間がかかる
- 計算が苦手
- 場面に合わない質問をする
- 1人でしゃべり続ける
- 思ったことを口に出しすぎる
- 場の空気を読むのが苦手
- 文脈の理解をするのが難しい
- 好きなことにしか集中ができない一方、興味のないことには一切興味を示さない
- 忘れ物や失くし物が多い
保育園児・幼稚園児の発達障害グレーゾーンの子どもへの支援

主な症状は、「こだわりが強い」「常に動き回る」です。
- 「〇〇後にできるよ」など見通しを立てる
- タイマーを使用して時間を区切る等の切替えが出来るよう工夫する
- 危険な行動や本当にしてほしくないことに対しては特に工夫したり、伝えたりする
- 横断歩道を渡るとき、信号に関すること、手をつなぐ等のルールブックを作り、その都度見せる
幼児期は、本人がうまく言葉に出さないため、大人は「わがままだ」と感じることも少なくありません。その場合、無理やりやめさせると癇癪を起したり、パニックになってしまったりすることも逆効果になるときもあります。
発達障害グレーゾーンの子は、「ちゃんとして」といったあいまいな表現が伝わらないので、「授業中にわからないことがあれば、手を挙げてから発言してね」と伝えることも大切です。
小学生の発達障害グレーゾーンの子どもへの支援

主な症状は、「言い争いやトラブルが多い」「ゲームやマンガに熱中しすぎる」です。
- 「ダメ」などの否定的な言葉は使わず、「こうしてね」と肯定的な表現に置き換える
- 曖昧な表現やほのめかしは使わず、わかりやすく落ち着いて話す
- 娯楽物がなるべく目に入らないようにするなど、環境をととのえること
- タイマーなどを用いて、時間を区切る、視覚的にスケジュールを伝えること
学校生活を送ることでさえ、本人はしんどい思いをしていることも少なくありません。
「ちゃんとしましょう」といった曖昧なルールではなく、「授業中に質問するときは、手をあげたあとで、先生に指されてから質問する」など具体的かつ詳細なルールを定めるようにしておきましょう。
また、友人同士とのかかわりの中でも、お互いが納得できるようなルールや決まり事を作ることも大切です。
中学生・高校生の発達障害グレーゾーンの子どもへの支援

主な症状は、「反抗期や、不登校など学校への行き渋りがある」「提出物や予定を忘れる」です。
- 悩みや不安を傾聴する
- 本人の感情や気持ちの整理をしながら「困ったらいつでも助ける」といった姿勢で接すること
- TODOリストやリマインダーなどを活用すること
学校の不適応に関しては、担任の先生やスクールカウンセラーと情報共有して、対処していくことが大切です。
発達障害グレーゾーンでも利用できる支援機関4選
発達障害グレーゾーンの人でも、仕事や日常生活における困りごとに関して相談できる機関は、あります。以下では、発達障害グレーゾーンの人が利用できる4つの相談先を紹介します。
支援機関①就労移行支援事業所

就労移行支援事業所は、障害のある方に対し、一般企業へ就職できるようサポートする福祉サービスです。全国に約3,300箇所以上設置されています。
事業所では、働き続ける上で重要となる健康管理能力や対応力を身につけることを目的としています。以下のサポートを受けることができます。
- 就職前の職業訓練や就職活動の相談やアドバイス
- 就職後の職場定着支援といったサポート
- スキルアップのための研修やトレーニング
※就労移行支援事業所を利用するために、下記の必要条件をすべて満たしている必要があります。
- 18歳以上満65歳未満
- 発達障害などの障害がある方で、一般企業で働くことを希望する
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、うつ病や発達障害などの人のための就労移行支援事業所です。
- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月
新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。
支援機関②発達障害者支援センター
発達障害者支援センターでは、保健、医療、福祉、教育、労働などの関係機関と連携し、地域における総合的な支援ネットワークを構築しながら、発達障害児(者)とその家族からの相談に応じ、指導と助言を行っています。
診断を受けている人だけでなく、診断を受けていないが、発達障害の可能性がある人に対する支援も提供しています。都道府県・指定都市自ら、または、都道府県知事等が指定した社会福祉法人、特定非営利活動法人等が運営しています。
基本的に無料で相談することが可能ですが、詳しい内容は各自治体に問い合わせてみてください。
支援機関③障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは、障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として、全国に設置されています。
発達障害を持つ就業者や就業を希望している人に対して、衣食住を安定させるための支援や制度の紹介を行っています。
支援機関④ハローワーク(職業紹介所)
ハローワーク(職業紹介所)は、厚生労働省が運営しています。一般の相談窓口とは別に、発達障害がある方に対する就業サポートのために、障害への専門知識を持つ担当者によるサポートが受けられる「障害者相談窓口」を設置しています。
障害者手帳を持っていない場合でも、自身の特性による困りごとを相談し、求人情報の提供や就職活動のアドバイス、就職後の継続的な支援などを受けることが可能です。
まとめ:周囲の理解を得るためにコミュニケーションを取っていくこと

発達障害グレーゾーンにいる人は明確な診断をもらっていない分だけ、発達障害の人とはまた別の苦労を抱えやすい傾向にあります。
しかし、「ご自身の特性を理解して仕事を工夫すること」、そして「周囲の理解を得るためにコミュニケーションを取っていくこと」は、発達障害の診断が下りた人と同様に大切です。
症状をハンデのように感じられることもあるかと思いますが、それもひとつの個性だと受けとめる姿勢を保ちながら仕事探しをしていきましょう。
発達障害グレーゾーンの傾向別に、オススメの仕事術を知りたいです。
一般論として、ADHD傾向の方には、次の3点が挙げられます。「整理整頓する時間を取っておく」「リスト化を徹底する」「ダブルチェックをお願いする」。ASD傾向・LD傾向の方も含めて、詳細はこちらをご覧ください
発達障害グレーゾーンの自分ができる、仕事探しのコツを知りたいです。
一般論として、次の3点が挙げられます。「苦手なことを紙に書き出してみる」「特性を活かせる仕事を選ぶ」「支援機関を利用する」。詳細はこちらをご覧ください。
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
執筆寺田淳平
てらだ・じゅんぺい。
高校2年の春から半年ほど不登校を経験。保健室登校をしながら卒業し、慶應義塾大学に入学。同大学卒業後の就職先(3,500人規模)で人事業務に従事する中、うつ病を発症し約10か月休職。寛解・職場復帰後、勤務を2年継続したのち現職のフリーライターに。
2019年に一般財団法人職業技能振興会の認定資格「企業中間管理職ケアストレスカウンセラー」を取得。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→





