双極性障害のある人が仕事を続けるコツ7選 向いてる仕事や仕事に行きたくないときの対処法を解説

こんにちは。就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)です。
双極性障害があるあなたは、以下のようなことをお悩みではないですか?
- 双極性障害になっても仕事は続けられるのか
- どんな仕事が向いてるのかわからない
- いまの働き方で働きつづける自信がない
このコラムでは、双極性障害のある人に向けて、双極性障害が仕事に与える悩み・影響や仕事を続けるコツ、向いてる仕事・職場、向いてない仕事・職場、仕事に行きたくないときの対処法、仕事探しのポイントを解説します。
このコラムが、双極性障害にお困りのあなたの悩みを軽くする手助けになれば幸いです。
双極性障害と就職活動については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
目次
双極性障害が仕事に与える悩み・影響5選
この章では、双極性障害が仕事に与える具体的な悩み・影響を紹介します。
あなた自身のこれまでを振り返り、どのようなことに気をつけながら働くべきか対策を考えましょう。(参考:あしたのクリニック精神科 心療内科「双極性障害で仕事ができないと感じたときの対処法|就職方法も紹介」)
悩み①躁状態のときに仕事を引き受けすぎる

双極性障害のある人の仕事上の悩みとしてよく挙がる事例に、「躁状態のときに遂行できないことを引き受けすぎる」というものがあります。
躁状態になっている人は、あまり休まなくても仕事がはかどるため、自分だけではできない仕事まで引き受けがちです。
また、そこからうつ状態に転じると、仕事がままならなくなり、「自分から引き受けたのに仕事をやり切らないじゃないか」と、周囲からの社会的信用を失うことに繋がることもあります。
悩み②ミスが増える
2つ目の悩みは「ミスが増える」です。
双極性障害には、認知機能の低下がみられるというデータがあります。
認知機能には以下のものが挙げられます。
- 注意力
- 記憶力
- 計画力
- 学習能力
- 意思決定力
うつ状態の場合、集中力や思考力などの低下がみられ、躁状態では注意力散漫や衝動を抑えられないといった症状がみられるとしています。
双極性障害のある人は、交互に訪れる、または混合してみられるさまざまな症状によって、仕事に集中できなかったり仕事が思うように進められなかったりするようです。
悩み③うつ状態のときに仕事を休みたくなる

3つ目は「仕事を休みたくなる」です。
こちらでも解説したとおり、躁状態のときは、体力と気力を使いすぎることがあります。うつ状態に転じたときにはぬけ殻のように何もしたくなくなって、欠勤が続くというケースもあります。
自分なりに気を付けたり工夫したりしていても、ミスが増えてしまえば仕事に行くことが苦痛に感じ、休みたくなる人もいるようです。
これはうつ状態によって意欲が湧きにくくなり、仕事に限らず外に出ること、起床することすら憂うつに感じてしまうことがあるためと考えられています。
調子がすこぶる良かったのに、突然休みがちになったことで、職場の同僚や上司から「スパンの長い仕事は任せられない」と判断され、昇進が遅れるということがあるようです。
悩み④対人トラブルが増える
躁状態になると、ちょっとしたことで怒りやすくなったり攻撃的な言動がみられたりすることがあります。
躁状態のときは、アイディアが豊富に湧き、普段では見られないほど精力的に仕事に取り組むため、一見ポジティブな影響があるように思われます。しかし、その状況についていけない周囲の人に対して「こんなこともできないのか」といらだちを覚えることもあるのです。
その結果、職場でもきつい言葉で怒ってしまったり周囲を気にせず感情的になったりするなどの行動につながり、対人トラブルに発展することがあります。
また、こちらでも触れたように、「一人で物事を勝手に進めて周囲を困らせる」「できもしない約束を交わす」などといった予想外の行動を引き起こしてしまうことも珍しくありません。
これらの言動によって結果的に周囲からの信用をなくし、仕事を辞めざるを得なくなることもあるようです。
なお、うつ状態の場合、人と関わることに興味を持てず避ける傾向がみられます。そのことから、コミュニケーションが不足し、仕事に行けなくなるといった事態につながることがあります。
悩み⑤身体的症状が見られる

5つ目は、「身体的症状が見られる」です。
仕事でのミスが増えたり、自身の気分の高低差にストレスを感じたり、それによって対人トラブルが増えてしまうと、食欲不振や不眠などといった体調不良を引き起こすことがあります。
さらに、そのまま放置してしまうと全身のだるさがみえるなど深刻な状態にまでつながることもあるようです。
もし、仕事に行くことはできても、どこか体調が優れないと感じたり、そのような毎日が続くときは、休息時間を設けることをおすすめします。
双極性障害のある人が仕事を続けるコツ7選
この章では、双極性障害のある人が仕事を続けるコツを7つ紹介します。(参考:貝谷久宣『よくわかる双極性障害(躁うつ病)』、野村総一郎『新版 双極性障害のことがよくわかる本』、双極はたらくラボ「双極性障害と家族の限界 共倒れしないための工夫」、厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス不調者の事例性に 着目した支援方策に関する研究」、厚生労働省「障害者手帳について」)、厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」、厚生労働省「事業主の方へ」、内閣府「「合理的配慮」を知っていますか?」)
コツ①医師や支援者の意見にきちんと耳を傾ける

仕事を続けるための1番のコツは、「医師や支援者の意見にきちんと耳を傾ける」ことです。
双極性障害のある人は、躁状態にあるときには気が大きくなるため、人の意見に耳を傾けることが難しくなります。自信に満ちあふれているため、「ひとりでどうにかなる」と思い込むことが多いです。
そのため、躁転しそうな予兆を感じたときや、うつ状態にあるときなど、早い段階で自分の現状を知らせるなどして医師や支援者から意見をもらうようにしましょう。
また、自己判断で薬の服用を中断したり通院をやめたりすることは、絶対にしないでください。
先述したように、双極性障害では薬物療法がメインとなるため、怠薬したことで悪化したり、再発したりする可能性が高いのです。
「この章で紹介されているほかのコツを実践しているから」と過信するのも禁物です。
調子が良くなったり、気分が上向いたりしているときでも、主治医の先生やご家族、支援者などの意見にはきちんと耳を傾けるようにしましょう。
コツ②疾患を受け入れる
2つ目のコツは、「疾患を受け入れる」姿勢を保つことです。
双極性障害は、再発しやすく、長期の治療が必要な病気と言われています。
軽快したから「完治した」と本人が思っていても、ふとしたきっかけで症状が再発する可能性が高いのです。
そのため、あなたが疾患を受け入れて、長期的なスパンで付き合っていく姿勢を保つことが大切です。
幸い、治療法は確立しています。再発の予兆を自分で把握したり、ストレスを感じたらリラックス法を実践したりといった心掛けをしていくことで、安定した社会生活を送ることができます。
双極性障害による気分の「ムラ」を自分の性質と考えて、疾患を受けいれる姿勢を持つようにしましょう。
コツ③体内時計を整える
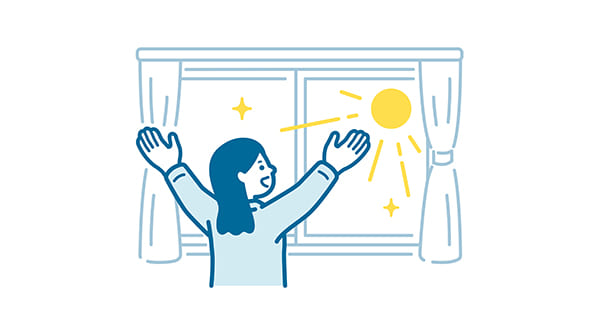
長続きのコツの3点目は、「体内時計を整える」です。
双極性障害のある人は、活動的な躁状態と、そうでないうつ状態が不定期に訪れるため、体内時計が乱れやすいです。
体内時計が乱れると、入眠障害や中途覚醒などの睡眠障害を引き起こしたり、日中の抑うつ感が増したりと、双極性障害を悪化させるさまざまな症状のリスクが高まります。
そのため、日頃から体内時計を整えることを意識してください。
体内時計を整えるためには、以下の3つのリズムを保つことが大切です。
- 睡眠のリズム
- 食事のリズム
- 活動のリズム
就寝と起床の時間を定めるようにしましょう。
また、就寝前には覚醒作用のあるコーヒー・緑茶・エナジードリンクなどのカフェインの飲食は控え、脳を刺激するパソコンやスマホの使用を避けると良いです。
食事も1日3食、決まった時間に食べ、日中はできるだけ太陽の光を浴びるために、外で活動する機会を設けましょう。
数十分のジョギングなど、適度な運動も取り入れることも、体内時計を整えるのに効果的です。
コツ④できるだけ残業を避ける
4つ目のコツは、「できるだけ残業を避ける」です。
双極性障害のある人が躁状態に転じやすいタイミングとして、繁忙期に遅くまで残業をするなど、過剰に仕事に取り組むときがあげられます。
躁状態のときは疲れを感じることもなく気分が高揚しているため、無理をしてでも仕事を進めたくなる人がいるはずです。
しかし、双極性障害のある人はこうした気分の波をできるだけ減らすことが大切になります。勤務時間や仕事量もできるだけ一定にするのが望ましいのです。
とはいえ、躁状態のときは自分で仕事を止めるのも難しいでしょう。そのため、普段から同僚に「あまり残業が続いているようだったら声をかけてください」と一言お願いするとよいでしょう。
コツ⑤休暇取得日を月初めに決めておく

5つ目のコツは、「休暇取得日を月初めに決めておく」です。
こちらで解説したコツと同様に、「働きすぎを抑制する」ための工夫です。
スイッチが入っているときには、休みを挟むことなく立て続けに仕事をするため、月初にあらかじめ休暇を入れて休日を決めておくことは有効です。
とはいえ、休暇を取得してもきちんと休まなければ意味がありません。
職場によっては、休暇予定日の直前でも休暇の申請をキャンセルできるかもしれませんが、「働けそう」と思っても、「入れた休暇は絶対に消化する」など自分で決まりを作って、周囲の人にもそのことをアピールするとよいでしょう。
コツ⑥つらい状況を家族に共有する
6つ目のコツは、「つらい状況を家族に共有する」です。
双極性障害と診断されたお母様を持つコミックエッセイストのまりげさんは、「双極性障害を抱える本人から、自発的に心の状態を少しずつしゃべってくれたり共有してくれたりすることに、むやみに心配しなくてよくなった」「家族側からすると、双極性障害を抱える本人の心の中が見えないのがとにかく不安」と話しています。(参考:双極はたらくラボ「双極性障害と家族の限界 共倒れしないための工夫」)
双極性障害のある人は、自身の変化にいち早く気付いてもらうため、家族に共有することが望ましいでしょう。
ただし、ご家族が病気に理解を示さないこともあります。家族に伝えたほうがいいのか、どのように伝えるべきかについては、あなた一人で考えるのではなく、医師も含めて支援機関に相談することをオススメします。
コツ⑦異動・転職を視野に入れる

厚生労働省によると、双極性障害を含むメンタルにまつわる病気と診断した医師の多くは、休業のほか転職を促しているそうです。(参考:厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス不調者の事例性に 着目した支援方策に関する研究」)
双極性障害のある人は、躁状態とうつ状態を繰り返したり、時に混在したりすることがあります。
そのため、人間関係がうまくいかなかったり、そんな自分に強い憤りを感じたりすることも少なくありません。
現在の仕事に対して不満があるとき、さらには自身の症状によって仕事に行きにくくなったときは、異動や転職を視野に将来を考えることも大切と考えられます。
補足:症状がつらいなら障害者雇用を検討する
双極性障害がある人が働くには、自身の症状について把握し、上手に付き合っていくことが求められます。
しかし躁状態とうつ状態が混在したり、それぞれの症状が強く出たりすると、仕事に行くことも苦痛に感じるでしょう。
自身の症状をつらいと感じるときは、障害者雇用も検討しましょう。
障害者雇用とは、障害のある人を専用の雇用枠を用いて雇い入れる制度です。障害のある人でも、個々の能力や特性に応じて、安定的に働けるようにすることを目的としています。
障害者雇用では、一般的には病気・障害についての理解を得ながら働くことができます。
障害者雇用に切り替えて働く場合、障害者手帳を取得して職場に提示するのが一般的です。
障害者手帳とは、障害がある人に交付される手帳のことです。(参考:厚生労働省「障害者手帳について」)
双極性障害は「気分障害」のひとつであるため、双極性障害のある人でも障害者手帳の取得は可能です。(参考:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」)
障害者雇用促進法では、障害者手帳を取得していない人でも「障害者雇用」の対象です。ただし、注意が必要です。(参考:厚生労働省「障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象」)
障害者雇用促進法では、事業主が雇い入れる労働者の全体人数に対して、一定の割合を障害のある人にするよう義務づけられています。この「労働者の全体人数に対する障害のある人の雇用率(の義務)」のことを「法定雇用率」と言います。(参考:厚生労働省「事業主の方へ」)
しかし、障害者手帳を取得していない障害のある人を障害者雇用で雇用したとしても、障害者雇用促進法上、法定雇用率に算定できません。
そのため、職場は「障害者手帳を取得していない、障害のある人」を(障害者雇用という意味では)積極的に採用しない傾向にあります。
障害者雇用での就労を検討しているのであれば、障害者手帳を取得するのが無難でしょう。
なお、双極性障害を含む障害のある人、さらには生活に困りごとがある人は、障害者雇用でなくても合理的配慮を受けることができます。
合理的配慮とは、障害のある人の人権を保証するとともに、教育や就労、社会生活において平等に参加できるよう、障害や特性、困りごとに合わせて講じる配慮のことです。
障害者雇用においては、募集・採用時に障害のある人と障害のない人との均等な機会を確保すること、また障害のある人が業務上で支障があったときに改善するための措置を取ることを目的としています。(参考:内閣府「「合理的配慮」を知っていますか?」)
ただし現実問題として、十分な合理的配慮ができない事業所もあります。また、何が合理的の範囲なのかが曖昧な部分もあります。
障害者雇用も含めて、「どのような仕事・職場・働き方が自分に向いているか」については、支援機関に相談することをオススメします。
障害者雇用の詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
障害者手帳の詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
双極性障害のある人に向いてる仕事・職場
この章では、双極性障害のある人に向いてる可能性がある仕事を具体的に解説していきます。
精神科医の加藤忠史先生によると、双極性障害であっても、きちんと病気を理解して受けとめて、有効な予防さえすれば、仕事を諦めなければならないということはほとんどないと言います。(参考:加藤忠史『双極性障害[第2版]』)
ただし、仕事の内容や環境によっては双極性障害を悪化させることがあるのも事実です。
これから就職しようと考えている人、転職を考えているけれどどのような職種に就くのが良いかわからないといった人は参考にしてみてください。
仕事①通院・服薬の配慮が受けられる仕事・職場

1つ目は、「通院・服薬の配慮が受けられる仕事・職場」です。
双極性障害の治療・改善にあたっては、服薬や通院が必要です。そのことから、本人にとって必要な通院・服薬への理解が十分にあり、適切な配慮が受けられる仕事・職場を選びましょう。
躁状態やうつ状態が続くと、自分でも思いもよらない言動が出ることもあります。そういった意味でも、配慮が受けられる仕事や職場を選ぶことは、働く上でもっとも重要です。
たとえば、在宅ワークという働き方を選ぶと、自分のペースで通院・服薬が可能です。ただし、職場には事前に通院が必要になることを申し出ることを忘れないようにしましょう。
仕事②障害者雇用に注力する職場
2つ目は、「障害者雇用に注力する職場」です。
双極性障害症状が強まると、仕事に行きたくなくなることも少なくありません。
そのようなことをあらかじめ考慮し、障害者手帳の交付を受けて、障害者雇用に注力する職場で働くのも方法の一つです。
障害者雇用に注力する職場であれば、症状が出ているときにきちんとした配慮が受けられます。
障害者雇用や双極性障害について職場に開示した上で働くオープン就労を選んで働く方法も視野に入れましょう。
仕事③業務量・勤務時間の変動が少ない仕事

3つ目は、「業務量・勤務時間の変動が少ない仕事」です。
業務量や勤務時間に変動のある仕事だと、躁状態では多少無理がきいても、うつ状態になったときに症状がひどくなることがあります。
躁状態のときに仕事が抑えられるよう、業務量や勤務時間の変動がない仕事を選ぶことで、自分のペースを維持しながら働くことができます。
例を挙げるとするなら、事務職や在宅ワークのように自分のペースで取り組める職種や、残業の少ない仕事がおすすめです。
仕事④人との交流が少ない仕事
4つ目は「人との交流が少ない仕事」です。
双極性障害の状態によって、周囲の人とトラブルにつながることもあります。逆に、周囲の人とのトラブルが症状の悪化につながることもあるでしょう。
そのことから、自分の状態について理解し、「人との交流は避けた方が良いかも」と考えるときは、在宅ワークや倉庫内の軽作業スタッフ、調理スタッフなどの仕事を選び、人との交流が少ない仕事に就くと良いでしょう。
双極性障害のある人に向いてない仕事・職場

双極性障害のある人に向いていない可能性がある仕事にはどのようなものがあるでしょうか?
基本的には、こちらで解説した向いてる仕事の内容の裏返しです。
- 外的要因で仕事の量が多く変化する仕事
- 生活リズムが乱れるような仕事
- 対人折衝の多い仕事
以上のような仕事は、どちらかというと避けた方がいいでしょう。
特に、「早朝勤務や深夜勤務といったシフト制」は、生活リズムの乱れによる双極性障害の再発の原因になります。
以下のような仕事は残業や夜勤の多さ、業務量の変化が大きいため避けたほうがいいかもしれません。
- 営業職
- 接客業
- 看護師
- 工場でのシフト勤務
双極性障害の場合、薬物療法が前提となりますが、ほとんどの向精神薬には、「本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械類の操作に従事させないよう注意すること」という注意書きがあります。
そのため、重機の操作や自動車運転が必要な仕事にも課題が残るでしょう。
その他、予防療法の第一選択薬である「リチウム」には、副作用として「手の震え」が起こることが知られているため、細かな手作業には向いていないという人もいるでしょう。
双極性障害のある人が仕事に行きたくないときの対処法5選
服薬や通院をしていても、どうしても仕事に行きたくないと思うこともあるでしょう。
そのようなときは、これからご紹介する5つの対処法を試してみてください。
対処法①家族・医師などの専門家による意見を聞く

1つ目の対処法は、「家族・医師などの専門家による意見を聞く」です。
躁状態の場合、気が大きくなり、その結果、人の意見に耳を傾けずに、あらゆることを自分ひとりで判断することがあります。
例えば、調子の良いときが続いているからといって服薬や受診を自己判断で辞めるなどです。
正確に判断できることもあればできないときもあり、誤った行動を取る可能性も予想されます。
そのことから、双極性障害を抱えながら働くときは、家族のほか、医師などの専門家による意見をきちんと聞き、受け入れることが大切です。
対処法②気分転換を意識する
2つ目の対処法は、「気分転換を意識する」です。
双極性障害の状態は、常に複雑に変化するものです。そのことから、まずは気分転換やストレス解消できる工夫を自分なりに考えてみましょう。
仕事に向き合うことが面倒になったり、モチベーションの維持に難しさを感じたりするときは、以下のようなことを試してみてください。
- 仕事が終わったら楽しめるごほうびを毎日用意する
- 好きな飲み物をそばに置く、飲んで気持ちを切り替える
- リフレッシュに効果のある香りをそばに置く
このようなことを仕事に取り入れると、自然と仕事に向かえるようになります。自分にとってのごほうびや仕事に差し支えのない範囲で楽しめるものを取り入れ、躁状態とうつ状態をコントロールしましょう。
対処法③作業内容・作業時間について上司に相談する

3つ目は、「作業内容・作業時間について上司に相談する」です。
作業内容が大きく変わったり、不規則な就業時間だったりする場合は、一度上司に相談してみることをおすすめします。
こちらでも解説しましたが、躁状態だとつい無理をする懸念があります。そしてうつ状態を迎えてしまうと、無理したことで体が思うように動かなかったり、気持ちが後ろ向きになったりすることも少なくありません。
そのため、上司に気分のムラがあることを伝え、心身ともに負担のかからない作業内容・作業時間に変えてもらいましょう。
もし相談することが難しい、または相談しても変化が見られないときは、自分の体調に合う仕事について考え、異動や転職を視野に動いてみるのも方法のひとつです。
対処法④自身の変化をきちんと受け入れる
4つ目は、「自身の変化をきちんと受け入れる」です。
仕事をする上では、自身の体調の変化にはいち早く気付くことが大切です。
躁状態・うつ状態になるときのサインを自分自身で把握しておけば、「残業しない」「予定を入れない」「無理をしない」など、状態にあわせた働き方が実現します。
しかし、躁状態の場合、「今日はすこし調子が良いかも」と感じることもあり、気付かないときもあります。
そのようなときでも無理をしないよう、職場の人や家族に躁状態とうつ状態のサインが見られたときは、声をかけてもらう環境づくりをお願いすると良いでしょう。
対処法⑤心身のバランスを取り戻すため休業を申し出る
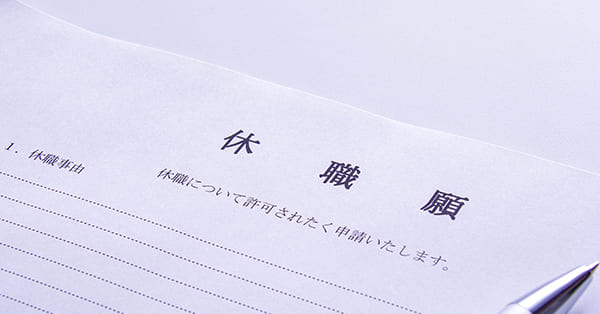
最後の対処法は、「心身のバランスを取り戻すため休業を申し出る」です。
どれだけ工夫を取り入れても、仕事に行きたくないと思うときは、心身のバランスを取り戻すために休業を申し出るのも効果的です。
躁状態とうつ状態が交互に来る日と混在する日が長期間続くと、不眠症や食欲不振などにつながり、働くことさえも困難になります。
また、これらの症状によっては、栄養不足に陥り、入院を余儀なくされることも考えられます。
どうしても仕事に行く気になれないときは無理に行こうとはせず、その旨を上司に打ち明け、休職期間を求めることをおすすめします。
双極性障害のある人にあった仕事探しのポイント3点
この章では、双極性障害のある人にあった仕事探しのポイントを3点ご紹介します。(参考:秋山剛『「はたらく」を支える! 職場×双極性障害』)
繰り返しになりますが、仕事探しをする際にも大切なのは、「周囲の人を適切に頼る」ことです。
特に、就職・転職活動をする際には、定期面談を受けているかかりつけ医の先生に相談するようにしましょう。
躁とうつの波がまだ激しいときに転職活動をするのは禁物です。
しかし、双極性障害のある人は「自分がまだ安定していないこと」を自覚することが困難な場合も多いので、専門医やご家族などの客観的な意見が大切になってきます。
こうした「周囲の人を適切に頼る」という点を前提として、以下の仕事探しのポイントを見ていきましょう。
ポイント①就労移行支援事業所を利用する

1つ目のポイントは、「就労移行支援事業所を利用する」です。
双極性障害のような精神障害のある人が仕事探しをするとき、以下のような点で悩まれることも多いのではないでしょうか。
- 障害者手帳を取得すべきか
- 障害を開示して働くべきか
- 障害を開示せずに働くべきか
- 雇用枠をどうすべきか
就労移行支援事業所では、以上のようなお悩みに応えた上で、就職活動の手助けをしています。
就労移行支援とは、一般企業などへの就職を目指す、病気や障害のある方向けに、「障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」に基づいて行われる福祉サービスのことです。(参考:e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
実際のサービスは、国の基準を満たした様々な民間の「就労移行支援事業所」が行います。キズキビジネスカレッジ(KBC)もそのひとつです。
就労移行支援事業所では、体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができます。
さらには、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
就労移行支事業所については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、双極性障害のある人のための就労移行支援事業所です。
- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月
新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。
ポイント②繁閑の差が激しくない仕事を探す
仕事探しのポイント2点目は、「繁閑の差が激しくない仕事を探す」ことです。
双極性障害が悪化したり、再発したりするのは、残業のしすぎなどをきっかけとする「生活リズムの乱れ」です。
そのため、年末に突発的に忙しくなるなど、繁忙期と閑散期の差が激しいようなお仕事だと、躁状態とうつ状態の波が激しくなる可能性があります。
また、繁閑の差が激しくなくても転勤や出張などの頻度が高いお仕事だと、移動や環境変化に伴って生活リズムが乱れやすいためあまりオススメできません。
こちらでも解説しましたが、「繁閑の差が激しくない仕事を探す」というのを軸にするとよいでしょう。
ポイント③障害への配慮が厚い職場かどうかを確認する

最後のポイントは、「障害への配慮が厚い職場かどうかを確認する」です。
2018年に改正障害者雇用促進法が適用され、障害者の法定雇用率が2.2%に引き上げられたことにより、職場における障害のある人への配慮が重視されるようになりました。
それに伴い、コンプライアンスの一環として、事業者側でも障害のある人への配慮を厚くしているところが増えています。
実際に障害に配慮している職場かどうかを見分けるポイントは、2つあります。
- 障害に関する研修制度が充実しているかどうか
- 福利厚生制度が整備されているかどうか
障害やメンタルヘルスを重視している職場では、それに関連した研修制度を複数取り入れています。
こうした職場であれば、障害を開示しているかどうかを問わず、障害のある人にどのような配慮をすべきかを考慮していることが多いため、仕事が長続きしやすいでしょう。
また、福利厚生制度を確認するのも重要です。
家賃補助などの金銭的な面よりも、休職制度や短時間勤務制度など「従業員が健康を害したときにフォローしてくれる制度があるかどうか」を確認するようにしてください。
長く働き続けるためには、障害に配慮している職場かどうかを見極めることが大切です。
仕事をしている双極性障害のある人の事例

日本うつ病学会双極性障害委員会は、仕事をしている双極性障害のある人19名の手記を公開しています。(参考:日本うつ病学会双極性障害委員会「仕事をしている双極性障害患者さんの手記」)
30代の専業主婦の方や、50代の男性会社員の方、公務員として働く方の手記も読むことができます。
それぞれ、双極性障害と診断されてからさまざまな紆余曲折を経験したことを詳しく手記として残しており、中には工夫したことなども記載されています。
双極性障害と診断を受けて、これからどのように仕事と向き合えば良いのか不安があるという人は、参考にしてみると良いでしょう。
日本うつ病学会双極性障害委員会「仕事をしている双極性障害患者さんの手記」
双極性障害のある人が利用できる支援制度5選
この章では、双極性障害のある人が利用できる支援制度を5つ紹介します。
なお、制度を受ける場合は、あらかじめ最寄りの自治体や病院で相談をしてから手続きを進めるのが一般的です。
制度によっては主治医が発行した診断書や個人を証明できる運転免許証や健康保険証などが必要になります。利用したい制度を見つけたときは、必要なものについても確認しておくことをおすすめします。
支援制度①自立支援医療制度(精神通院医療)

自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療に関する医療費の自己負担額を軽減する公費負担の支援制度のことです。双極性障害もその支援の対象です。(参考:厚生労働省「自立支援医療について」、厚生労働省「自立支援医療制度の概要」、東京都福祉局「自立支援医療(更生医療)」)
通常、医療保険による医療費の自己負担額は3割です。自立支援医療制度を利用すれば、原則1割まで軽減することができます。この制度は、指定の医療機関・薬局のみで利用可能です。
さらに、自己負担額には上限が設定されています。1割負担であっても、月額の上限以上となる金額は、原則として負担を免除されます。ただし、世帯の総所得額によっては、自己負担額が変動したり、対象外になったりする場合があります。
また、費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない場合や所得の程度に応じて、さらに軽減措置が行われます。
自立支援医療は、下記の3種類に分けられます。
- 精神通院医療:精神疾患の治療など
- 更生医療:身体障害に関わる治療など
- 育成医療:身体障害がある子どもに関わる治療など
特定の精神疾患がある人以外に、身体障害者手帳を持つ人なども対象です。
具体的な支援内容や条件、必要な書類、名称などは、自治体によって異なります。自治体によっては自己負担分も負担してくれるケースがあるようです。
継続的な通院・投薬が必要になることを想定して、気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。
支援制度②障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)
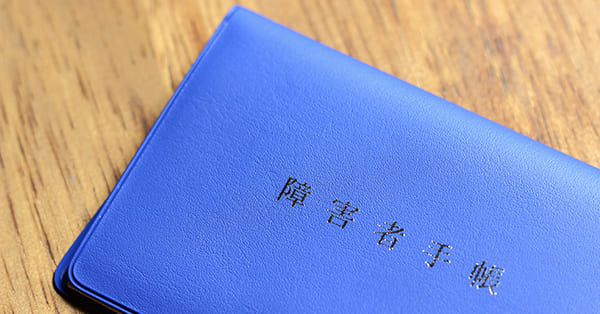
障害者手帳とは、障害がある人に交付される手帳のことです。
障害者手帳をお持ちの人は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」の対象となり、さまざまな支援が受けられます。(参考:厚生労働省「障害者手帳について」、e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)
障害者手帳には、障害の内容によって以下の3種類があります。
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
症状の程度にもよりますが、双極性障害を含む一定程度の精神障害の状態にある場合、「精神障害者福祉保健手帳」を申請できる可能性があります。
障害者手帳のメリットは以下のとおりです。
- 税金控除の対象になる
- 各種公共料金などの割引がある
- 医療費などの助成がある
- 補装具費用が安くなる
- 障害者雇用での就職も選択できる
気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。
障害者手帳については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援制度③障害年金
障害年金とは、病気やケガ、障害によって仕事や生活に影響が出た場合に年金加入者が年金を受給できる支援制度のことです。(参考:日本年金機構「障害年金」)
「事故で足を失った」「生まれつき四肢が不自由」「知的障害がある」などのケースだけでなく、発達障害・精神疾患・生活習慣病なども受給の対象になります。
一般的な年金は高齢者にならなければ受け取れませんが、障害年金は現役世代でも受給できることが特徴です。
障害年金は、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。障害厚生年金に関しては、補足的に障害手当金という制度もあります。
気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。
障害年金については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
支援制度④特別障害者手当

特別障害者手当とは、精神または身体に著しく重度な障害があり、日常生活において常に特別な介護を必要とする在宅生活をしている人に対して、必要となる精神的、物質的な負担の軽減を目的に手当を支給する支援制度のことです。(参考:厚生労働省「特別障害者手当について」)
利用できる場合、2023年4月現在では、月額2万7980円を受給できます。
ただし所得制限があり、受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母など)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
申請は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口で行えます。
気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。
支援制度⑤心身障害者医療費助成制度
心身障害者医療費助成制度とは、精神または身体に重度な障害のある人の福祉の増進を図る目的で、各自治体が医療費の一部または全部を助成する支援制度のことです。「マル障」とも呼ばれています。(参考:東京都福祉局「心身障害者医療費助成制度(マル障)」、渋谷区ポータル「医療費の助成 | 障がい者の医療」)
一般的に、各種医療保険の自己負担から一部負担金を差し引いた金額または全額が助成されます。
心身障害者医療費助成制度を利用する場合は、交付された自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票が必要です。利用時はそれぞれ受診時に医療機関へ提示します。
自治体によって支援内容や受給条件などのルールが異なります。
気になる方は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にご相談ください。
双極性障害のある人が利用できる支援機関5選
ここからは双極性障害のある人が利用できる支援機関を5つ紹介します。
どのような支援機関があるのか知らないという人はぜひご利用ください。
支援機関①就労移行支援事業所

こちらでも解説しましたが、就労移行支援事業所の利用をオススメします。
就労移行支援事業所では、就職活動の手助けをしています。
就労移行支援事業所では、体調管理の方法、職場でのコミュニケーションの基礎スキル、就職に必要な専門スキルなどを学ぶことができます。
さらには、実際の就職活動でのアドバイス、就職後の職場定着支援も含む、総合的な就労支援を受けることが可能です。
キズキビジネスカレッジ(KBC)もそのひとつです。
就労移行支事業所については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。
私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、双極性障害のある人のための就労移行支援事業所です。
- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も
- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%
- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月
新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。
支援機関②精神保健福祉センター
精神保健福祉センターとは、双極性障害などの精神障害のある人のサポートを目的とした支援機関のことです。(参考:東京都福祉保健局「精神保健福祉センターとは」)
他の支援機関と比較して、精神疾患に特化している点が特徴と言えるでしょう。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」により、各都道府県に設置されています。(参考:e-Gov法令検索「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)
精神疾患に関連する悩みの相談や社会に適応するための指導と援助を行っています。
精神障害による症状で悩んでいる本人だけでなく、ご家族や周囲の人の相談も受け付けています。また、匿名での相談も受け付けています。医師から正式な診断を受けていなくても相談は可能です。
詳しくは、お住まいの自治体の精神保健福祉センターに問い合わせてみてください。
支援機関③地域障害者職業センター

地域障害者職業センターとは、病気や障害のある人に対して、職業評価や職業指導、職業準備訓練、職場適応援助などの専門的な職業リハビリテーションを提供する支援機関のことです。(参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センターによる支援」、厚生労働省「地域障害者職業センターの概要」)
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しており、障害者雇用促進法に基づいて、全国47都道府県に設置されています。
ハローワークや医療・福祉機関と連携しているため、仕事に関する相談や訓練、復職するためのサポートを行っています。
病気や障害に悩む当事者だけでなく、障害のある人を雇用する事業所に対して、雇用管理に関する相談・援助も行っています。
仕事を両立したい人や就労状況について相談したい人におすすめです。
支援機関④障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターとは、雇用や保健、福祉、教育に関する関係機関と連携し、障害のある人の雇用の促進・安定を目的とした一体的な支援を行っている支援機関のことです。(参考:厚生労働省「障害者雇用促進法制の整備について」、厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」)
障害のある人の就職活動の支援や求人の紹介、職場定着のためのサポートなどを行います。
就労面だけでなく、金銭管理などの経済面や生活面のことまで、日常および地域生活に関する支援も行っています。
生活習慣や金銭管理、健康管理などについても幅広く相談できるため、生活面のサポートも受けたい人におすすめです。
2023年4月1日時点で、全国に337箇所設置されています。
支援機関⑤ハローワーク(公共職業安定所)

ハローワーク(公共職業安定所)とは、仕事を探している人に対して、就労に関連するサポートを行っている支援機関のことです。(参考:東京労働局「東京ハローワーク」、厚生労働省「こころの健康サポートガイド」、厚生労働省「ハローワークにおける障害者の就労支援」)
主に職業相談や職業訓練、求人情報の提示などを行っており、具体的な支援内容は事業所によって異なりますが、一般的には以下のような幅広いサポートを行います。
- 仕事で活かせる知識・技能の習得
- 仕事や私生活で活かせるメンタル面のサポート
- 「どのような仕事や働き方が向いているのか」のアドバイス
- 転職先候補の業務や雰囲気を体験できる「職場体験実習(インターン)」の紹介
- 履歴書・経歴書・エントリーシートの作成支援
- 面接対策
- 転職後の職場定着支援
ハローワークでは、双極性障害に限らず、病気や障害のある人に向けた支援を行っています。障害者手帳が交付されていない双極性障害のある人などでも、専門医による診断書があれば支援を受けることができます。
ハローワークで求職登録を行うと、障害の特性や希望職種に応じた職業相談を受けられます。双極性障害があることや障害のある人向けの求人を探していることを伝えると、双極性障害のある人に向いていると思われる求人情報を紹介してもらえます。
ほかにも、「双極性障害がある状態でどのように就職活動をすればよいのか?」「面接や履歴書には双極性障害の経験をどのように記載すればよいのか?」など、双極性障害のある人の就職活動や履歴書の書き方、面接での双極性障害の伝え方など、細かい疑問も解決できます。
また、ハローワークには、住まいや生活に関する総合相談を行う窓口もあります。経済面や生活面などについても幅広く相談できるため、心配がある場合は相談してみましょう。
双極性障害とは?
この章では、双極性障害の概要や種類、症状、原因、診断基準、治療法について解説します。
双極性障害の概要

双極性障害とは、気分が高揚する「躁」状態と、気分が落ち込む「うつ」状態を繰り返す精神障害の一種のことです。かつては「躁うつ病」という名前で知られていました。(参考:こころの情報サイト「双極性障害(躁うつ病)」、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の精神疾患の診断・統計マニュアル』、加藤忠史『これだけは知っておきたい双極性障害 躁・うつに早めに気づき再発を防ぐ! ココロの健康シリーズ』、MedlinePlus「Bipolar Disorder」、MSDマニュアル家庭版「双極性障害」、国立国際医療研究センター病院「双極性障害とは?」、大塚製薬「双極性障害とは」)
医師や薬剤師向けのポケットマニュアルとして出版された『MSDマニュアル家庭版』では、双極性障害は、以下のように書かれています。
双極性障害(以前の躁うつ病)では、抑うつ状態と躁状態または軽躁状態(軽度の躁状態)が交互にみられます。躁状態は、過度の身体活動や、置かれた状況と著しく不釣り合いな高揚感を特徴とします。
双極性障害の発生率に性差の影響はありません。また、通常、10代から30代までに発症するとされており、小児が双極性障害を発症することは少ないそうです。
双極性障害には、大きく分けて以下の種類にわかれます。
主な違いは、「躁状態の激しさ」と「社会生活への影響」です。
双極性障害の種類①双極性障害Ⅰ型(双極Ⅰ型障害)
双極性障害Ⅰ型(双極Ⅰ型障害)とは、完全な躁状態を経験している双極性障害のことです。
双極性障害Ⅰ型(双極Ⅰ型障害)の躁状態は、日常生活への影響が大きく、社会生活に支障をきたす影響を及ぼすこともあるとされています。
双極性障害の種類②双極性障害Ⅱ型(双極Ⅱ型障害)
双極性障害Ⅱ型(双極Ⅱ型障害)とは、完全な躁状態を経験していない、うつ状態と軽い躁状態を経験している双極性障害のことです。
双極性障害Ⅰ型(双極Ⅰ型障害)の軽い躁状態は、社会生活に大きな支障はない程度の躁状態とされています。本人が気分の入れ替わりに悩んだり、周囲の人から「あの人は気分屋だ」と思われる程度で済むケースも多いです。
しかし、双極性障害Ⅱ型(双極Ⅱ型障害)の方が、双極性障害Ⅰ型(双極Ⅰ型障害)よりも軽症であるというわけではありません。
双極性障害Ⅱ型(双極Ⅱ型障害)のうつ状態は、重くて長い傾向にあるとされています。また、躁状態が認識しづらいのに対して、うつ状態が認識しやすいため、「うつ病」と誤診されて、慢性化しやすい傾向にあります。
双極性障害の症状:躁状態とうつ状態

双極性障害の症状は、躁状態とうつ状態で異なり、その両極を行き来するかたちで現れます。
具体的な症状としては、以下が見られます。
- 自分が偉くなったように感じる
- 気分が高揚しすぎて興奮する
- 怒りっぽくなる
- 普段の様子と異なるほど気分が高揚するため、他人から別人のように思われる
- 睡眠をあまり取らなくても平気になる
- いつもよりおしゃべりになる
- 色々な考えが次々に頭に浮かぶ
- 抑制が効かず、後先を考えずに楽しいことに熱中する(散財、賭博など)
- ほとんど一日中憂うつで、気分が沈んでいる
- ほとんどのことに興味や関心を失う
- 寝つきが悪かったり、夜中に目が覚める
- 話し方や動作が緩慢になる
- 気力が低下して疲労感が続く
- 自己肯定感が失われ、「自分には価値がない」と感じる
双極性障害では、躁状態とうつ状態が切り替わるタイミングで、躁状態とうつ状態の両方の症状が合わさる「混合状態」になることがあります。
具体的な症状としては、以下が見られます。
- ネガティヴなことを絶え間なくしゃべり続ける
- 夜に不安や焦燥感に駆られて、街を徘徊する
- 気分が高揚しているが涙ぐむ
混合状態では気持ちのコントロールが難しくなるため、乗り越えるためには医師や医療機関などのサポートが必要な場面もあります。
こうした躁状態とうつ状態の落差が大きくならないように心掛けることが大切です。
生活の上では、その日の出来事や気分を日記につけるなどして、あなたなりに躁とうつの病相変化のタイミングを少しでも掴んでおくとよいでしょう。
双極性障害の原因
双極性障害を発症する原因は今のところ分かっていません。(参考:MSDマニュアル家庭版「双極性障害」)
『MSDマニュアル家庭版』によると、双極性障害の発症には、遺伝が関与していると考えられています。また、神経細胞が情報を伝達する際に必要な物質である神経伝達物質が正常に調節されていない可能性があるようです。
双極性障害の診断基準

『DSM-5』では、双極性障害Ⅰ型(双極Ⅰ型障害)と双極性障害Ⅱ型(双極Ⅱ型障害)の診断基準は、以下のとおりです。(参考:日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の精神疾患の診断・統計マニュアル』)
- 躁エピソードを1つ以上確認できる
- 軽躁エピソード、抑うつエピソードの有無は問わない
- 躁エピソードが確認できない
- 軽躁エピソードを1つ以上確認できる
- 抑うつエピソードを1つ以上確認できる
ただし、いずれかの症状がみられる場合であっても、自身で双極性障害と判断することは危険です。
どの程度なら「当てはまる」と言えるのか、他の病気や障害の可能性はないかなども含めて、「ある人が双極性障害かどうか」は、医師だけが判断できます。
生活するうえで懸念があるとき、気になることがあるときは必ず専門家による検査を受けましょう。
双極性障害の治療方法

双極性障害は、早期から治療を開始すれば、症状を調整しながら仕事をすることも可能な病気です。
双極性障害の治療は、躁状態とうつ状態から回復して、再発を予防することが目的です。
双極性障害は再発を繰り返すたび、次の再発までのサイクルが短くなり、悪化しやすい傾向にあります。そのために、再発を予防することが最も重要です。
双極性障害の治療方法として、主に以下の2種類が用いられます。
- 薬物治療:気分安定薬や抗精神病薬を使用する治療
- 心理社会的治療:病気を受け入れコントロールできるようになることが目的の治療。家族など支援者と行う集団療法や、双極性障害のある人のみで行う個人療法などの手段がある
補足:かつて躁うつ病という名で知られた双極性障害とうつ病の違い
双極性障害は、かつては「躁うつ病」という名前で知られていたため、「うつ病」の一種と誤解されてきました。しかし、双極性障害とうつ病は別の疾患です。治療法も異なります。
例えば、うつ病の主な治療薬は抗うつ薬ですが、双極性障害の主な治療薬は、こちらで解説したとおり、気分安定薬と抗精神病薬です。
今でも双極性障害であるにも関わらず、うつ病と誤診されるケースは少なくありません。
うつ病と診断されたが、なかなか治らず、気分の入れ替わりが激しいという人は、一度セカンドオピニオンを求めて他の先生の診察を受けるのもひとつの手段でしょう。
その際は、代替医療や民間療法ではなく「病院」で診察を受けることが大切です。
まとめ:双極性障害でも上手に障害とつきあえれば仕事を続けられます

双極性障害であっても、病気を受け止めて、適切な予防措置を取っていれば、仕事を続けていくことは可能です。
そのときには、あなた自身では気づかない変化を掴むために、専門医やご家族、支援者といった周囲の人を頼ることが大切です。
ぜひ、ひとりで抱え込まずに、周りにいる人に相談するようにしてください。
このコラムが双極性障害によるお仕事の悩みを抱えているあなたの助けになれば幸いです。
双極性障害とはなんですか?
双極性障害とは、気分が高揚する「躁」状態と、気分が落ち込む「うつ」状態を繰り返す精神障害の一種のことです。かつては「躁うつ病」という名前で知られていました。
詳細については、こちらで解説しています。
私は双極性障害がありますが、仕事を続けたいです。
双極性障害のある人が仕事を続けるコツについては、以下が考えられます。
- 医師や支援者の意見にきちんと耳を傾ける
- 疾患を受け入れる
- 体内時計を整える
- できるだけ残業を避ける
- 休暇取得日を月初めに決めておく
- つらい状況を家族に共有する
- 異動・転職を視野に入れる
詳細については、こちらで解説しています。
監修キズキ代表 安田祐輔
発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。
その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。
【著書ピックアップ】
 『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』
Amazon
翔泳社公式
【略歴】
2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)
2015年 株式会社キズキ設立
2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)
【その他著書など(一部)】
『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』
日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』
現代ビジネス執筆記事一覧
【メディア出演(一部)】
2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)
執筆寺田淳平
てらだ・じゅんぺい。
高校2年の春から半年ほど不登校を経験。保健室登校をしながら卒業し、慶應義塾大学に入学。同大学卒業後の就職先(3,500人規模)で人事業務に従事する中、うつ病を発症し約10か月休職。寛解・職場復帰後、勤務を2年継続したのち現職のフリーライターに。
2019年に一般財団法人職業技能振興会の認定資格「企業中間管理職ケアストレスカウンセラー」を取得。
サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)
うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→






